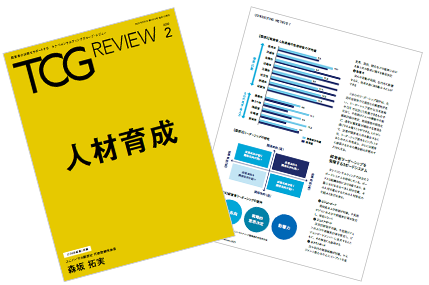人材育成が企業の未来を左右する時代に
企業を取り巻く環境は、大きく変化しています。少子高齢化による労働力不足の深刻化、インフレによる原価の高騰、生成AIをはじめとしたデジタル技術の進化など、企業には刻々と変わりゆく変化の中で柔軟な対応が求められています。一方で、後追い的な対応に終始していては、企業の中長期的な成長は成し遂げられません。環境変化を前提とし、柔軟に、かつ能動的に企業を変えていくことが重要です。そのためには、未来志向を持ち、全社最適で判断し、持続的に変革を起こしていく力を持つ人材が求められています。

食品製造業が直面する人材育成の課題
①機能別組織が生む「視野の限界」
多くの食品製造企業では、商品開発、製造、品質管理、営業などの機能別に分けられた機能別組織を採用しています。この組織構造は、効率的なオペレーションを可能にし、品質や安全の担保がしやすいというメリットがある一方で、部門間の壁が出来やすいというデメリットがあります。
結果として、社員が「自分の部署のことはよくわかるが、全社の動きや経営の意図までは分からない」という状況に陥りやすく、経営層に必要な全体最適の思考が育ちづらいという課題があります。
②「安全・安心」の価値観による変化への慎重さ
食品業界は、言うまでもなく「安全・安心」の担保が最優先の業界です。異物混入や食中毒など、企業の存続に関わるリスクが常に存在しています。そのため、食品製造業の現場では「決められた手順を正確に守ること」が強く求められ、ミスやイレギュラーな事態を避ける思考が根付いています。これは安全・品質の維持においては有効に働く一方、「変化や挑戦を避ける文化」を生み出しやすいのが実情です。

これからの時代に求められる能力とその磨き方
これからの食品製造業に必要なのは、安全・安心を支える現場力を持つ人材に加え、「経営視点を持ち、変化を起こす力」を持つ人材です。
具体的には、以下のような力が求められます。
・全社を俯瞰する視座
・長期的視野に基づく思考力
・現状に捉われずあるべき姿を再定義する力
・周囲を巻き込みスピード感を持って進める推進力
・常に学習し続け情報をアップデートする姿勢
これらは、日常業務の中だけで養うのは難しいことが多く、意図的な育成施策が不可欠です。
本コラムでは、このような力を身に付ける施策について、「越境学習」の観点からポイントを示します。
①越境学習・ジョブローテーションの導入
社員に全社視点を持たせ、経営を担う視座を育むには、特定の業務や部門に特化した経験だけでは限界があります。そこで有効なのが、「越境学習」と「ジョブローテーション」です。
経済産業省では、越境学習を「自分がもともと所属している組織を一時的に離れ、別の組織や地域コミュニティで実際に業務やプロジェクトに関わることで、新たな知識や視点、スキルを獲得する学習」と定義しています。例えば、製造部門の社員が営業や商品開発に関わるといった社内越境に加え、異業種交流研修や外部プロジェクトへの参加など、社外の人材との接点を持つ社外越境も高い効果を得ることができます。他社や異業種の価値観や課題意識に触れることで、社員は自社の常識に捉われずに、主体的に問いを立てられるようになります。
一方、ジョブローテーションは、意図的に担当業務や所属部門を変える仕組みです。特に、若手・中堅社員に対しては、ジョブローテーションを通じて自社内の多様な業務や部門の繋がりを体感させることが、全体最適の視点を持つ土台になります。製造・品質・営業・企画というような幅広い領域を経験することで、全社の業務プロセスを理解しながら「自らの仕事の位置づけ」を理解しやすくなります。
ジョブローテーションは、いわゆるゼネラリスト人材の育成に効果を発揮しますが、近年はジョブ型雇用が浸透しつつあり、より高い専門性を持った人材が求められるケースも多いでしょう。越境学習は社員の専門性を損なうことなく、大局的な視野を身に付けるのに効果を発揮します。

越境学習としての効果を生み出す「3ボードシステム」
こうした広い視野を持ち変化を起こす力を養う手法として、タナベコンサルティングが提唱する「3ボードシステム」があります。3ボードシステムとは、広い視野を持つ経営人材の育成に有効な実践型育成システムであり、「ビジョンボード」「ジュニアボード」「ネクストボード」の3つから構成されます。
①ビジョンボード
現経営陣が中心となり中長期ビジョンの策定を行うことを指します。経営陣が日常業務から離れ、長期的視野で未来を構想するためのディスカッションと意思統一の場となります。例えば、市場環境の変化を踏まえた自社のビジネスモデルの再設計や次世代への事業承継構想の議論など、経営者としての重要事項の議論と意思決定を行う場となります。自身の担当部門の枠組みを外し、全社的な視野から議論・意思決定を行うことで、現経営陣の経営視点の向上を目指すプログラムです。
②ジュニアボード
次世代の経営幹部(役員候補)を選抜し、経営視点で全社課題に向き合い、提案力と当事者意識を高めることを目的としたプログラムです。取り扱うテーマは中長期ビジョンの策定に限らず、働き方改革や採用など、自社の経営課題を踏まえた設定を行い、決定事項を役員へと上申します。ジュニアボードでは、経営テーマについて複数部門のメンバーと議論することで、全社視点や他部門の視点を養うとともに、役員への上申を通じて経営に参画するという当事者意識の醸成を図ることを大きな目的としています。
③ネクストボード
ネクストボードは、主に若手幹部やその候補者を対象とし、自社の経営テーマについて議論するプログラムです。ジュニアボードがアウトプット主体の取り組みである一方、ネクストボードはインプットを主体としており、若手幹部の育成に効果を発揮します。
これら3ボードシステムは、部門最適に陥りがちな機能別組織においても「全社的視点で考える場」を意図的に設けることが大きなポイントです。また、安定重視・安全志向の高い文化の中においても、経営目線での変革・改善策を導き出し、変化を起こす訓練の場となります。このようなプログラムは、日常業務の中では獲得し得ない越境学習としての効果を発揮します。
一つの事例として、宮城県仙台市に本社を構える食品製造業A社では、次世代経営幹部を対象としたジュニアボードに取り組んでいます。同社は複数のグループ企業から成り立っており、グループとしての企業成長に備えて各社の将来を担う役員候補者を育てるとともに、10年ビジョンを策定し、高収益ビジネスモデルへの変革を目指しています。この取り組みで、複数部門メンバーから多角的な意見が交わされ、新たな事業アイデアが生まれています。
さいごに
食品製造業においては、構造的な課題から「経営視点を持ち変化を起こせる人材」の育成は容易ではありません。このような人材の育成を期待するのであれば、組織的な育成の仕組みが不可欠です。本コラムで紹介した「3ボードシステム」を含む越境学習を有効に活用し、経営視点と変化創造力を持つ人材の育成に踏み出す企業こそが、これからの食品業界をリードしていくのではないでしょうか。
関連情報
-
課題解決人材育成の見直し方
-
課題解決製造業における「成長する」人事評価制度策定のポイント
-
課題解決製造業における人事制度の構築ステップと導入事例
-
課題解決間違った若手人材育成と離職防止策
-
課題解決製造業における人事制度の特徴と構築ポイント
-
課題解決製造業における人事制度改定の課題
-
課題解決建設業における若手・人材育成の重要性と育成方法
-
課題解決食品製造業・食品メーカーにおける人事制度構築のポイント
-
課題解決製造業で成功する賃金制度構築とは
-
課題解決製造業における人事制度の成功事例
-
課題解決電気工事会社で社員の自主性を高める人材育成事例
-
人事コラム効果的な人材育成ロードマップの作成方法とは?
-
人事コラム中小企業における人材育成の重要性とは
-
人事コラム【2024年最新】人事トレンド最前線~人材育成~
-
人事コラム従業員のモチベーション向上に繋がる『人材育成における大切なこと』
-
人事コラム効果的な人材育成計画の立て方
-
人事コラム人材育成における目標設定の重要性とその具体的方法
-
人事コラム企業研修の課題と解決策/成功する人材育成のポイント
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング
ゼネラルマネジャー三浦 秀
飲料業界で法人営業・事業企画・マーケティング・マネジメントを経験後、当社へ入社。建設・住宅関連企業への中期ビジョンの策定、アミューズメント・小売・自動車関連企業等の幅広い業種における人材育成・人材採用支援・現場改善のコンサルティングに携わる。
- 主な実績
-
- スタンダード上場企業における人事制度策定コンサルティング
- 上場小売企業への人材育成支援
- 建設業界の中期経営ビジョン策定コンサルティング
- 中堅自動車関連企業への現場改善支援コンサルティング

 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト