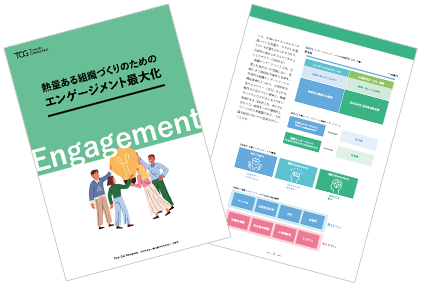人事コラム
モチベーション向上に繋がる『人材育成における大切なこと』
人材育成に欠かせない「モチベーションマネジメント」

モチベーションとは何か?
「モチベーション」とは、目標に向かう原動力となるものであり、「やる気」「動機」「意欲」等と訳されることが多い。恐らく、このモチベーションという言葉を聴いたことが無いという人は殆どいないであろう。
モチベーションについては、アメリカを中心に1900年代の初頭より様々な研究が行われてきた。古くは、1911年にフレドリック・テーラー氏が、人は金銭によって動機づけられるとして科学的管理法を提唱した。それ以降、ダグラス・マクレガー氏の「XY理論」、フレデリック・ハーズバーグ氏の「二要因理論」等、様々な理論が提唱されてきた。その中でも一番有名なのはアブラハム・マズロー氏が提唱した「欲求段階説」であろう。欲求を5段階に体系化し、「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「自我の欲求」「自己実現」の順番で欲求が満たされていき、一つ上の欲求を満たすことに人は動機付けされているとしたものである。

部下のモチベーションは上司の責任か?
ビジネスにおいて言うと、会社と従業員は雇用契約を結んでおり、従業員は会社の規則を守りつつ課せられた目標を達成し、それに対する報酬を会社から受け取ることになる。そのため、従業員が会社(上司)の指示に従って全力を尽くすのは責務であり、本来そこにモチベーションの高低を持ち出すべきでは無いのかもしれない。
しかしながら従業員も感情を持った人間であり、モチベーションの高低により、どうしても生産性に影響が出てしまうという側面もある。
結論から言えば、部下のモチベーションは上司の責任ではないが、部下の成果(パフォーマンス)に対する責任を追っている以上は、部下のモチベーションマネジメントは上司にとっての腕の見せ所であると言える。
ダニエル・ピンク氏の「モチベーション3.0」
ダニエル・ピンク氏の著書「モチベーション3.0」によれば、モチベーションは3段階あるとされている。モチベーション1.0は、働かざるは食べるべからずという時代にあって、働かないという選択肢が有り得ない状態。モチベーション2.0は、工場(オフィス)時代にあって、働けば報酬を貰え、働かなければ罰則を与えられる状態。そしてモチベーションは、動機付けが無ければ働かないという状態である。今は生活に必要な物はほぼ全員に行き渡り、食べることにも困らない時代であり、このような時代に「ここで働く」という選択肢を取るには、それ相応の理由がいると言うことである。
更には、モチベーションの3要素として下記3つが重要であると説いている。
- 1. 自主性(仕事おける裁量の度合い)
- 2. 成長(上達の実感)
- 3. 目的(仕事の意義(何のため、誰のため)の腹落ち)
メンバーがこれらを得られるように、会社として上司としてサポートしていくことは、人材育成において非常に大切なポイントである。

上司が行うべき「モチベーションマネジメント」
部下のモチベーションの3要素を満たしていくためには、上司として下記の様なことを意識すると良い。
1.自主性
元サッカー日本代表監督の岡田武史氏は、次の様に説いている。「守」の段階ではティーチング、「破」の段階ではコーチング、「離」の段階では機会の提供が有効であると。まずはティーチング(教育)で型を教え、コーチングで気付きを与えながら工夫させ、最後に機会を与えて自由にやらせるということである。自主性を育むにはそのための機会が欠かせず、例え小さな範囲であっても、上司は部下を高速で守破まで導き、離にチャレンジさせるという心構えが大切である。
2.成長
一昔前は寿司職になるのに10年掛かると言われたが、今の若い世代はとてもではないが10年も待つことはできない。特に意欲の高い人材は、自分の市場価値を高めることに強い意識を持っているため、成長を実感できなければ、すぐに環境を変えようとする。ここで上司がやるべきは、部下の実力に対して少し上の難易度の仕事を与えることと、フィードバックをサボらないことである。特にフィードバックは重要であり、上司と部下が2人3脚で成長していくという心構えが大切である。
3.目的
良いからやっておけではなく、なぜそれをやる必要があるのか?(目的・背景)を伝えることで、部下は納得し、モチベーション高く仕事に取り組むことができるようになる。その分、当然コミュニケーションコストは高くなるが、目的を理解することは、自発的な行動やアイデアに繋がり、仕事を通じて部下が成長することに繋がっていく。
まとめ
以上、モチベーションマネジメントの重要性について書いてきたが、「ここで働く理由」が見つけ辛い時代だからこそ、モチベーションを軸とした人材育成の在り方を考え直し、人材を育成→活躍→定着へと導いていく必要がある。
部下(組織)のモチベーションを高め、育成しながら目標達成に導いていけるリーダーは、これからの時代、益々重要になってくるだろう。
本事例に関連するサービス

Engagement KARTE
(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)
人的資本投資において重要となる指標を明確化し、人的資本経営の推進と企業価値の向上をサポートします。
Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)の詳細はこちら
関連動画
関連情報