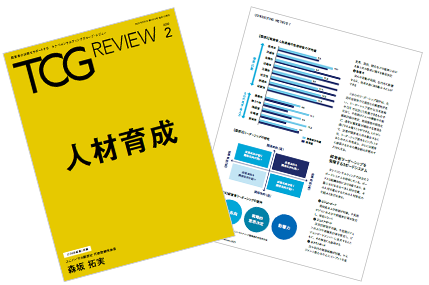人事コラム
企業における成長戦略としての女性活躍
― 大局着眼・小手着手が鍵となる
近年、ダイバーシティ経営の一環として、女性活躍推進が官民問わず主要なテーマとして再注目されている。
その背景には、先進的に女性活躍に取り組む企業において、
企業価値の向上や人材基盤の強化といった成果が、
「経営として打った手の差」として明確に表れていることがある。

経営戦略の視点 ― 女性活躍推進による企業価値向上と人材獲得力の強化
企業価値向上という観点においては、女性取締役がいる企業の方が、いない企業に比べて株式パフォーマンスが良好であるという傾向が示されている。特にリーマンショックやコロナショックといった厳しい環境変化の中でも、回復力において明確な差が見られた。
これは、意思決定層に多様な視点が加わることで、取締役会における健全な議論と独立性が確保され、コーポレートガバナンス機能が強化されるためである。多様性の導入は、単なる女性登用にとどまらず、経営基盤を強化する戦略的要素としての認識が進んでいる。
人材獲得力の強化という観点においても、女性活躍は注目されている。あさがくナビが実施した2024年3月卒大学生に対する調査では、82.7%の学生がDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)を推進する企業に好感を抱いていると回答している。今や、多様な人材が活躍できる企業は求職者に対しての企業ブランディングの一部であり、選ばれる企業の条件となっている。
従来のように右肩上がりの経済成長を遂げてきた時代においては、同じ考え、同じ行動ができる同質性の高い集団というものが重宝されてきたが、不確実性の高いVUCA時代においては集団を形成する中で、多様性が重視されてきている。女性活躍推進は「単なる社会的配慮」ではなく、VUCA時代において、企業成長に直結する戦略的テーマへと変化してきている。

組織・制度の視点 ― 段階的導入と部門横断で"仕組みを育てる"
女性活躍を進めるうえで、フレックスタイム制や男性育休制度などの制度整備は重要な出発点である。しかし、それ以上に求められるのは、制度を"運用できる仕組み"として社内に定着させることである。 制度が「存在する」ことと「活用されている」ことの間には大きな乖離がある。単に制度を導入しても、前例がなければ運用されず、現場に定着しない可能性が高い。ゆえに、段階的かつ試験的に制度を導入し、社内で育てていく姿勢が不可欠となる。
たとえば、ある中堅製造業では、「女性を現場に配置する」という発想自体がなかった。そこでまず、部門間コミュニケーションを目的に社内インターンシップ制度を試験導入した。結果として、女性も現場で力を発揮できるという実感が生まれ、女性製造職の採用へとつながる制度化へと発展した。また、ある建設業では、DX(デジタルトランスフォーメーション)プロジェクトを契機に、部門横断的な業務改革が進んだ。生産性向上のために業務の平準化・可視化・再設計を行い、女性ならではの視点を活かした技術者育成の仕組みが構築された。
このように、「試験運用→検証→制度化」というプロセス設計そのものが成功要因となる。特にダイバーシティ経営に関わる制度は、形だけ導入しても形骸化しやすいため、関係者の納得と現場の実感を伴う段階的アプローチが有効である。
制度の導入はゴールではなく、「機能させる」「育てる」ことが本質的な目的である。自社の状況に応じて柔軟に制度を設計・運用することが、最終的な実効性を高める鍵となる。

風土・意識の視点 ― 取り組みを発信し、外圧で内部の変化を醸成する
制度を整備しても、職場風土や個人の意識が変わらなければ、女性活躍は定着しない。ここで重要となるのが、外圧を内部変革の契機とする視点である。
女性活躍・ダイバーシティ推進においては、経営層が「自社の持続的成長には多様性が不可欠である」と明確に発信し、戦略方針に組み込むことが求められる。そのうえで、管理職層(ミドルリーダー)がそのメッセージを現場で具体的な行動に落とし込むことが、企業風土を変える決め手となる。
ある中堅製造業では、後継経営者こそダイバーシティ経営に積極的だったものの、他の経営層には十分に理解が浸透しておらず、制度導入も限定的であった。しかし、現場のミドル層が中心となり、小さな打ち合わせや対話を積み重ね、女性社員の声を拾い、改善提案を仕組みとして構築した。
さらに、こうした取り組みを業界紙の取材対応や表彰制度への応募を通じて社外に発信することで、女性活躍推進企業としての社内外の認知度が高まり、経営層も変化を無視できない状況となった。外圧を通じた意識変革が、社内の女性活躍推進を後押しするかたちとなった。
このように、現場の積み重ねと外部発信の連携が、組織風土の変革を実現する要因となる。
また、「女性だから支援する」のではなく、「多様な人材が成果を出せる仕組みを整える」という発想を社内に浸透させることで、性別や年齢を問わず、能力と意欲に応じた機会が公平に提供される組織へと進化していく。
まとめ ― 多様な人材が活躍し、成長する組織づくりに向けて
日本社会は今、人口減少局面の入口に立っている。特に2030年以降は労働人口の急激な減少が予測されており、企業が持続的に成長するためには、多様な人材が活躍できる風土と制度の整備が不可欠となる。
女性活躍推進は、その第一歩である。それは単なる制度整備にとどまらず、経営戦略・組織設計・文化醸成を一体的に推進する必要があるテーマである。
この取り組みを進める上で最も重要な姿勢が、「大局着眼・小手着手」である。
経営理念やビジョンに基づいて、多様性推進の方向性を明確に定めながらも、現場では会議体の見直しや日常の対話といった"小さな実践"を継続して積み重ねることが、女性が活躍する企業文化の醸成に直結する。
本事例に関連するサービス

教育体系構築・人材育成体系
構築コンサルティング
人材育成方針および人事制度との連動性を図りながら、各階層・各等級別に必要な教育・育成内容を整理・明確化させ、最適な能力開発機会を提供するための体系を構築します。
教育体系構築・人材育成体系構築コンサルティングの詳細はこちら
関連動画
関連情報