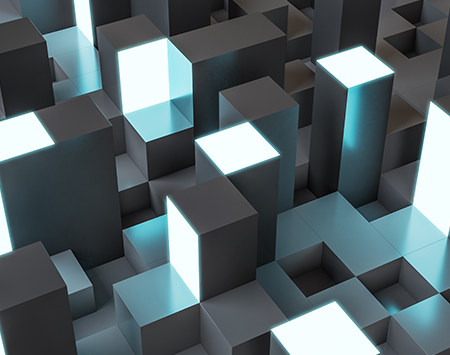人事コラム
年功序列制度とは?
年功序列制度から等級制度への改革
企業文化と社員モチベーションに好影響を与える

年功序列制度・等級制度とは
人事考課という言葉が文献に出始めたのは、1930年代だと言われている。その後、日本は戦争を経験し、戦後から復興、更には高度成長を成し遂げるためには、会社は社員の雇用を守る必要があった。そのため、いわゆる日本型雇用システムと呼ばれる「①新卒一括採用、②年功序列の昇進・賃金システム、③終身雇用」(三種の神器)が出来上がっていった。この仕組みは、若い人口が増え、右肩上がりの経済成長期には非常に合理的であった。供給量を増やすことで売上向上が期待できたため、社員には、同じような処遇・教育を実施し、分かりやすいキャリアステップを準備することができた。
時代は進み、現在はご存知の通り、GDP成長率は僅少の水準、生産年齢人口の減少、少子高齢化社会となり、更に市場環境変化の激しさからVUCAの時代とも言われている。提供サービス・商品のライフタイムサイクルは短くなっており、常にアップデートが求められている。働く人々には同じことを画一的に求めるのではなく、それぞれが必要とされる役割を理解し、何をすべきか自発的に考えることが求められている。
ここで、人事制度における「等級制度」を紹介する。「等級」という階層を設定し、働く社員それぞれの能力や役割に合わせた格付けを行う仕組みを指す。等級でそれぞれの社員の力量が把握でき、人材配置・教育・採用を実施しやすい特長がある。
戦後復興から長らく主流であった日本型雇用システムは現代において、不満を多く生んでおり、年功序列制度から等級制度への改革が進んでいる。2つの大きな違いは、処遇決定の根拠である。年功序列は年齢・勤続年数に基づき、等級制度は等級ごとに設定された能力・役割に基づく。改革が進む理由として、現代社会において、変化が激しく、年齢・勤続年数(経験)があることと成果を出すことができることとは、イコール関係ではなくなっている点にある。成果の少ない年長者に対し、高い賃金を払い続ける余裕は企業になく、若手人材からの不満にも繋がる。成長や成果に対して分配をする考え方がより明確になってきていると言える。
社員モチベーションの変化と企業文化への影響
等級制度のメリットでも触れたが、それぞれに求めることを提示し、それを成長を後押しする仕組みにしていくことで成長が処遇に反映できる運用が可能となる。結果として、社員は働きがいを感じ、モチベーションアップに繋げることができる。これは前向きな雰囲気を作り、良い循環が生まれる。また、等級制度で求める能力・役割(以後、等級要件)を社員が体現していくことで社風になる。例えば、新しい取り組みを考える役割を求め続けると、新しい企画を生み出すことが文化になり、それが武器の会社になっていく。ここでのポイントは、等級要件が、事業戦略から落とし込まれたものになっているかである。
これをタナベコンサルティングでは、経営のバックボーンシステムと呼んでいる。企業のありたい姿から事業戦略を設定し、それに基づき人事戦略の設定、人事制度へ落とし込む。社員の頑張りや成長が事業戦略を推進し、企業のありたい姿の実現に繋がる構図を生み出すことができる。当然であるが、事業戦略は環境変化に伴って変えるべきものであり、それに伴って人事制度も合わせてアップデートをすべきである。年齢や社歴に関係なく、為すべきことを実践できている社員が報われ、更なる成長機会を提供していく。これこそが変化の激しい現代において、必要な人事施策だと言える。

等級制度導入のステップ
等級制度導入に向けて、以下のステップで検討を進めていく。
①経営理念・ミッション・ビジョン・バリューの上位概念を整理
↓
②自社の強み、競争環境を考えた上で、事業戦略を設定
↓
③事業戦略を推進するために必要な人材と人事方針(人事ポリシー)を設定
↓
④人事ポリシーを踏まえ、人事フレームを設計
※コース別、職種別、ステージ別、単線・複線型、働き方 など 制度の骨子にも多様な選択肢がある
↓
⑤人事フレームと合わせて必要な階層を設定し、等級とする
↓
⑥等級要件を1つずつ作成し、その達成度・発揮度を測る評価制度・昇格制度を作る
↓
⑦⑥に基づき、賃金制度を設計していく(基本給与、諸手当、賞与、退職金、トータルリワード など)
等級要件は、大きく分けると3種類あり、職能・役割・職務で設定をする。各等級に求めることを鑑み、全等級同じケースもあれば、職能+職務のようにミックスをするケースもある。コンサルティング現場では、役割をベースとしながら、若い等級では職能の考え方を取り入れるケースが多く、これは日本企業には馴染みやすい。
さいごに
この数年で相談が増えているのは、現役世代の社員向けと合わせて、定年退職後の人材活躍のための制度である。
これまでは、シニア層に求めることが明確になっていない企業が多く、処遇も限定的になることから、モチベーションが保ちにくい状況を生んでいた。しかし、労働人口が減少し、採用にも苦戦する企業が増え、シニア層にも活躍を求め、戦力として考えるようになってきたと言える。シニア層についても等級制度を導入し、求める能力・役割を明確にしていくことで、モチベーションを維持し、活躍したシニア社員には昇給・昇格・賞与を設定する企業が増えつつある。
どの世代でも働く社員が迷いなく、自身のキャリア・活躍がイメージできる組織づくり
これから選ばれ、生き残る会社とは、これが出来る会社であると明確に言える。今一度、社員に明確なメッセージを出せているか、自社の現状を確認して欲しい。