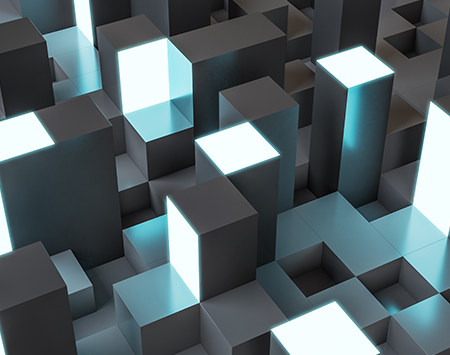事業モデルや顧客層、職員の特性を正しく捉え、
最適な人事制度を描く

金融機関の業界を取り巻く環境変化と人事制度見直しの必要性
働き方改革、人的資本経営、DE&I、コロナ禍など人材マネジメントを取り巻く環境は大きく変化しており、その影響で人事制度を見直す企業が増えている。金融機関も同様で、ジョブ型人事制度を導入する銀行も出てきているが、銀行だけでなく信用金庫や信用組合でも人事制度を見直すニーズが高まっている。
本コラムでは銀行と信用金庫で求められるスキルについて触れながら、信用金庫の人事制度改革について述べるが、まずは信用金庫を取り巻く環境変化について見ておきたい。
(1)地域社会・顧客基盤の変化
地域社会の人口減少と高齢化が進んでいる。また、地域の中小企業で後継者不足が深刻化し、廃業する企業が増える恐れがある。これらの状況が進むと信用金庫の顧客基盤が縮小してしまう。そのため、個人顧客には高齢者向けの金融商品・サービス、その他ライフプランに応じた金融商品・サービスなど、法人顧客には事業承継やM&A支援の強化、地域社会には地方創生プロジェクトなどの地域経済活性化に向けた取り組みへの積極的な関与が求められている。
(2)デジタル化の進展
フィンテックの台頭やAI・データ分析の活用が進む中、信用金庫でも業務効率化や顧客サービスの高度化が求められている。これに伴い、職員に求められるスキルセットが変化し、デジタル人材の育成が必須となっている。また、個人・法人顧客がオンラインでの金融取引を好む傾向が強まり、信用金庫でもデジタルチャネルの整備やセキュリティ対策を強化する必要がある。
(3)採用競争力の激化と人材不足
人材確保と競争力強化を目的として、初任給の引き上げや賃上げが相次いでいる。金融業界では、特に都市銀行や地方銀行などの銀行が顕著で、銀行と信用金庫で賃金水準に差が出始めている。このままでは人材不足が深刻化することが考えられ、賃上げは継続的に行いながらも、業務効率化などによる人材不足への対応、一般職(事務職)の縮小と総合職への転換なども検討しなければならない。

銀行と信用金庫に求められる人材の違い
銀行と信用金庫は、どちらも金融機関としての役割を果たす点では変わりなく、顧客志向や変化対応力は共通して求められるスキルになるが、事業モデルや顧客層の違いから、求められるスキルや人材育成の方向性に違いがあることを理解しておくが重要である。
(1)信用金庫に求められるスキル
①ゼネラリスト(多様な業務スキル)
信用金庫では、法人営業から個人向けサービスまで幅広い業務を担当することが多く、柔軟に対応できるスキルが求められる。そのため、一つの分野の専門性を極めるよりも多くの分野の専門性を広く習得しているゼネラリスト人材が人材育成の方向性となる。
②地域貢献意欲
信用金庫は地域社会や中小企業の発展を支援することを使命としており、地域イベントやボランティア活動への参加などもある。地域社会への貢献意欲が高く、地域住民や地元企業との信頼関係を築ける人材が求められる。
③コミュニケーション能力
地域の中小企業や個人顧客に寄り添い、ニーズを深く理解するための対話力が重要となる。
(2)銀行に求められる人材
①スペシャリスト(専門性の高さ)
銀行は、法人向けの大規模な融資や投資銀行業務など、専門性の高い業務を行うことが多いため、特定分野における深い知識やスキルが求められる。また、ネット銀行も増え、銀行のサービス領域も拡大させている状況であるため、他社との差別化や付加価値の向上を実現できるスペシャリスト人材が人材育成の方向性となる。
②デジタルスキル
デジタル化が進む中、今後はフィンテック関連のスキルに加えて、AI活用ができる人材が求められる。
③競争力のある営業力
銀行は全国規模での競争が激しいため、顧客を獲得するための営業力や交渉力が重要である。

信用金庫の人事制度再構築5ステップ
前述のとおり、信用金庫はゼネラリストの育成が人材育成の方向性であり、ゼネラリストを輩出する人事制度を構築することがポイントである。構築の基本ステップとして、次の切り口を順に見ていく。
(1)現状分析 (2)求める職員像・人事ポリシー策定 (3)制度詳細設計 (4)制度導入と職員周知 (5)定期的な制度改善
(1)現状分析
職員アンケートやヒアリングを通じて、現行の人事制度における課題を明確化する。キャリア形成、働き方の柔軟性、評価の納得感に関する課題などを分析する。また、金庫の将来ビジョンや成長戦略を実現するために必要となる人材レベルと人数が充足しているか、賃金水準は業界やベンチマークと比較して高いか低いか、生産性や労働分配率が適正かなど、あるべき姿とのギャップも分析する。これらの情報をもとに、金庫の課題を整理し、今後の設計の方向性を明確化する。
(2)求める職員像・人事ポリシー策定
地域密着型金融機関としての使命や成長戦略を実現する人材ビジョン(求める職員像)と人材マネジメントや人事制度設計の基本方針(人事ポリシー)を定義する。筆者がご支援している先では、求める職員像では「地域貢献」「自律」「チームワーク」「コミュニケーション」など、人事ポリシーにおいては「能力・役割・成果発揮に応じた公正な評価・処遇」「年功からの脱却」「職員のキャリア形成支援」「挑戦を後押しする」などのキーワードが挙げられることが多い。
(3)制度詳細設計
求める職員像・人事ポリシーを判断基準として、等級・評価・賃金の各制度を詳細設計する。これらは各々が独立した制度ではなく、連動していることが重要である。例えば、等級で職能資格等級制度を採用するのであれば、評価では能力発揮を評価する、賃金では能力給を採用する、ということになる。なお、制度設計のベースとなる思想は3つに区分されるが、それは能力(職能)、役割、職務の3つ。この3つのいずれかを採用することになる。ただし、最近では一般階層を能力、管理職を役割、専門職を職務の思想を取り入れるなどのハイブリッドパターンを採用することも多い。 上記が考え方のベースとなっており、信用金庫の代表的な制度設計パターンについては、前提として職群は管理職・専門職・総合職・一般職の4職群で設計することが多い。なお、ここでいう専門職とは職務限定職のような位置づけではなく、あくまでも高度な専門スキルを持つ職群である。
①事例A すべての職群で役割等級制度
シンプルに役割と処遇を一致させ、担う職務や役割を上げていく方向で人材マネジメントを行う。
なお、一般職は縮小(将来的に廃止)する方向で設置し、総合職転換のための育成を金庫として強化。
②事例B 管理職:役割等級制度 総合職・一般職:職能資格等級制度 専門職:ジョブ型
総合職・一般職は能力習熟段階、それよりも上の管理職や専門職は成果発揮段階として、その思想に合う等級区分を採用。
③事例C すべての職群で職能資格等級制度+役職任命制度
能力の習熟をベースとしつつ、役職は任命制にすることでフレキシブルな運用が可能な仕組みを構築。
(4)制度導入と職員周知
タナベコンサルティングではご支援先に設計3割、運用7割と伝えているが、人事制度の成功は設計よりも運用が肝である、という意味で伝えている。そのため、導入時と導入後のフォローが非常に重要である。
制度導入時には、職員への説明会や評価者・被評価者研修を実施し、制度の目的や運用方法を共有する。目標設定がうまくできない職員も多く、最近では被評価者研修を実施する金庫も増えている。
(5)定期的な制度改善
制度導入後は定期的に運用状況を評価し、職員のフィードバックを基に改善を続ける。取り組みの具体例としては、評価制度運用アンケートの実施や等級定義や評価項目の見直し、賃金テーブルの改定などがある。
まとめ
信用金庫における人事制度の見直しは、地域社会や顧客ニーズに応えるための重要な経営課題となっている。導入後のPDCAを回しながら制度の定着を図り、職員のエンゲージメントを高め、組織の競争力を向上させることで、金庫のビジョンや成長戦略の実現が強化できる。
関連情報
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
ゼネラルパートナー岡原 安博
外資系ラグジュアリーブランドで店舗マネジメントに従事後、人事コンサルティング会社にて組織・人事領域のコンサルティング、教育、組織開発等の経験を経て、当社へ入社。人事領域全般のコンサルティングを中心に、上場・中堅企業の人事制度・教育体系の構築において数多くの実績を持つタナベトップコンサルタントの一人。
- 主な実績
-
- 中期経営計画策定コンサルティング(組織・人事戦略策定)
- グループ経営企業の人事制度統合コンサルティング
- 金融・建設・製薬・物流の人事制度構築コンサルティング
- その他多種多様な業界での人事制度・教育制度構築実績あり
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト