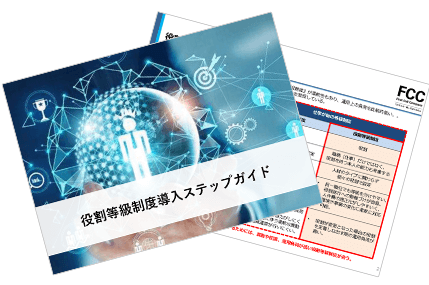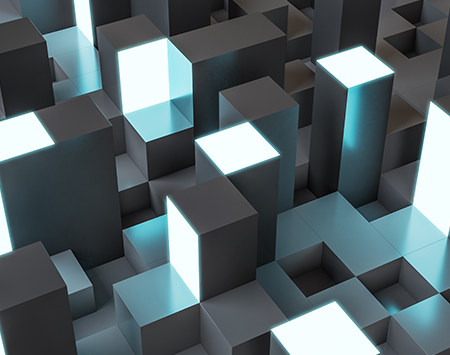人事コラム
役割等級制度と評価基準の最適化で企業の競争力を強化
職能×職務のハイブリッド、役割等級制度のポイントと設計ステップを押さえる!

職能資格制度、職務等級制度とは
昨今の日本企業の傾向として、「年功主義」から「職務・役割主義」へと根本的な考え方が変化してきているものの、年齢や勤続年数とともに等級や役職が上がり、一度上がると下がることがない、"年功的な"「職能資格制度」を運用している企業が多く存在する。
職能資格制度とは、職務を遂行する能力(=資格)に基づいて等級・評価・賃金を決定する制度である。
仕事を経験するほど職務遂行能力は身に付くということや、終身雇用で長期的に育成することを前提とした制度である。
一方で職務遂行能力の評価は難しく、自ずと年齢・勤続年数が重ねているほど能力がある"だろう"という考えのもと年功的な運用になっている。
必ずしも長期間働くと能力が身に着くとは限らず、年功的に処遇が決定するためポスト不足や若手社員のモチベーション低下、労務費の増加といった問題点もある。
そのような問題点を解消するために昨今良く耳にする「職務等級制度(≒ジョブ型)」を導入する企業が増えている。
職務等級制度とは、企業が人材を採用する際に社員に対して職務内容を明確に定義して雇用契約を結び、労働時間ではなく職務(ジョブ)の価値(サイズ)を評価する制度である。
職能資格制度がその人の能力(=「人」基準)で処遇を決めるのに対して、職務等級制度はその人が従事する仕事(=「仕事」基準)で処遇を決めるため、職務レベルと処遇が一致しやすく、採用時にも職務が明確であることから条件を提示しやすいなどの特徴がある。
一方で職務等級制度においては個々人の職務を明文化した職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)があるが、そのメンテナンスが非常に大変であることや、職務記述書に記載されていない職務は一切行わない、職務と完全にマッチした人材を採用できないといった問題点があり、人材が豊富でない日本の中小・中堅企業では馴染みづらいのが実態である。

役割等級制度の定義と導入メリット
業務遂行能力に基づいて等級が決定する職能資格制度、職能資格制度の曖昧さをなくし従事する職務に応じて等級が決定する職務等級制度、そして職務等級制度の問題点を解決すべく誕生したのが「役割等級制度」である。
役割等級制度は、各等級において期待する役割を定義し、その発揮度合いに応じて処遇が決定する制度である。
役割を遂行することで能力が身に付くという考え方のため、年齢や勤続年数等に関わらず、求められる役割を果たすことで評価され、昇格することが可能であり、若手社員のモチベーションアップにも影響するという特徴がある。
職務記述書に比べ役割要件(各等級において期待する役割を明文化したもの)はメンテナンスが楽である点や、職務を明確に定めないため、職務が限定されることはなく柔軟な対応が可能である点など職務等級制度での問題点を解決することができ、なおかつ保有能力ではなく明確な役割要件とその発揮度合いに基づいて処遇を決定するため社員からの納得が得られやすいというメリットがある。
ただし、各社において期待される役割は異なるため、企業理念や中長期ビジョン、単年度方針などの経営バックボーンシステムを元に自社にはどのような人材が必要か、社員にどういった役割を発揮してほしいかを整理したうえで制度設計する必要がある。

役割等級制度と評価基準の連携
先述したように、役割等級制度においては各等級に期待される役割に対する発揮度合いを評価することとなる。
そのため、役割要件から期待するコンピテンシー(行動特性)や成果、プロセス/能力といった評価要素を抽出し、評価項目として設定する。
職務等級制度においては職務に対する成果のみを評価するケースが多いが、役割等級制度においては、「①保有する能力を発揮し、②成果に繋がる行動をとった(プロセス・コンピテンシー)結果、③成果として現れる」という各段階を評価対象とする。
役割等級制度の評価制度設計のポイントは3点ある。
1.基準が明確であるか
役割等級制度はあえて明確にせず曖昧にさせる部分をつくることで職務等級制度の問題点を解決しているため、反対に評価制度が曖昧になりやすいという問題点がある。
そのため、評価制度設計においては特に評価項目・評価の着眼点・段階評価の基準を明確にし、被評価者・評価者双方が理解しやすく評価基準にズレが生じづらいよう制度設計する必要がある。
加えて、その評価を評価者から被評価者にフィードバックすることも重要である。
明確な基準があったとしても評価者が根拠を持って評価できていなければ被評価者からの納得は得られづらい。
評価期間においては観察・対話・記録といった人材育成マネジメントを行い、適切な評価を行った結果を個別にフィードバックし翌期に繋げることが評価者には求められている。制度設計と合わせて運用を見据えた評価者の育成も行っていただきたい。
2.成果評価は、中期経営計画や方針から落とし込まれているか
成果評価の項目を決めるにあたっては大きく指定型とMBO型がある。
指定型は会社あるいは上司が、個人の成果目標を指定して決めるものであり目標設定を組織単位で行うため、目標設定のレベルが揃いやすい。
一方で本人が目標としたい内容と会社・上司が求める内容が異なる場合が多く、その場合は上司から本人へ目標に対する意欲づけが必要となる。
MBO型は個人がその期に取り組みたい内容を元に目標を設定し上司と認識を合わせたうえで目標が決定するものであり、被評価者本人が主導して目標設定するため目標達成に対するモチベーションを高めやすい。
一方で被評価者の目標設定が適切かを精査する上司(評価者)のレベルによって難易度にバラつきが出やすいため注意が必要である。
いずれの方法であったとしても成果評価の設計においては、中期経営計画や方針から落とし込まれているか確認する必要がある。
タナベコンサルティングではよく「経営のバックボーンシステム」とお伝えしているが、中期経営計画を元に全社年度方針が策定されており、全社年度方針を元に部門方針が策定され、部門方針を元に個人目標が策定されているというように、組織の中長期的な目標が個人まで落とし込まれている企業は持続的に成長している。
個人によって期待される役割が異なるからこそ、成果評価の設計においては中期経営計画や方針と落とし込まれているかを確認していただきたい。
3.相対評価か絶対評価か
相対評価とは、被評価者の組織(チーム・部・同等級・同役職・全社など)のなかで客観的な基準ではなく個人同士を比較し、相対的に評価する手法である。また、絶対評価とは客観的な基準を元に、その基準に対して個人を評価する手法である。一般的に相対評価は所属する組織内に本人よりも優秀な人材がいれば、どれだけ役割を発揮しても評価されず、反対に本人よりも優れない人材がいれば役割を発揮していなくとも評価されるというような評価に対する納得性を得られにくく、本人の成長にも繋げづらい。
そのため役割等級制度においては各個人が該当等級に期待される役割をどれほど発揮できたかを評価するため、一次評価においては絶対評価とすることが望ましい。なお二次評価以降に関しては一次評価間の甘辛を調整するために一部相対評価を取り入れている企業もある。

企業の競争力を高めるための具体的なステップ
ここまで役割等級制度の特徴や制度設計のポイントを記述してきたが、最後に企業の競争力を高めるためのステップに
ついて紹介したい。
STEP1:現状を知る
タナベコンサルティングでは「現状認識」とも呼ぶが、まずは自社の現状を正しく押さえる必要がある。
具体的にどのような点に課題があり、なぜそのような課題が起きているのか明確にすることで制度設計の方向性が見えてくる。現状認識においては定量的な分析だけでなく、実際に働かれている社員の方からヒアリングする・アンケートをとるなど社員の声を聴くことで見えてくる課題もある。
STEP2:人事ポリシーを策定する
現状を知り、改善の方向性が明確になれば制度設計に入る。ただし、制度設計においてはいきなり等級制度設計を行うのではなく、まずは自社の人材に対する想いや新人事制度の軸となる考え方を明文化していただきたい。
人事ポリシーの型は様々であるが、人事ポリシーを明確にすることで以下のような良い影響が考えられる。
①社員が会社の想い・考えを知り、人事ポリシーに沿った人材になろうと意識することや会社に対する愛着が増加する
②対外的にも出すことでステークホルダーから自社の想い・考えを理解してもらえる
③採用活動において自社の想いに共感した人材が集まる など
STEP3:等級制度・評価制度・賃金制度を設計する
制度設計におけるポイントは先述したが、いずれのフェーズにおいてもSTEP2で策定した人事ポリシーを元に設計することが重要である。どのような人材を育てたいのか、どのような人材を評価したいのか、どのような人材に利益を還元したいのか...など人事ポリシーを軸に各フェーズを設計することで会社の想い・考えが人事制度に組み込まれていく。
加えて制度設計において忘れてはならないのは、"自社らしさ"である。他社の事例等を見ているとスタイリッシュさや斬新さ、シンプルさなど自社と違う制度に目を惹かれがちであるが「自社に浸透するか」「自社らしいか」「自社の想い・考えと合っているか」を確認していただきたい。
どれだけ素晴らしい制度であっても、自社らしさがなければ自社には馴染みづらく、結果制度変更が失敗となることも考えられる。
STEP4:新制度の運用を強化する
繰り返しにはなるが、制度は設計2割、運用8割であり運用が何より重要である。そのため、制度の運用体制を整える必要があり、特に推奨したいのは以下の3点である。
①評価者研修
評価=選別査定という認識を持った評価者はまだまだ多いため、評価は人材育成のためにするものであり、評価者には評価時だけでなく評価期間中・評価実施後においても役割があることを認識していただく必要がある。
加えて、制度の理解を促進し、評価者同士の目線を合わせ、甘辛を可能な限りなくすことで適切に制度運用を行うためにも評価者研修は必須で行っていただきたい。
新制度の運用においては評価者の協力が必須である。
②被評価者研修
加えて被評価者に対しても、評価の目的を伝え、評価を通じて成長をしてほしいという想いを理解していただく必要がある。被評価者が人事制度(特に評価制度)を理解しておらず、評価者からのフィードバックを受け入れなければその企業の人材はいつまでも成長しない。
評価の目的や評価フィードバックの活かし方を学んでいただき、自身の成長のための仕組みであることを理解していただくことが重要である。
③制度の定期的な見直し
本来人事制度は2~3年に1度制度のメンテナンスを行うことが望ましいものの、数十年放置しているという企業も少なくない。しかし、外部環境やそこで働く社員の価値観も変化の激しいこの時代においては制度も合わせて変化させる必要がある。
制度のメンテナンスにおいては総務・人事部門のみでなく、社員(被評価者・評価者)から制度に対するフィードバックをもらい、そのような意見を元に改善策を検討することでより自社に合った制度へと成長していく。
さいごに
企業は人なり、というように企業の競争力強化においてはそこで働く人の育成が必須となる。
もちろん人材育成においては教育制度も重要であるものの、自社においてどのような人材を育てたいか明確にし、そのような人材を育てる仕組みである人事制度が整えられているからこそ教育制度は効果が発揮されるものである。
企業によって最適な制度は異なり、数あるパターンの中から選択し設計する、その判断が非常に重要である。
本コラムにおいては役割等級制度をメインに記載したが、役割等級制度がどの企業においても最適というわけではない。
自社の状況を踏まえた制度の設計・運用を検討していただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画