人事コラム
賞与制度設計のポイントとは?
賞与制度の基本概要や支給ルールのステップなどを解説
賞与の特性を踏まえた分配・支給方法について紹介

賞与支給ルールの種類と考え方
賞与を支給している企業は多くあるが、その支給ルールは各社各様である。
賞与制度を検討するにあたり
①原資決定ルール(賞与の原資をどのように決定するか)
②個人分配ルール(原資をどのように社員へ分配するか)
について検討することが必要となる。
賞与制度の設計においては、まずはどのようなコンセプトで賞与を運用していきたいのかを明確にすることから始めていただきたい。
例えば、成果に報いるため、会社の思想と合致している人に報いるため、利益を分け合い喜びを分かち合うため、など正解はないが、コンセプトを明確にすることにより会社の思いと連動した制度設計へと繋がる。
本コラムでは、賞与支給ルールの基本となる考え方について解説していく。
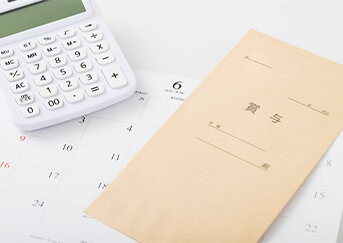
賞与の基本概要と種類について
賞与とは
賞与とは、ボーナス・期末手当・特別手当・一時金とも呼ばれており、毎月の給与とは別に支給される賃金のこと。
賞与の支給回数や時期は企業によって自由に決められる。
賞与が支払われる時期は夏と冬の年2回が一般的だが、そもそも賞与を制度として導入していない企業も存在する。
従業員からすれば、賞与は生活に大きく影響するものであるため、企業側は賞与の種類やメリット・デメリット、計算方法を正確に把握しておくことが重要になる。
賞与の種類
企業が従業員に支給する賞与は、基本給連動型賞与・決算賞与・業績連動型賞与の3種類に分けられる。どの種類の賞与を支給するかは企業が決定するが、従業員はどの種類の賞与が採用されているか、就業規則や労働契約等で確認しておくことが必要になってくる。
それぞれの種類について簡単に説明する。
・基本給連動型賞与
基本給連動型賞与は、基本給をベースに支給額を計算する賞与制度。計算方法はとてもシンプルで、賞与算定基準日の基本給に支給月数を掛けて計算することによって算出される。
・決算賞与
決算賞与とは、決算の前後に会社の業績に基づいて支払われる賞与のこと。「特別賞与」や「臨時賞与」、「年度末手当」と呼ばれることもある。その年の業績が良かった場合、通常の給与とは別に従業員に支給される。
決算賞与とは?決算賞与のメリット・デメリット、決めるポイントを解説
・業績連動型賞与
企業業績や個人の業績に応じて支給額を決定するのが、業績連動型賞与。
予測不可能な情勢の中で、企業の財政安定と優秀な人材の留保を目的に、業績連動型賞与を導入する企業が増加している。業績連動型賞与制度を中心とした制度の構築ステップについては以下に別途まとめている。
業績連動型賞与制度を中心とした制度の構築ステップとは?
賞与のメリット・デメリット
賞与は企業と従業員双方に大きな影響を与えるため、そのメリットとデメリットを深く理解しておくことが重要である。単なる給与の追加支給として捉えるのではなく、経営戦略や働き方の一環として捉えるべきである。
・企業側のメリット・デメリット
企業側にとって、賞与は業績と連動した柔軟な人件費調整弁となるメリットがある。業績が好調な年には、従業員に利益を還元することで、企業への貢献意欲やエンゲージメントを高めることができる。これにより、優秀な人材の定着や採用活動における魅力向上にもつながる。一方で、業績に関わらず一定額を支給する慣行が定着すると、固定費化するリスクを抱えることになる。市場環境の悪化などで業績が急落した場合、賞与の減額や不支給は従業員の大きな不満となり、離職に繋がる可能性も潜んでいるのである。
・従業員側のメリット・デメリット
従業員側にとって、賞与は年に数回、まとまった収入を得られるという大きなメリットがある。これにより、生活の安定や住宅、車の購入、長期的な貯蓄など、計画的な資金利用が可能となる。また、業績連動型や個人の評価が反映される制度では、自身の努力や成果が報われるため、働く上での大きなモチベーションとなる。しかしその反面、企業の業績や個人の評価によって支給額が変動するため、安定した収入源として見込みづらいというデメリットも存在する。特に、住宅ローンなどの固定支出がある場合、賞与が不安定であることは大きな不安材料となるのである。

生活給と成果給
賞与支給ルールを考えるにあたり、賃金制度において前提となる考え方について紹介する。
基本的に賞与は、固定要素が多く生活保障の一部として支給する「生活給」、変動要素が多く、成果(業績・利益など)に報いるために支給する「成果給」がある。
この2要素を押さえた上で、支給ルールの考え方について解説していく。
賞与支給ルールの決定ステップ
賞与支給ルールを決定するにあたっては、前述の2つのルールに分類して検討していきたい。
以下にポイントを記載する。
【STEP1 原資決定ルールの検討】
原資を決めるための考え方は大きく3パターン挙げられる。
| NO. | 考え方 | 算出方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月例給をもとに算出 | 月例給×〇ヶ月×社員数 | 月例給の積み上げがベースなるため、支給月数が変わらずとも評価による積み上げにより原資が毎年増加する可能性がある |
| 2 | 利益をもとに算出 | 利益の〇% or 目標利益の上回り分 | 利益がベースとなることから成果給要素が強く、経営のハンドリングがしやすい |
| 3 | 固定額にて算出 | 前年の支給実績をベースに、一定のルールに基づき定める | 前年の支給実績が基準となるため生活給要素が強く、固定化されやすいため、実績以上の支給になる可能性がある |
前年踏襲型で決めているのであれば固定(生活給)の要素が強く、利益や経営数値に応じて決めているのであれば変動(成果給)の要素が強いと言える。
最適な方法は各社で異なるため、職種特性、財務状況、企業文化などを踏まえ検討していただきたい。
【STEP2 個人分配ルールの検討】
次に、個人分配ルールである。
こちらは大きく4パターンが挙げられる。
| NO. | 考え方 | 算出方法 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月例給をもとに算出 | 月例給の〇ヶ月分 (全社員に一律の月数を掛ける) |
過去の積み重ね(定期昇給)が反映されるため、年功の要素が強くなる |
| 2 | 成果に応じて支給 :係数制 |
評価結果に応じて係数を設定し、 月例給に係数を掛けて算出する |
過去の積み重ね(定期昇給)による年功的な要素と成果(評価)により決定する |
| 3 | 成果に応じて支給 :ポイント制 |
評価結果や個人のステータス(等級・役職など)に応じてポイントを付与し、原資を総ポイントで割る | 賞与算定基礎額として、月例給を用いず原資の分配により決定するため成果給要素が非常に強い |
| 4 | 等しく分配 | 原資を社員数で割り、配分する。 | 個別の努力や成果が反映される余地はほとんどなく、生活給要素が非常に強い |
各社の思想に合わせ、何に報いていきたいのかを明確にし決定していただきたい。
また、夏季・冬季賞与とは別に決算賞与を支給する企業もあるが、賞与の種類に応じて、支給ルールを分けることも可能である。
※一般的に決算賞与は決算時の業績(売上・利益など)に応じて賞与支給額が増減するため成果給として支給するケースが多い

賞与制度設計の際のポイント
賞与制度の設計は、企業の成長と従業員のモチベーションを高めるための重要な要素になる。効果的な賞与制度を構築するためには、いくつかのポイントを押さえる必要がある。
下記にて、企業が賞与制度を設計する際に意識するべきポイントを紹介する。
・企業のビジョンと目標に沿った制度設計
賞与制度は、単なる給与の追加支給ではない。企業の経営理念やビジョン、経営戦略・目標と連動させることが重要である。たとえば、「顧客満足度向上」を掲げる企業であれば、その目標達成に貢献した部署や個人に報いる制度を設計するべきである。これにより、従業員は会社の方向性を理解し、自身の行動がどのように会社の成長に繋がるのかを実感することができ、結果として、組織全体の一体感が強まり、業績向上への貢献意欲が高まるのである。
・公平性と透明性の確保
従業員が制度を信頼し、納得して働くためには、公平性と透明性が不可欠である。この両者が一体となることで、賞与制度は従業員のモチベーションを最大限に引き出すことができる。
公平性とは、同じような成果を出している従業員間で不当な支給額の差が生まれないようにすることである。職種や等級、役割に応じて、評価の基準や配分ルールを明確に設定すべきである。
一方、透明性とは、その評価基準や計算方法を従業員に分かりやすく説明し、開示することである。たとえば、個人の評価結果と支給額の関係を明確に示したり、評価フィードバックの面談を実施したりすることで、従業員は「なぜこの金額になったのか」を理解しやすくなる。
特に、業績連動型の賞与制度を導入する場合は、この二つの要素がより重要となる。会社全体の業績目標と個人のパフォーマンスがどのように反映されるのかを、事前に丁寧に説明することで、従業員の納得感を高め、公正な評価への信頼を築くことが可能となるのである。
・定期的な見直しとフィードバック
賞与制度は一度設計したら終わりではない。市場環境の変化や企業の成長ステージに応じて、定期的に見直し、フィードバックの仕組みを設けることが不可欠である。
自社の制度が外部の賃金水準や競合他社の制度に対して競争力を保てているかを確認するとともに、従業員満足度調査やアンケートを通じて制度への意見や不満を吸い上げるべきである。これにより、制度の効果を客観的に評価し、継続的な改善が可能となる。
また、支給額を伝えるだけでなく、「何が評価されたのか」や「次期に向けてどのような行動が期待されるのか」を具体的にフィードバックすることで、従業員の成長を促し、次期以降のパフォーマンス向上に繋がる。このように、制度を柔軟に見直し、継続的に改善していくことが、企業の持続的な成長と、従業員のエンゲージメントを最大化する鍵となるのである。
賞与制度の設計はこれらのポイントを押さえたうえで構築していくと良い。

賞与制度を見直す際のポイント
ここでは、すでに賞与制度を運用している企業が、より効果的な制度へと改善するためのポイントを解説する。
・見直しの目的を明確にする
まず、「なぜ賞与制度を見直すのか」という根本的な目的を明確にすることが重要である。たとえば、従業員のモチベーション向上のために、社員の頑張りに報いる制度へと変えたい場合、あるいは企業の利益変動と人件費をより密接に連動させるため、業績との連動強化を図りたい場合がある。また、外部の賃金水準と乖離し、採用や離職に悪影響が出ているのであれば、優秀な人材の獲得・定着が目的となる。これらの目的を共有し、見直しに着手することで、ブレのない制度設計が可能となるのである。
・現状の制度を徹底的に分析する
次に、既存の制度が抱える課題を具体的に把握することが、見直し成功の鍵となる。まずは、従業員へのヒアリングを行い、制度に対する意見や不満を直接聞くことで、現場のリアルな声を反映すべきである。さらに、支給実績のデータ分析を行い、過去数年間の支給額データを検証することで、年功序列や特定の部署への偏りがないかなどを客観的に把握できる。そして、新しい制度を導入した場合の人件費の変化や、特定の社員に大きな不利益が生じないかを事前にシミュレーションしておくことが不可欠である。
・従業員への丁寧な説明と合意形成
制度の変更は、従業員にとって大きな関心事であり、不信感を生むリスクを伴う。そのため、制度の変更に際しては、目的とメリットの共有を丁寧に説明し、なぜ制度を変えるのか、そしてそれが従業員自身にどのようなメリットをもたらすのかを伝えるべきである。また、質疑応答の機会として、説明会や個別面談の場を設け、従業員の疑問や不安を解消することが重要である。これにより、スムーズな移行と新制度への納得感を促すことができるのである。
まとめ
最近タナベコンサルティングにてご支援しているクライアント先では、生活保障としての意味合いが大きい「生活給」を中心にした賞与制度から業績と連動した「成果給」の要素を強めた賞与制度への見直しを検討する企業が増えてきている。
この背景として以下の3つの理由が挙げられる。
①ひと昔前と比べ業績を読むことが難しく安定的に賞与を支給し続けることが厳しい。
②働く価値観の変化により、年功的に積み上げる固定化された賞与ではモチベーションが上がらない。
③賞与をある程度経営でハンドリングしたい。
とは言え、これまで固定的に支給してきた企業が変動要素を多く持たせた賞与制度に切り替えるということは、社員の理解を得るのに時間を要し、制度導入の難易度も高い。
だからこそなぜ賞与制度を見直すのかという目的と何に対して報いるのかを明らかにした上で、制度の見直しを進めていただきたい。
どちらかが良い悪いというわけではなく、企業文化や業種特性に合わせて経営のハンドリングと社員のモチベーションのバランスを踏まえた上で賞与制度の見直しを進めていただきたい。
関連動画
関連情報



