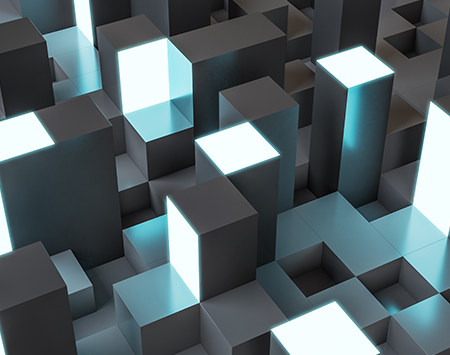建設業の経営者・人事担当者必見

建設業における人事制度の現状
近年、建設業における人事制度は、伝統的な年功序列型から成果主義型へと移行しつつある。
しかし、依然として職務内容や能力、貢献度を適切に評価する仕組みが整備されていない企業も多く存在する。
また、建設業特有の多能工化、技術伝承、業務効率化(DX含む)等、考慮すべき要素も多く、人事制度設計は複雑化している。
その上で、今後新たに人事制度を構築される、もしくは既存の制度をリニューアルされる建設業の経営者・人事担当者の方は、後述のポイントを参考にして欲しい。
建設業は、事業規模や業種(建設・土木)、公共工事と民間工事の割合など、様々な側面において多様性を持つ業界である。
そのため、人事制度の設計・運用においても、画一的なアプローチではなく、各社の特性に合わせた柔軟な対応が求められる。
本稿では、建設業における人事制度の一般的な情報を提供するが、各社においては、自社の状況を十分に分析し、最適な制度を構築・運用していただきたい。

建設業における職種別に求められる評価要素
(1)施工管理
施工管理は、プロジェクト全体を統括し、成功に導くための重要な役割を担う。
評価要素としては、下記があげられる。
①工程管理能力
これは、計画に基づいた工程管理を遂行する能力、遅延発生時のリカバリー力、そして複数プロジェクトを同時管理する能力などが含まれる。
②安全管理能力
建設現場における最優先事項であり、労働安全衛生法規の遵守、現場の安全管理体制構築・維持、事故発生時の適切な対応なども評価の対象にする必要がある。
③原価管理能力
原価の高騰という課題がある中では、原価管理能力も重要な要素である。
予算内での工事完了、コスト削減提案、実行予算と実績の比較分析などが評価対象である。
④コミュニケーション能力
発注者や協力業者との円滑なコミュニケーション、現場スタッフへの指示・指導力が評価の対象になるだろう。
(2)施工スタッフ
施工スタッフは、実際に手を動かして建設物を造り上げる役割を担う。
評価要素としては、下記が挙げられる。
①技術力
これは、建設に関する知識(資格取得含む)・技能の習得度、作業の正確性やスピード、そして新技術・工法への対応力などが含まれる。
②安全意識
安全作業手順の遵守、危険予知・回避能力、安全具の適切な使用などが評価の対象になる。
③協調性
チームで作業を行う上で重要な能力である。
チームワークを重視した作業、周囲への配慮、現場の規律遵守などが評価の対象になる。
(3)営業
営業は、発注先との関係構築や新規案件の獲得、協力業者との関係性構築など、企業の収益に貢献する役割を担う。
評価要素としては、下記が挙げられる。
①顧客開拓力
これは、新規顧客開拓、既存顧客との関係強化、潜在顧客へのアプローチなどが含まれる。
②提案力
顧客ニーズに合った提案、技術的な説明能力、交渉力などが評価の対象となる。
③受注獲得力
見積もり作成、契約締結、競合他社との差別化などが求められる。
③原価管理能力
施工管理と同じく、業には必要な能力である。
資材価格高騰を踏まえた原価管理、実行予算作成、利益確保などが評価される。
④協力業者との関係構築・開拓
人員不足の中では、自社だけではなく、協力業者との連携が必要不可欠である。
その為、協力業者との連携や、開拓についても評価の対象となる。
⑤人員配置調整力
案件規模に応じた適切な人員配置、その為に現場との密なコミュニケーション等が評価の対象となる。
(4)事務
事務は、建設業では、社内の業務を円滑に進めるためのサポート役に留まらず、施工管理の資料作成のフォロー、DXを踏まえた業務効率化を担うことが求められている。
評価要素としては、下記が挙げられる。
①業務効率化
これは、事務処理能力、業務改善提案、システム活用などが含まれる。
働き方改革を推進する上で、付加価値の低い仕事をを減らし、付加価値の高い仕事を増やす心がけが重要である。
②正確性
書類作成、データ入力、計算処理などが評価の対象となる。
③コミュニケーション能力
現場を含む社内外との円滑なコミュニケーション、報告・連絡・相談、チームワークなどが求められる。

人事制度運用におけるよくあるミス
建設業における人事制度は、企業の持続的な成長を支える上で欠かせない要素だが、その効果を最大限に引き出すためには、適切な運用が必要である。
しかし、制度設計が緻密であっても、運用段階で様々な課題に直面し、その意図が十分に反映されないケースも少なくない。
特に、建設業においては、現場と人事部門との連携不足が深刻な問題として挙げられる。
現場の状況や従業員のニーズを把握せずに制度が運用されると、制度が形骸化し、従業員の不満やモチベーション低下に繋がる可能性がある。
人事制度運用におけるミスは多岐にわたるが、ここでは特によく見られるケースとその要因について解説する。
(1)制度の周知不足
制度内容が従業員に十分に理解されていない状態は、制度への不信感を招き、利用率の低下に繋がる。
これは、制度説明会を開催せずに資料のみで配布していることや、評価者自身が制度の理解を不足していること等が要因として考えられる。
(2)評価基準の不明確さ
評価基準が曖昧で、従業員が納得感を得られない場合、評価に対する不満や不公平感を生み出す。
これは、評価項目の具体性不足や評価者の価値判断基準がすり合っておらず、主観に偏った評価が行われていること等が要因として考えられる。
(3)フィードバックの欠如
評価結果に対するフィードバックが行われず、改善に繋がらない場合、従業員の成長意欲を削ぎ、能力向上を阻害する。
これは、評価者がフィードバックの方法を理解していないこと等が要因として考えられる。
(4)現場の実態との乖離
制度が現場の実態と合致しておらず、運用が困難な場合、制度自体が無意味なものになってしまう。
これは、制度設計段階で経営陣・人事部のみで制度設計をしてしまうことで、現場意見の反映が不足していること等が要因として考えられる。

人事制度運用を成功させるためのポイント
人事制度運用を成功させるためには、以下のポイントを押さえることが重要である。
(1)制度の目的を明確にする
制度の目的を明確にし、制度設計に従業員を巻き込むことで、制度への理解と協力を得やすくなる。
(2)評価基準を具体的に定める
評価基準を具体的に定め、誰でも理解できるようにすることで、評価の公平性と透明性を確保できる。
(3)フィードバックを徹底する
評価者研修を実施し、評価結果に対するフィードバックの方法を伝えることで制度の有効性を高めることができる。
(4)現場との連携を強化する
制度構築のプロジェクトに現場メンバーを巻き込むだけでなく、社内アンケート等で現場の声をしっかりと聴くことが大切である。現場とのコミュニケーションを密にし、制度の実効性を高めることで、現場のニーズに合った制度運用が可能になる。
さいごに
本稿では、建設業における人事制度設計の重要性とそのポイントについてお伝えした。
人事制度は、企業の成長を支える重要な基盤の一つである。
ぜひ、本稿を参考に、自社の人事制度を見直し、より効果的な制度を構築できることを願っている。 今回の内容が、厳しい環境変化の中で戦い続ける経営者の皆様、社員の皆様にとって、少しでも参考になれば幸いである。
関連情報
-
課題解決人事制度完全ガイド~成功事例から最新トレンドまで一挙ご紹介
-
課題解決最近のトレンドのハイブリッド型人事制度とは
-
課題解決業績と連動した成長を支える人事制度構築のポイント
-
課題解決北陸の建設業界における人事制度のトレンドとは?
-
課題解決建設業における若手・人材育成の重要性と育成方法
-
人事コラム人事制度の抜本的改革
-
人事コラム『人事制度構築の失敗事例』人事制度再構築を行うタイミングを見極める
-
人事コラム効果的な人事制度見直しのためのステップ
-
人事コラム人事制度改定の進め方と最適な運用手法
-
人事コラム人事制度の見直しにおける基本的な考え方について
-
人事コラム避けるべき人事制度設計と成功のポイント
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング
チーフコンサルタント大西 将之
人材業界で法人営業、マネジメント業務に従事後、当社に入社。【人】に関わるテーマを中心に、製造業、建設業から卸売業まで幅広い企業の経営支援に取り組んでいる。”支援を通して、クライアント、社員、そして社員の家族の幸せに貢献する”というポリシーのもと、クライアントの本質的な課題と向き合う姿勢でのコンサルティング展開で高い信頼を得ている。
- 主な実績
-
- 中堅製造業:採用戦略構築コンサルティング
- 中堅卸売業:新入社員受入体制構築・社外エルダー担当
- 中堅卸売業:階層別教育
- 中堅製薬業:若手階層別教育
- 中小建設業:経営理念・人事ビジョン策定コンサルティング
- 中小不動産業:人事ビジョン・人事制度構築コンサルティング
- 中小製造業:採用戦略構築・インターンシップ推進支援
- 中小製造業:人事制度構築コンサルティング
- 中小建設業:採用戦略構築コンサルティング
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト