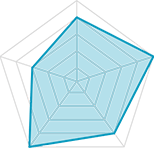人事コラム
人事制度改定の進め方と最適な運用手法
社員の活躍を促進する人事制度を一から見直すことで、社員と会社の双方が成長し合える基盤を築く

人事制度改正のトレンド
人事・人材分野では人的資本経営、エンゲージメント、ダイバーシティなど様々なホットワードに注目が集まっている。
特に着目されているのは「人事制度の改正」だ。
4~5年前と比較すると、人事制度を改正したいまたは着手する企業の数が急激に増えている。
なぜ人事制度を改正する企業が増えているのか。
言わずもがなであるが、経営環境が劇的に変化し、時代に即した人材の活躍を模索する必要性に迫られているからであろう。
過去当たり前であったことがあっという間に非常識になる変化の時代が現代である。
変化に適応しながら企業の成長へ貢献する人材を採用・育成・活躍させていくことが企業にとっての成長戦略であり、その仕組み・基盤として「人事制度」の重要性を見つめ直す企業が増えている。

人事制度改正の一丁目一番地
まず大前提として押さえるべきなのは、企業の究極の目標は「理念の実現」にあるという点だ。
ゆえに人事制度を改正しようとする全ての企業が一番最初に次の三点を棚卸しする必要がある。
【価値観の整理】
①我が社の理念はなにか
②理念を実現するための中長期のビジョンはなにか
③理念・ビジョンを叶えるために必要な人材要件(=人材ビジョン)はなにか
いきなり人事制度の中身を考え始めるのではなく、人事制度を通して、何を実現したいのかという価値観や判断基準を明確に持つことが重要である。

人事制度改正の基本手順
続いて人事制度改正の基本手順を解説する。
人事制度は大きく分けて3つに大別され、等級制度→評価制度→賃金制度の順で改正を進めるのがセオリーである。
まずは等級制度から検討するのが望ましい。
等級制度は社員に求める水準をグレードという形で可視化したものであり、我が社におけるキャリアステップそのものである。
過去は入社後に管理職を目指す単一的なキャリアパスが主流であったが、昨今では自らの専門性で貢献する専門職を設置した複線的なキャリアパスがトレンドになっている。
加えて、一つの企業でも営業や開発、製造など多岐に渡る機能を保有するケースが多いため、職種で制度を変えるというパターンも増えつつある。
我が社の理念やビジネスモデルを考えた際にどのようなキャリアを歩んでほしいのかを踏まえつつ、階層数・複線化・職種特性の観点で最適なグレードとそれに基づく詳細定義の設計を行っていく。
続いて評価制度である。
評価制度は、評価項目の設定と評価運用ルールの二点で検討を進めるのが良い。
評価項目は上段で整理された人材ビジョンや等級定義と紐づけることがポイントであり、等級制度と評価制度を繋げる最重要な要である。
他社で使われている項目の活用ではなく、我が社の求める人材を図る最適な項目が何かを検討されたい。
また評価運用ルールは、評価フロー・スケジュール・昇降要件の整理など運用に関わる仕組みを一つひとつ設計していく。
評価制度に対する社員の納得度と運用に関わるオペレーションコストの二軸のバランスを踏まえながら、詳細設計を行っていく。
最後に賃金制度である。
賃金制度のポイントは、総人件費と世間相場とのバランスである。
昨今では賃上げの風潮が強いが、世間相場や競合他社と比較して競争力のある基本給・諸手当・賞与・退職金であるかを分析する必要がある。
ただしその結果、賃金水準を上げようとしても、人件費を無尽蔵には投下できないという現実がある。
労働分配率や一人あたり生産性を踏まえながら総人件費として適切かの視点を更に加えて、最終的な金額水準を設計していく。

社員のモチベーションを高める運用手法
ここまで人事制度改正に向けたオーソドックスな進め方を解説してきた。
ただし、どんなに素晴らしい制度を設計したとしても、運用がなされなければ期待された効果は得られないだろう。
つまり「制度:2割、運用:8割」という考え方に基づいて、人事制度設計後は運用に心血を注がなければならない。
人事制度が社員のモチベーションを高める仕組みとして機能している企業は漏れなく運用が上手くいっている。
ではどのようなポイントが運用面で重要となるのか。
それは人事制度をいかに「身近な仕組み」として落とし込めるかである。
人事制度に接する機会は評価を行う半期または期末のタイミングであり、年に1~2回であることが通常だ。
ただし年に数回しか活用されない制度・仕組みであると当然社員への浸透度は高まらず、またその制度で処遇が決まるとなると納得感は得にくい。
ゆえに継続的な評価研修の実施や人事制度を期中のコミュニケーションツールとして活用するなど接点を増やすことが大切だ。
多くの接点を持つことで目指す方向性や本質的な意味する背景を理解し、日常の個人の行動へと落とし込むところまで運用されたい。
さいごに
人事制度は社員の採用・活躍・定着の全てに寄与する仕組みである。
なぜならば社員目線で捉えると自らの成長軌跡を可視化されるのが人事制度だからである。
社員の成長を支援する人事制度を今こそ整備し、最終的には我が社の理念実現に向けた仕組みの再構築が求められる。
本事例に関連するサービス

人事制度運用・定着・浸透コンサルティング
制度の運用プロセスを最適化し、効果的なコミュニケーション戦略を通じて、従業員の理解と協力を促進します。また、制度の定着を図ることで、 組織の目標達成に貢献し、持続可能な成長を支援します。
人事制度運用・定着・浸透コンサルティングの詳細はこちら