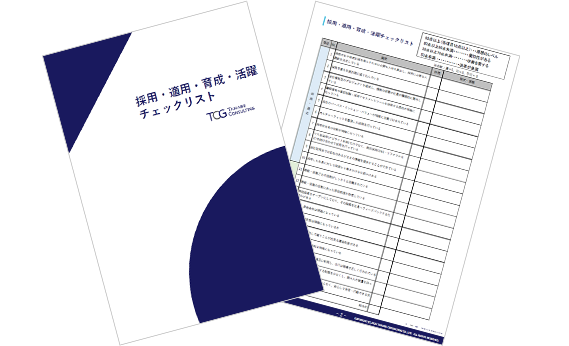人事コラム
人材獲得競争とは?
人材獲得のための効果的な戦略と方法を解説
人材獲得は重要度の高い経営テーマである

人材獲得競争とは?
近年は、労働者側の優位な状態(売り手市場)が続いており、有効求人倍率(※一人に対して何件の求人があるかを示す指標)も上昇を続けている。この背景には、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少が大きく影響している。転職をする割合も上昇をしており、流動性が高まっているため、企業は絶えず募集を続けていることも起因している。
また、職種での偏りも顕著で、専門人材と呼ばれる技術を持った層は引く手数多である。特に、DX化・IT技術の導入を事業変革の必須事項と考える企業も広がり、IT人材の枯渇が進んでいる。人材獲得に困っていない企業を見つける方が難しい、まさに人材獲得競争時代と言える。
人材獲得競争の現状
この競争状態により、人材獲得のためのサービスは非常に増えており、トレンドの移り変わりも激しい。求人広告の種類も増え、以前からの主流である掲載課金型から、スカウト型、マッチング型、成果報酬型、口コミ型など多岐に渡る。直接人材を紹介するサービスを提供する企業も参入障壁の低さから上昇傾向にある。また、昨今ではSNSを活用した採用手法も広がりを見せており、特に企業側は何をどう活用すれば、思ったような人材獲得に繋がるのか捉えきれていないのが実情である。
また、競争激化に加え、最低賃金の上昇に伴い、給与水準の引き上げも待ったなしの状況である。新卒者の初任給が年々上昇しており、合わせて既存社員との逆転を防ぐため、全体的な見直しも実施されている。この機に人事制度全体の見直しを行う企業も多い。体力のある企業であれば、人件費の上昇に耐えられるが、余力のない企業は、この賃上げトレンドに対応できず、最悪の場合、倒産の危機に瀕する。事実、新型コロナウイルスが落ち着いた最近では企業の倒産件数が着実に増えている。人件費を引き上げるということは、事業戦略・利益構造を見直すタイミングである。まさに、人材獲得は1つの人事テーマではなく、極めて重要度の高い「経営テーマ」だと言える。

人材獲得のための効果的な方法
前章でも触れたように、人材獲得のための方法は多岐に渡っており、何が効果的か判断できず、結局これまでの延長線上にある方法に終始するケースは多い。
ここでまずお伝えしたいのが、目先にある方法論や効果的な新サービスを模索しても、競争に巻き込まれ、特に中小企業は人材獲得競争に勝てない。これまでの主流であった応募者の数を追求し、その中から良いと思う人材にオファーを出す方法を盲目的に選択している企業は未だに多い。数を集め、確率論で採用を考え、想定数が残れば良いとする考え方は、生産年齢人口が減少している現在において、限界を迎えている。
それでは、どうすべきか。大事なポイントは、「人材獲得競争にならないようにする」ことである。自社が本来求めるべき人材像を徹底的に洗い出し、要件を設定する。その人材像に対して、共感を呼べる自社の訴求ポイント(強み)を軸に、採用戦略を作る。この戦略を実現するために最も効果の高い方法は何かを考え、その上で、先に挙げたようなサービスを検討する。集める採用から「集まる採用」にシフトチェンジすべきである。訴求ポイントが見つからない、自社にはないと言う経営者・人事担当者がいるが、以下2点を考えると良い。
1.求める人材像が誰でも良い、もしくはどの企業も求める条件ばかりになっていないか
⇒求める要件から考えることが難しければ、自社の既存社員の中で、活躍人材から想定をしていくことも1つである。その人物はどのような要件を持っているから活躍しているのか、他の社員との違いは何か、1つずつ洗い出しをしていくと明確にしやすい。
2.自社の訴求ポイントは既存社員にヒアリングをしてみる
⇒自社で働く社員は何か理由(縁)があって勤務をしている。この理由は、経営者が思うポイントと案外違っていることも多く、把握できていないことも多々ある。これを機会に、自社で勤務する理由(特に活躍人材の理由)を把握し、それを訴求ポイントの軸としたい。併せて課題も把握できれば、自社の働く環境改善に繋げることができる。
上記ステップを踏まえ、自社の採用戦略の軸を設定した上で、方法を検討すると良い。自ずと方法を絞られ、効果的な方法にたどり着きやすい。方法が決定できれば、必要な体制を作ることも必要である。多くの企業が現状の体制から検討してしまい、選択肢を狭めている現状がある。重要な経営課題だと認識できているのであれば、必要な体制を組むことに躊躇をしてはならない。採用担当部署に人材を厚くせずともできる体制づくりは、PJチームを作る、採用フローごとに区切って協力担当を決めるなどいくつもあるため、広く検討すべきである。
人材獲得競争で成功した企業事例
この人材獲得競争時代を勝ち抜いている事例を2つ紹介したい。
事例1.
売上高約40億円、社員数約80名の製造業の事例である。同企業は、長らく集める採用を実施していたものの、応募数は年々減少し続け、売上減少とともに社内の雰囲気も良い状態とは言えるものではなくなっていた。そこで経営者の世代交代とともに、事業変革を行い、情報発信も積極的に行うようにした。自社の強みは社員と設定し、働く様子や社内イベントの情報開示も積極的に実施した。具体的には、全社員交代制で、自社のSNSを更新していき、情報を発信し続けた。その結果、ファンが拡大していき、自社のブランディングはもちろん、結果として応募数が伸び、更に、自社理解をした上での入社のため、早期離職も減った。自社の強みを正しく認識し、全社体制で向き合った結果だと言える。
事例2.
もう1社は、売上高約500億円、社員数約1,700名でグループ経営をしている事例である。こちらも長らく集める採用を盲目的に実施していたものの、本来採りたい人材像とは違っていることを認識され、広告媒体への掲出を止め、対面で会うことに特化した。伝える内容も会社の課題点をあえて挙げ、変えていくためには、あなたに来て欲しいと直接かつ継続的に訴えかける形に変えたことにより、会社理解と共感した人材を安定的に確保ができるようになった。ありのままの姿を直接かつ継続的に提示することで接点を確保し、結果として、他社との差別化となり、自社を選ぶ理由になっている。
さいごに
人材獲得はマーケティング・ブランディングの考え方を持つことが重要であり、商品は会社と考える。すべての企業に合う効果的な方法は存在せず、自社においての軸(採用戦略)を持つべきである。軸がないまま、この熾烈な採用戦線を勝ち抜くことは不可能である。何をもって、どこで戦うのか、この考えを整理した上で、各社それぞれの方法を模索し続けることが重要である。正解も完成形もないものとして、常にアップデートをしていく。全社で取り組むものという認識を組織全体に広げることができれば、非常に強い。自社の取り組み方を改めて整理し、人が集まる状態になっているか、今一度、確認すべきである。
本事例に関連するサービス
関連動画