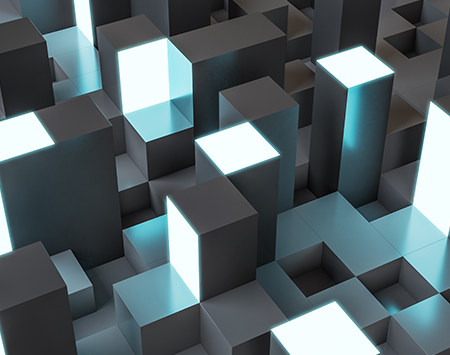人事コラム
失敗事例から学ぶ、人事制度改革の際の企業が取るべきアクション
「人事制度の改革」は企業の成長と競争力を維持するために重大な経営テーマの一つ

人事制度改革の重要性
国税庁の「民間給与実態統計調査」によると、2023年の平均勤続年数は男性が13.8年、女性が9.9年となっている。女性活躍の推進から女性の平均年数の推移は緩やかに上昇する中、男性はほぼ横ばいが続いている。
ただし、男性に見られる特筆すべき変化はその内訳にあり、男性の平均60歳以上は平均勤続年数を大きく伸ばす傍ら、50歳以下の平均勤続年数はいずれも低下傾向となっているのである。「活躍し続けることを望むシニア層」と、「より自身にフィットしたキャリアを求める若手~中堅層」に二分されている状態と言える。
また、総務省統計局のデータを見ると、日本における「転職希望者」は2023年時点で1,000万人を超える。これは就業者の15.3%に該当し、7名に1名以上の割合で、いつ、突然に自社の人材が離職してもおかしくない状態であることを意味する。
社会・経済環境が目まぐるしく変わる中で、働き手の仕事観・働き方の変化にも対応が求められており、人材の育成・定着に苦慮する企業は多い。このような背景から、人的資本戦略の基盤ともいえる人事制度の重要性は高まるばかりであり、"自社の戦略にあった人事制度への改革"に注目が集まるのは自然な流れと言える。

人事制度改革の失敗事例とその要因
とはいえ、性急な改革を進めてしまうと、かえって組織の反発を招いてしまう危険を孕む。
ここで筆者が人事制度改革に携わらせていただいた、あるクライアントについて、弊社に人事制度改定のお声がけをいただくまでの経緯を紹介したい。
ITサービスを展開する同社は、3年程前にオーナー家である社長主導のもと人事制度の見直しを行った。人材育成スピードの向上を目的に、等級フレームの見直しから評価構成、処遇反映ルールまで大きくテコ入れを図ったのである。中でも改革における目玉の一つは、これまでの行動評価に加え、新たに「目標管理制度(MBO)」を導入したことであった。会社の新しい成長フェーズに向け、社員に自律的な成長を促したいという社長の思いがあっての人事制度改定である。
プロジェクトの中で、資料を一通り拝見したが、人事制度そのものは整備されており、主だった不備・欠損は見られなかった。それでも、直近で行ったESアンケートではまさに"目標管理制度に対しての不満"が溢れており、「無理やり目標を設定させられて現場の負担が増えた」、「目標も評価結果も妥当性が分からない」などのコメントが階層を問わず寄せられた。報告レポートを見た社長は、「社員にとって意味がないなら、いっそ目標管理を無くすべきではないか――」と頭を抱えたという。
この企業の"失敗"における最たる要因は「経営者の想いが先行しすぎた結果、現場が置き去りになってしまったこと」にある。経営陣のみで人事制度改革を進めたため、突然完成した制度が降りてきた現場が面喰ってしまい、新しい仕組みやルールに拒絶反応が生じたのである。明確な目的のもと制度改革を行った場合でも、このようなコミュニケーションギャップや、現場の実状を考慮しない無理な運用によって躓いてしまうケースは多い。
これは一例であるが、人事制度改革が失敗するケースは他にもあり、筆者が目にしてきた「人事制度改定の失敗ケース」を掲載するので、参考にしていただきたい。
ケース1:プロジェクトが頓挫してしまう
策定の道半ばで、経営層や現場のトップとの折り合いがつかなくなり、制度の検討自体がストップしてしまう場合がある。これは特に、人事部を主体に制度改定を進めた時に行き当たる可能性が高い。フレキシブルな登用・処遇を実現したい人事部サイドと、人件費コントロールとのバランスを取りたい経営層、現場が見えているからこそハレーションを抑えたい部門長とで対立してしまうのである。
ケース2:構築した制度が自社にフィットせず、機能しない
初めに述べたクライアントのケースに近いが、制度そのものは問題なくとも、自社の文化や価値観あるいは規模にそぐわず、結果的に機能しない場合がある。せっかく変えるのだから、と現行制度から大幅なリニューアルを図った結果、制度が複雑化して運用の負担が大きくなりすぎたり、現場が持つ権限と等級・評価とで矛盾が生じたりした結果、現場が正しい運用を放棄してしまい、機能不全に陥ってしまうケースがある。
ケース3:導入時の対応に問題があり、定着しない
良い人事制度を構築したとしても、人事制度改革の目的や、具体的な内容が社員に十分に伝わっていない場合は、不安や抵抗感を招いてしまうことも多い。また、人事制度に合わせて研修等を実施し、評価者・被評価者ともにリテラシーを向上させていかなければ正しい運用がなされず、結果的にそもそもの改革を行った目的が達成されにくい状態となってしまう可能性がある。

人事制度改革を成功に導くポイントと具体的なアクション
人事制度改革に取り組む際に押さえていただきたいポイントと具体策は以下の3つである。
1.人事制度の方針を明確にすること
人事制度を変えることで何を実現したいのか、制度方針(ポリシー)を明確にすることが、人事制度改革の第一ステップとなる。文章の技巧や魅せ方にこだわる必要はないので、等級・評価・賃金それぞれにおける思想を明確にされたい。
経営戦略と合致したポリシーを軸とすることで、制度に一貫性が生まれるため、経営層の理解を得やすくなったり、社員に浸透させていく際も目的が伝わりやすくスムーズになる。また、検討を進める中で迷った時にも、端的で明確なポリシーが揺るぎない判断基準となってくれるのである。
2.社員の意見を取り入れること
特に、現行制度に対して現場からの不満が多い場合は、「制度設計に社員を巻き込むこと」を推奨する。各部門から管理職や社員の方々に直接、評価の検討プロジェクトに参画していただき、現場目線の意見を積極的に取り入れることで、社員の納得感を得ながら構築することが可能となる。さらに、導入時には制度改定の想いを共にしたメンバーが各事業部に点在することになるため、結果的に推進力も向上する効果が見込めるのである。
3.新人事制度導入~運用を通じて、徹底的に・繰り返し伝えること
当然ながら、一度の説明会のみで社員が目的や内容を十分に理解できることはない。あるクライアントでは、ドラスティックな制度改定を目指していたことから、社員との丁寧なコミュニケーションを重視し、社員向けの「新人事制度"中間"説明会」を開催したり、絵や図に富んだ読みやすいマニュアルの整備、社員全員との個別面談実施など、現場に寄り添った発信を様々な手法で行った。たとえ全ての社員からの賛同は得られなくとも、自社で活躍してほしい人材に想いを届けるためのコミュニケーションは、疎かにしてはならないポイントといえる。
また、導入後も定期的に社員の声を集め、ブラッシュアップをし続けることで、自社らしい強みのある制度を確立することが可能となる。
さいごに
「人事制度の改革」は企業の成長と競争力を維持するために重大な経営テーマの一つであるが、ともすれば社員の大量離職を招きかねないリスクもあることは、肝に銘じておくべきである。失敗事例から学び、自社の現状と照らし合わせた上で適切なアクションを取ることで、人事制度の変革を成功に導いていただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画