人事コラム
人事評価制度の種類別メリットとデメリットとは?
評価制度選定のポイントも解説
各評価制度の特性を正しく理解し、自社にあう制度選択を

人事評価制度の重要性
「人事評価は何のために実施するのか?」この質問をされた時、あなたは何と答えるだろうか。
評価者の回答の多くは、「賞与や昇給・昇格を決めるための査定」である。言い換えるならば、報酬や処遇を決定するためのツールと考えられていることが多いということである。もちろんこれも評価制度の役割の一つではあるが、本来求めるべき最終的な成果は「企業の成長」であり、評価を通じて個々の成長を促し、モチベーションを高め、求めるべき成果をあげながら、総合的に組織力を高めていくことを目的に実施されるべきものである。
つまり、人事評価制度は自社が成長するために、人と組織を育むための重要な経営の仕組みであると再認識していただきたい。

人事評価制度の種類
人事評価制度とは、先にも述べたように人と組織を育むための仕組みである。故に、評価制度に落とし込むべきポイントは、自社の進む方向に沿って、どれだけ進むことができたか(成果)、進めるための役割を全うできたか(行動・姿勢)を確認する項目を設定することである。代表的な評価制度の種類を以下に紹介する。
1.成果に対する評価の種類
(1)業績評価:評価期間中に生み出した成果の量(売上高、粗利益、営業利益、生産高、生産性など)が基準量にどの程度達したかを確認する
(2)目標達成度(MBO)評価:会社または自身で設定した目標に対する達成度と、成果創出への貢献度を確認する
2.行動・姿勢に対する評価の種類
(1)行動評価:求められる役割や行動がどの程度実践できたかを確認する
(2)コンピテンシー(プロセス)評価:わが社の優秀な社員の行動パターンをどの程度実践できたかを確認する
(3)理念実践(バリュー)評価:自社の経営理念やバリュー(行動規範)に応じた考え方や判断、行動がどの程度実践できたかを確認する
(4)スキル評価:業務遂行に必要なスキル(技術)をどの程度有しているかを確認する
(5)能力評価:業務遂行に必要な能力や知識をどの程度有しているかを確認する
(6)姿勢(情意)評価:業務に取り組む姿勢や意欲、心構えが役割に応じた適正なものであったかを確認する

各評価制度のメリット・デメリット
次に、各評価制度のメリットとデメリットを整理する。
(1)業績評価・目標達成度評価
①メリット:実績数字を基に全社業績やチーム成果への貢献度を定量的に、また客観的にはかることができる
②デメリット:設定目標の内容や難易度が個々の役割や成長レベルに対して妥当性が低い場合、本人のモチベーションや成果創出意欲の低下に繋がる懸念があり、想定の成長に繋がりにくい
(2)行動・コンピテンシー・理念実践評価
①メリット:求められる役割に対して実際に行動して顕在化された内容や結果が評価されるため、公平性が高い
また結果に対する上司からの正しいフィードバックによって、更なる成長、成果創出へ繋がりやすい
②デメリット:求められる役割の変化に応じた定期的な見直が必要であることや、会社の方針から求められる行動を各階層別に丁寧に落とし込んで設定していくなど、運用面で手間が多くかかる
(3)スキル・能力評価
①メリット:社員個々の成長段階に応じて身につけるべきスキルや能力が備わったかが評価されるため、どのスキルや知識を身につければ次のステージへ進めるかというキャリアパスがわかりやすい
②デメリット:保有スキル・能力が活用されて結果に繋がっていくまでの工程は評価には反映されないため、年功的な評価傾向に陥りやすい
また保有能力=発揮能力ではないため、業績への貢献度が低くても、経験値があるだけで評価が高くつきやすい
(4)姿勢評価
①メリット:仕事に取り組む態度、向き合い方を評価するため、組織内でのチームワークを醸成するために効果的
②デメリット:評価項目の大半が定性的かつ、潜在的な部分であるため、評価者の主観に左右されやすく、評価者の教育が十分になされていない場合は公平性にも欠ける評価に陥りやすい
それぞれの評価の特性を正しく理解し、自社の成長に対して効果的な評価制度を選定することが必要であり、またこれらを運用する体制を整えることが重要であることを改めて理解されたい。

人事評価制度選定のポイント
会社の成長と人材の成長を目指して評価制度を活用するのであれば、評価期間内における取り組みの評価も短期的・中期的・長期的の3つの観点から捉えて制度を構成することが望ましい。
まず、短期的な観点で言えば、その評価期間内における業績・実績を評価する項目を設定されるとよい。
特に、営業職や生産職は期間内において会社の方針に沿った明確な数字目標に対して、どの程度達成できたのかを比率で示し、評価に落とし込むことが望ましい。なお、成果評価では外部要因をどの程度反映させるかといった疑問を持つ方もいらっしゃるが、小生は外部環境まで含めた実績で見ることが好ましいと考える。つまり、運も評価に含めるという考えたかである。理由としては、それが会社の業績そのものであり、更なる成長を果すためには、その外部要因も含めた成長施策を検討することが必要であるからである。
一方、間接部門は会社の業績を生み出すために、方針に基づいて機能別に何をすべきかを検討して目標を立てる、いわゆるMBO型で短期的な取り組みを評価することがよいと考える。
続いて、中期的な観点で言えば、行動評価やコンピテンシー評価、スキル・能力評価が相応しい。
短期的な評価は外部環境や運も含めた評価として実施するのに対し、再現性がある取り組みができ、自社の成長の土台作りがどの程度できたかを評価する項目として評価を行う。まだまだ、成長著しい育成年代においては、この中期的評価のウエイトを高めて評価運用することで、将来的に安定的な業績をもたらす人材への成長に繋がっていく。
なお、役割等級制度を運用される企業において、自社内における活躍人材の定義が十分に整備されている場合はコンピテンシー評価を、活躍人材の定義がなくとも、求める役割基準が明確に示されている場合は行動評価を活用することが望ましい。
また、職能資格制度を運用される企業においては、成長段階に応じて設定されている能力基準に基づいたスキル・能力評価を活用することが望ましい。
最後に、長期的な観点で言えば、姿勢評価や理念実践評価を用いるのがよい。
長期的な視点で成果を求めるためには、社員一人ひとりが進むべき方向性が理解できている、または共感されていることが必要である。どの程度その理解ができているか、それに準ずる考え方や行動がアウトプットされているかを評価、フィードバックすることで、組織の統一性が高まり、生産性高く、大きな成果に繋げていく。なお、理念実践評価は、姿勢評価と比べ、自社の理念やパーパスの浸透を推進する機能も持つため、理念経営を目指されている企業であれば採用されることを薦めたい。
以上、3つの観点から自社の評価制度を再構築する際、どの評価制度を選定することが望ましいかを検討されたい。
さいごに
繰り返しになるが、評価制度の運用目的は、「企業の成長」であり、評価を通じて個々の成長を促し、モチベーションを高め、求めるべき成果をあげながら、総合的に組織力を高めていくことである。改めて、単に社員の点数をつける制度ではないことを認識いただいたうえで、評価制度の選択を行っていただきたい。
故に、自社内で評価しやすい制度を選択するのではなく、評価すべき制度を選択するべきである。
そのためには、導入する制度のメリットとデメリットを正しく理解した上で、設計以上に運用面における制度設計にも充分に時間を割いて取り組んでいただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画
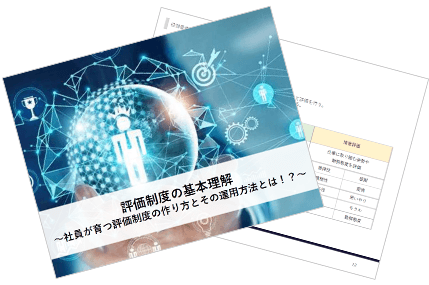
評価制度の基本理解
~社員が育つ評価制度の作り方とその運用方法とは!?~
単なるモノサシではなく、社員が育つ適切な評価制度の作り方、ならびにその運用方法を事例を交えて解説します。
この資料をダウンロードする



