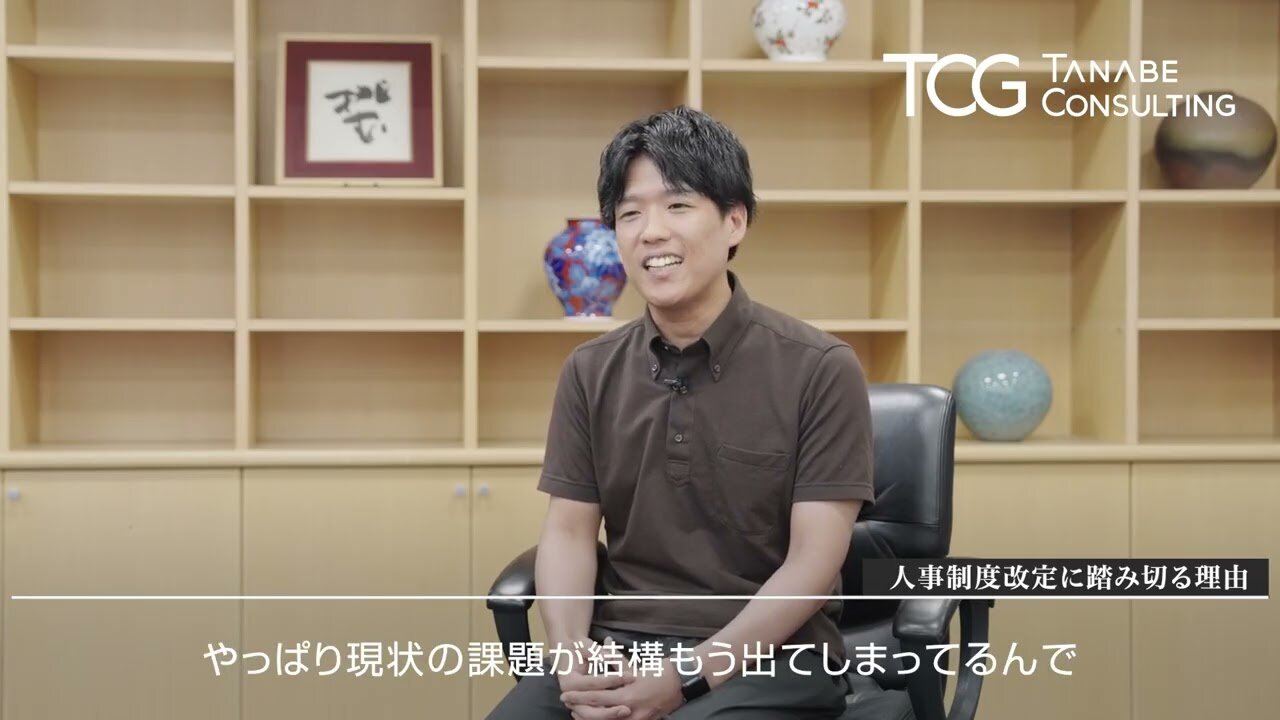人事コラム
評価制度の設計ポイントと各種評価手法のメリット・デメリット
自社に最適な評価制度と適切な運用を実現するためのポイント解説

評価制度における設計業務
評価制度における設計業務とは、企業や組織が従業員の業績や行動を公正かつ客観的に評価するための枠組みを設計・構築することである。評価制度の設計業務は、従業員のモチベーションを高め、組織全体のパフォーマンスを向上させるために極めて重要であり、具体的な手順が必要です。
まず、従業員の業績や行動を評価するための尺度を定めるための評価基準の設定が必要である。評価基準は、業務内容や役職に応じて異なるため、従業員の職務内容を詳細に把握し、それに対応した基準を設けることが重要である。例えば、営業職であれば売上や新規顧客の獲得数、技術職であればプロジェクトの完遂度や技術的な貢献度が評価基準となる。
次に、評価の手順を明確化する必要がある。評価手順には、評価の頻度、評価者の選定、評価方法などが含まれる。評価の頻度については、年次評価や半期評価、四半期評価などが一般的である。また評価者は、直属の上司だけでなく、同僚や部下からのフィードバックを含める360度評価も考慮される。評価方法としては、定量的なデータと定性的なフィードバックを組み合わせることが有効である。
評価制度の設計において、従業員のモチベーションを高めるためには、評価結果をどのようにフィードバックするかが重要である。具体的な改善点や達成度を明示し、次回の評価に向けた目標設定を行うことで、従業員は自身の成長を実感しやすくなる。また、評価結果に基づいた報酬や昇進の決定も、従業員のモチベーションを高める要因となる。

評価制度の目的と必要性
評価制度は、従業員のパフォーマンスを公正かつ客観的に評価し、適切なフィードバックを提供する仕組みであり、従業員のモチベーション向上やスキルアップが促進され、組織全体の生産性が向上するものである。
評価制度は従業員の成果を可視化するための重要な制度でもある。明確な評価基準が設定されることで、従業員は自らの目標を明確にし、達成に向けた行動を計画的に進めることができる。また、評価結果を基にしたフィードバックは、従業員の成長をサポートし、キャリアパスの明確化にも寄与するものである。
さらに、公正な評価制度は組織内の信頼関係を築く上で不可欠である。従業員が公平に評価されることを実感することで、組織に対する信頼感が高まり、長期的な雇用関係の構築が可能となる。これにより、優秀な人材の流出を防ぎ、企業の競争力を維持することができる。
最後に、評価制度は経営戦略の一環としても重要である。組織の目標と個々の従業員の目標を一致させることで、全社一丸となって目標達成に向かうことができる。これにより、企業全体のパフォーマンスが向上し、市場での競争優位性を確保することが可能である。

評価制度の考え方と設計ポイント
大前提として評価制度とは、賃金や賞与など処遇を決めるためだけの仕組みではなく、企業の理念・ビジョン・戦略を実現に向けた人材育成の一貫として捉えて頂きたい。評価制度を通じて会社から求められる水準に対してどこまで出来ているのか(強み)・どこまで出来ていないか(弱み)を個人ごとに定点観測(通年or半期)し、翌期に向けて強みを伸ばし、不足事項を補う一つの指標として教育や育成へと繋げる。
そのような考えのもと以下、5つのポイントにて設計を行う事が一般的である。
- ①評価項目:
- 等級や資格別の社員に求める姿やあるべき姿より評価したい項目や意識的に取り組む項目を設計する。
- ②評価ウエイト:
- 評価項目ごとに評価点数の配分を設計する。
等級や資格別に重要度の高い項目の点数を厚くするケースが多い。 - ③評価の着眼点:
- 等級や資格別に評価する視点を明文化し、評価者による評価の観点がブレないように設計する。
- ④段階評価の基準:
- 評価項目ごとに付ける点数の基準を設計する。
5段階評価が一般的であるが、評価点数が中心に寄る事を防ぐために4段階評価にするケースもある。 - ⑤評価ランク:
- 評価点数の合計点数を評価ランクに落とし込み、働きぶりを処遇へ反映させるランク付けを行う。
- ⑥評価シート:
- 等級や資格別に上記①~④の内容に加え、自身の働きぶりを振り返るコメント欄を設計する事も多い。
※タナベコンサルティングでは上記以外にも実運用を見据えて評価スケジュールやフィードバック面談の仕組みなども合わせて設計を行う。
評価手法とそれぞれのメリット・デメリット
代表的な評価手法のそれぞれのメリット・デメリットを4つ紹介する。
| 名称 | MBO評価(目標管理) | コンピテンシー評価 | スキルマップ評価 | 360度評価 |
| 特徴 | 会社や部門の方針を元に個人あるいはチーム単位で設定した目標を評価する方法 | ハイパフォーマー社員に共通する行動特性を元に評価項目を設定する方法 | 業務を遂行する上で必要な能力・スキル・知識を評価する方法 | 複数の関係者(上司・部下・同僚)から評価を行う方法 |
|---|---|---|---|---|
| メリット | 目標設定時より被評価者が関与する事で、やらされ感が減り能動的に目標に向かう事ができる | 会社の方向性と合致した評価項目を設計する為、より高い育成効果が期待できる | 業務上必要なスキルが分かりやすく、スキル毎に習得できている項目と不足している項目を 洗い出す事ができる |
被考課者の納得性が高くなる様々な目線で評価を受けるため、被考課者の気づきが多くなる |
| デメリット | 設定する目標の難易度にバラつきが出やすく、目標設定のスキルが求められる | ハイパフォーマー社員へどのような行動特性が成果に結びついているのかヒアリングに時間を要する | スキルだけの評価になってしまい、生み出す成果ではなくスキルを習得する事が目的になってしまう可能性がある | 馴れ合いや忖度により、公正な評価とならない可能性がある |
| 推奨する 対象者 |
営業職など目標が明確な職種 または、経営戦略の実行が役割である管理職層 |
日常の業務活動を観察する事ができる職種 (物理的に距離がある場合は適合し辛い) |
製造業など業務スキルが明確な職種 | 全職種にて導入する事が出来るが、組織の発達段階に応じて検討する必要がある |
ポイントは上記の通りであるが、必ずしも一つを選択しなければならないわけではなく、MBO評価とコンピテンシー評価など評価手法を複合的に組み合わせて設計し、自社に適合する評価項目を設定していただきたい。

評価制度の運用ポイント
評価制度は構築して終わりではなく、正しい運用を通じて本来の価値が生まれる。
正しく運用するためには、自社における評価制度の目的や評価項目の意味合いについて、評価に関わる全ての社員が十分に理解している状態を作る事が必要である。
そのためには評価制度の説明はもちろんのこと考課者に対する研修や被考課者に対する研修を行い、評価スキルや評価に対する認識レベルを向上させていく事が必要である。
また、評価制度は実際に運用をしていく中で改善点が判明するケースも珍しくない。
運用を通じて適宜ブラッシュアップしていく事を前提に、予め「評価見直し委員会」など定期的に見直す機会を仕組み化しておく事が理想とする制度へと繋がる。
改めて制度設計が目的ではなく、本来の目指すべき評価制度が運用を通じて実現出来ているのかという点に着目し、運用していただきたい。
さいごに
評価制度をはじめとした人事制度は、不変的なものではなく、会社の成長に合わせ適宜アップデートしていく事を推奨している。2023年度現在、タナベコンサルティングへのHR関連の問い合わせ内容は多くが人事制度再構築の依頼である。
時代の変化や会社の目指すべき方向性に合わせ、常に最適な制度設計となっているかを見定めていただきたい。
そして、社員は会社にとって最重要の資本であることを忘れてはならない。
本コラムが、最適な評価制度設計の一助となれば幸いである。
本事例に関連するサービス

人事制度運用・定着・浸透コンサルティング
制度の運用プロセスを最適化し、効果的なコミュニケーション戦略を通じて、従業員の理解と協力を促進します。また、制度の定着を図ることで、 組織の目標達成に貢献し、持続可能な成長を支援します。
人事制度運用・定着・浸透コンサルティングの詳細はこちら