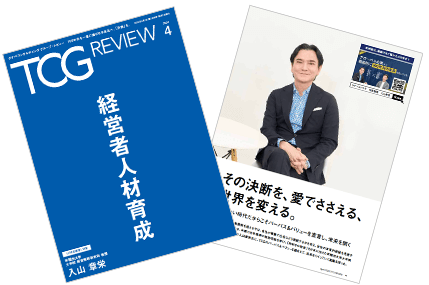人事コラム
役員定年とは~役員定年制のメリットとデメリット

役員定年とは
まずはじめに、「役員」を以下の通り定義する。そもそも「役員」とは法令上の地位では、会社法に規定され、株式総会によって選任される役員として取締役、会計参与および監査役を掲げ、指名委員会等設置会社においては取締役会によって選任される執行役のことである。つまり、会社を代表する事業主側として、社員を雇用する側の人間となる。「役員」は社員ではないため、労災などの対象にならない。
役員定年とは上記の「役員」に定年を定めることである。しかし、法律上は定年の定めがないため、健康である限りいつまでも働き続けることができる。そうなれば、高齢になった役員が会社に残り続け、新陳代謝が進まないことになる。
さらに、株主との関係でも経営陣の刷新が求められることもある。
そのため、上場企業や大企業では役員定年制を導入している場合が多い。
しかし、わが国で圧倒的に多くを占める中小企業は同族経営や創業者企業が多いため、経営陣に身を引かせる定年制は導入されにくいという実態がある。

参考までに、やや古い情報ではあるが、企業規模別の役員定年制導入実態を見ると、社員規模が大きいほど、導入比率は高くなる。
・1,000人以上 71.4%
・300~999人 58.8%
・300人未満 20.9%
(出典:労務行政研究所「2016年役員報酬・賞与等の最新実態」)
別の視点から見ると、役員の階層別定年年齢は次の通りである。
・会長 70歳(50%)、67歳(15%)
・社長 65歳(35.7%)、68歳(21.4%)
・専務 65歳(34%)、63歳(20%)
・常務 65歳(28%)64歳・63歳(18%)
・取締役 65歳(26.5%)、63歳(24.5%)
(出典:労務行政研究所「2016年役員報酬・賞与等の最新実態」)
社長、専務、常務、取締役は65歳定年が最も多い。世の中の流れでは、企業に求められる就業確保措置の実施(高年齢者雇用安定法の改正:2021年4月から)により、事業主は70歳まで社員を雇用しなければならない努力義務がある。その意味では、役員定年も将来的に70歳が主流となる可能性がある。

役員定年制の導入背景
役員定年制の導入背景には、いくつかの要因が考えられる。まず、企業の持続的な成長を目指すためには、新しい視点やアイデアを取り入れることが重要である。役員定年を設定することで、若手や中堅の社員にも役員としてのチャンスを与えることができ、組織全体の活性化を図ることができるのである。
また、役員定年制の導入はガバナンスの強化にも寄与する。長期間にわたって同じ役員が在籍することで、企業の意思決定が一部の人物に偏るリスクがある。役員定年を設けることで、定期的な役員の交代が促進され、透明性の高い経営が実現されるのである。
さらに、役員定年後の再雇用も重要な視点である。役員としての経験や知識を持つ人物を完全に退職させるのではなく、顧問やアドバイザーとして再雇用することで、企業にとって有益なアドバイスを受け続けることが可能である。これにより、企業は役員の退任後もその知見を活用し続けることができるのである。
役員定年に関する規程は、企業ごとに異なるが、一般的には60歳から70歳の間に設定されることが多い。これらの規程は、企業の経営戦略や業界の特性に応じて柔軟に設定されるべきである。役員定年制の導入背景を理解することで、そのメリットとデメリットをより深く考察することができるのである。
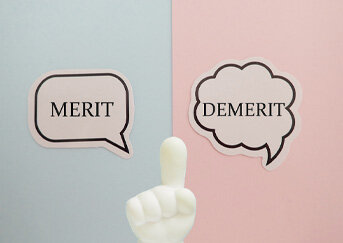
役員定年制のメリットとデメリット
(1)役員定年制のメリットについて、以下の通りである。
①経営陣の新陳代謝を決め事(ルール)として進められる
②社員に定年制を導入している場合、組織全体として一体感を高められる
③長く留任する経営者がいる場合、周囲がイエスマンばかりになったり、考えない社員ばかりになるリスクを防止できる
(2)役員定年制のデメリットについて、以下の通りである
①有能かつ必要であってもルールに従って退任せざるを得ない
②経営等のトップに適切な後継人材がいない場合(育っていない場合)がある
③実績・実力が伴わなくとも、定年まで任期を務めさせる温情が生じる可能性がある
企業が、デメリット①②のリスク回避方法として、特別の事情がある場合は定年延長ができる旨を役員規程等に定めることもある。
また、サクセッションプラン(後継者育成計画)を展開し、後継候補者を計画的に養成することで後継者不在を招かぬようにする必要がある。
③は、定年年齢までの雇用保障となってしまう可能性がある。退任すべき役員であっても、「定年まであと何年だから」と再任させることがある。

役員定年制を導入する際のポイント
役員定年制を導入する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要がある。
まず、法的要件について確認しておくことが不可欠である。役員定年に関する規程を明確にし、その内容を就業規則や役員規程に反映させることが求められる。また、定年後の役員の再雇用についても具体的な方針を定めておくことが重要である。再雇用に関する条件や役割を明確にすることで、役員のモチベーションを維持しつつ、組織の安定運営を図ることができる。
次に、社内コミュニケーションの重要性である。役員定年制を導入する際には、全社員に対してその趣旨や目的を明確に伝えることが必要である。特に、役員本人やその周囲のスタッフに対しては、事前に丁寧な説明と相談を行うことが求められる。これにより、役員定年制に対する理解と協力を得やすくなり、スムーズな移行が可能となる。
最後に、定年後の役員の活用方法についても考慮すべきである。役員定年後も、再雇用やアドバイザーとしての活用が考えられる。これにより、豊富な経験と知識を持つ役員が引き続き組織に貢献できる環境を整えることができる。また、定年後の役員が新たな役割を担うことで、若手社員の育成や新しい視点の導入にも寄与することができる。

役員任期制の併用
株式会社の役員(取締役や監査役)には任期がある。通常、取締役の任期は2年(監査役は4年)であるが、非上場会社の場合は、最長任期を5期(10年)とすることができる。
役員定年制と役員任期制を併用することで、定年年齢または最長任期のどちらかに至った時点で取締役を退任するという仕組みである。
任期到来の役員は原則として退任になるが、満了後も継続して役員を務める場合は、一度退任した上で再任の手続きを経ることで継続することとなる。つまり、自動で継続とはならないことに留意が必要である。
しかし、若くして役員になる優秀人材にとっては、定年や任期到来により、退任となるため企業の事情にあわせて採用を慎重に検討する必要がある。
本事例に関連するサービス
関連動画

企業価値を高める役員報酬の決め方と見直しのポイント
多様な役員報酬制度のメリット・デメリットを具体例とともにご紹介します。経営陣のモチベーション向上やガバナンス強化を目指す企業様必見の内容です。
この資料をダウンロードする