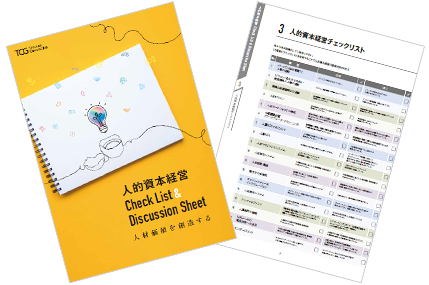人的資本経営が求められる背景とは
人的資本経営とは、「人材」をこれまでの代替可能な資源の一つとする考え方から、代替不可能な資産として再定義し、その価値を最大限に引き出すために戦略的な投資を行い、適切な配置によって活躍を促すことで、中長期的な企業価値の向上を目指す経営の在り方を指す。言い換えれば、「人材」を軸に置いた経営である。
日本では数年前から広まり始めた言葉だが、その起源は18世紀にまで遡る。経済学者アダム・スミスが著書『国富論』の中で、特別な技能や熟練を要する職業のために時間と労力をかけて教育された人材を「高価な機械」に例えた記述があり、これが人的資本概念の始まりとされている。つまり、この考え方は約250年前から存在しているのである。
現在、日本企業では労働生産性の低さや少子高齢化による労働環境の課題が顕在化しており、人材や働き方の多様化が進む中で、投資家のESG経営への関心が高まっている。こうした背景から、人的資本経営の重要性が高まっているのである。

人的資本経営を推し進めていくために押さえるポイント
人的資本経営を進めるためには、経済産業省が公表している「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会」(通称:人材版伊藤レポート)で示されている「3つの視点」と「5つの共通要素」を押さえることが重要である。
「3つの視点」とは、❶経営戦略と人材戦略の連動、❷As is-To beギャップの定量把握、❸企業文化への定着である。
具体的には、自社の経営理念やビジョンを実現するために、事業戦略と経営戦略を明確化し、それを基に組織・人材戦略へと落とし込むことが求められる。そして、戦略を実現するために強化・実行すべきポイントを、ありたいの姿(To be)と現状(As is)のギャップとして定量的に把握する必要がある。また、目指すべき姿を実現するために、企業の考え方を社内の組織体制や制度、事業の進め方に反映させ、意図的に企業文化を醸成していく取り組みが重要だ。
一方、「5つの共通要素」とは、❶動的な人材ポートフォリオ、❷知識・経験のダイバーシティ、❸リスキル(学び直し)、❹従業員エンゲージメント、❺時間や場所にとらわれない働き方を指す。
これらを実現するためには、必要な時に、必要な人材が、必要な場所で、必要な力を発揮できるよう、人材データを整理し、必要な教育投資を継続的に実施することが求められる。
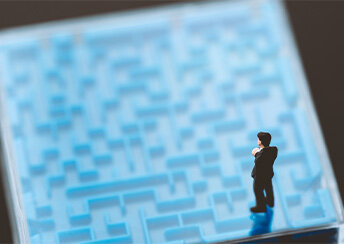
大企業における人的資本経営実践のロードマップ
人的資本の必要性を掲げ、具体的なアクションを起こしている企業は増加傾向にある。しかし、依然として情報開示にとどまっている企業や、課題を認識しているものの対策を講じられていない企業、対策を実施しても効果検証が十分に行われていない企業など、その実装フェーズはさまざまであり、取り組み方に悩む企業も少なくない。 そこで、人的資本経営を実装するためのロードマップについて簡単に解説する。
人的資本経営を実装するロードマップは、大きく以下の4つのフェーズに分けられる。
各フェーズの目的と押さえるべきポイントは次の通りである。
Phase 1.現状認識フェーズ
組織と人材の現状をありのままに正確に把握し、データを整理するとともに、成長課題を特定することが最初のフェーズである。課題を見つけるためには、現状を把握するだけでなく、将来の「ありたい姿」をどれだけ明確に定められているかが重要である。目指すものがなければ、成長課題を見つけることはできない。その場合、発見されるのは目の前で発生している短期的な改善策にすぎない課題だけである。
現状認識フェーズでは、現在の状況を正しく認識するとともに、「ありたい姿」を明確にし、そのギャップを正確に捉えることが何より重要である。
Phase 2.戦略設計フェーズ
PMVV(パーパス・ミッション・ビジョン・バリュー)を実現するために、人材ポートフォリオを構築し、人的資本KPI(重要業績評価指標)を設定するフェーズである。単なる目標設定ではなく、戦略を実現するための目標設定が求められる。内外部の環境変化を捉えながら、事業ポートフォリオの形を変更する場合、その形を実現するために組織体制を変化させ、各社員の役割を見直し、必要な人材を獲得する必要がある。
その形に沿った人材ポートフォリオを描き、現状とのギャップを把握したうえで、人的資本KPIを設定し、具体的なアクションプランに落とし込むことが重要である。
一部の企業では、現在の人員構成を基に退職者を考慮した採用KPIを策定しているが、これは間違いではないものの、人的資本経営を実装するという観点では視座が低く、短期的な人事施策にとどまる可能性がある。
Phase 3.実行フェーズ
計画を実現するためのアクションプランを実行するフェーズである。単に実行するだけではなく、想定した成果が出ているかを定期的に確認し、必要に応じて改良を加えながら進めることが求められる。そのためには、進捗を確認する場を設けることが重要である。
特に大企業では、人的資本推進委員会などを立ち上げ、定期的に状況を観察する仕組みを導入することが有効である。また、客観的に各社員のエンゲージメントを評価するために、パルスサーベイを実施し、社員の心理的な状態を可視化して確認することも、人的資本経営の実装において欠かせない。
Phase 4.開示フェーズ
ステークホルダーに対して情報を開示し、適切なコミュニケーションを行うフェーズである。上場企業においては、非財務情報の開示が2023年より義務化され、各社はそれぞれの数値指標を開示している。具体的には、採用予定数、勤続年数、女性管理職比率、有給休暇取得率、一人当たりの教育費、エンゲージメント指数などが挙げられる。
一方で、ステークホルダーが重視するのは、これらの開示情報が企業の成長にどのように繋がるかである。たとえ良い数値を並べたとしても、ステークホルダーがその数値に対してサステナビリティを感じなければ、信頼を得ることはできず、企業価値の向上には繋がらない。
つまり、将来の発展性を踏まえた真の課題に対して、目標と現状、そしてそのギャップをどのように実践して改善していくのかを具体的な施策に落とし込んで示すことが重要であると考える。ステークホルダーが見ているのは今の数字ではなく、数字の変化と、変化させるための施策である。小生もこれまでに開示された非財務情報に目を通してきたが、現状の人事指数が低い企業であっても株価が上昇している企業は多く存在する。その共通点を挙げるとすれば、改善に向けた具体的な行動が明確に示されている点である。
なお、財務情報の開示義務は上場企業にのみ課せられているものの、非上場企業においても率先して情報開示を行い、人的資本経営に取り組む意思を示すことで、企業の信頼度を高め、事業・資本・採用戦略にも繋げていただきたい。
さいごに
ここまで人的資本経営の進め方について解説してきたが、最後に一点だけ補足する。 経営は当然ながら経営陣が中心となって行うものである。しかし、人的資本経営を推進するためには、社員からのダイレクトな声に耳を傾けることが必要である。冒頭にも述べたように、人的資本経営は「人材」に軸を置いた経営である。社員の声なくして、人的資本経営で成功を収めることはないと言っても過言ではない。
企業規模が大きくなればなるほど、経営者と社員の距離は遠のきやすくなる傾向がある。しかし、だからこそ、社員が経営を身近に感じられるような社内の取り組みに力を入れるべきである。社員の声を適切に反映させることで、組織全体の一体感を高め、人的資本経営の成功に繋げていただきたい。
関連情報
-
人事コラム人的資本経営が注目される背景と企業に求められる対応策をご紹介
-
人事コラム『人的資本経営』の実装ポイント
-
人事コラム人的資本経営実装に向けた現状把握のポイント
-
人事コラム人的資本の情報開示とは~人的資本経営実装のポイント
-
人事コラム人的資本経営を実現するためのエンゲージメント戦略とは
-
人事コラム人的資本経営から考える人事KPIの設定ポイントとは
-
人事コラム人的資本経営における企業が直面した課題と解決策
-
人事コラム人的資本経営を成功に導く指標の役割と運用のポイント
-
人事コラム人的資本経営に向けて人事部が担うべき役割とは?
-
人事コラム人的資本の実装ポイント
-
課題解決人的資本経営完全ガイド~基本情報から取り組み事例まで一挙ご紹介
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
ゼネラルマネジャー三好 皓之
- 主な実績
-
- 物流企業向人事制度再構築コンサルティング
- 金属部品メーカー向人事制度再構築コンサルティング
- 卸売業の中長期ビジョン構築コンサルティング
- 生産機器メーカーの事業再生コンサルティング
- 食品メーカーの幹部候補者育成支援コンサルティング
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト