人事コラム
絶対評価とは?
絶対評価と相対評価の組み合わせで人事評価の最適化を目指す

ビジネス環境における人事評価の重要性
現代のビジネス環境は、変化のスピードが速く、競争も激化している。
企業が持続的な成長を遂げるためには、優秀な人材を確保・育成し、最大限に活躍いただくことが不可欠である。
そのために人事評価は極めて重要な役割を果たす。
人事評価は、社員の能力・実績・行動などを客観的に評価し、その結果を本人にフィードバックすることで個人の成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上に繋げるためのツールである。
適切な評価制度は、社員のモチベーションを高め、エンゲージメントを向上させ、優秀な人材の定着を促進する。
また、評価結果は昇給・昇格・異動・研修へのアサインなどの人事処遇の決定に用いられ、社員のキャリア形成を支援する。
さらに、人事評価は組織全体の戦略目標達成にも貢献する。
個々の社員の目標設定を組織目標と連携させることで、組織と個人が同じ方向を向き、目標達成に向けた取り組みを加速させることができる。
しかし、評価制度が適切に設計・運用されていない場合、個々の貢献や成長に応じて報いることが難しく、社員の不満や不信感を招き、モチベーションの低下や離職率の上昇に繋がる可能性もある。
そのため、企業は自社のビジネスモデルや組織文化(組織カルチャー)に合った、公平で納得感のある評価制度を構築し、運用することが極めて重要である。

絶対評価と相対評価の概要と違い
人事評価の方法は多岐にわたるが、評価結果を決定する仕組みの代表的なものとして絶対評価と相対評価が挙げられる。
絶対評価とは、社員の能力や実績を、事前に設定された評価基準に基づいて評価する方法である。社員一人ひとりの成果を、他の社員と比較することなく、予め定められている基準に沿って評価を行う。例えば、「売上目標を達成した」「新しい顧客を獲得した」など、具体的な成果や行動に基づいて評価を行う。
絶対評価のメリットは、個々の社員の努力や成果を正当に評価できる点である。優秀な社員は他の社員のパフォーマンスに左右されず、高い評価を得ることができる。また、絶対評価は、社員の成長を促進する効果も期待できる。事前に設定された評価基準を明確にすることで、社員は自身の強みや弱みを理解し、改善点を見つけることができる。
一方、絶対評価のデメリットは、評価者によるばらつきやブレが生じる傾向にある点である。評価者が社員に良い評価を与えようとする心理など様々なバイアスが働くため、評価基準が曖昧になったり、形骸化する可能性がある。
また、評価者の評価レベルが一定以上育まれていないと想定以上に高い評価ランクが頻出してしまい、結果的に相対的な調整を行わざるを得ない状況になる場合もある。
相対評価とは、社員の能力や実績を、他の社員と比較して評価する方法である。例えば、上位何%をS評価、次の何%をA評価というように、社員をグループ分けして評価を行う。
相対評価のメリットは、評価の公平性を保ちやすい点である。社員を比較して評価するため、評価者による評価のばらつきを抑えることができる。また、相対評価は、組織内の競争意識を高める効果も期待できる。社員は、他の社員よりも良い評価を得ようと努力するため、組織全体のパフォーマンス向上に繋がる可能性がある。
一方、相対評価のデメリットは、個々の社員の努力や成果が反映されにくい点である。
たとえ優秀な社員であっても、他の社員よりもパフォーマンスが低ければ、低い評価を受ける可能性がある。
また、常に他の社員と比較されるため、競争に疲れてしまったり、不公平感を抱いたりする社員が出てくる可能性があり、
結果、社員のモチベーションを低下させる可能性がある。

絶対評価と相対評価の組み合わせの必要性
絶対評価と相対評価は、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらか一方だけでは、必ずしも最適な人事評価を実現できるとは限らない。絶対評価は、個々の社員の努力や成果を正当に評価できる一方、評価者によるばらつきが生じやすい傾向がある。一方、相対評価は、評価の公平性を保ちやすい一方、個々の社員の努力や成果が反映されにくいという問題点がある。
そこで、絶対評価と相対評価を組み合わせることで、それぞれのメリットを活かし、デメリットを補完し合うことが重要になる。絶対評価で個々の社員の能力や実績を評価し、その結果を相対評価で調整することで、より公平で納得感のある人事評価を実現することができる。
例えば、絶対評価で一定以上の評価を得た社員は、相対評価の対象から除外することで、優秀な社員のモチベーションを維持することができる。また、相対評価の結果を絶対評価の参考にすることで、評価の偏りを防ぐことができる。

絶対評価と相対評価を組み合わせた人事評価の最適化方法
絶対評価と相対評価を組み合わせた人事評価を最適化するためには、以下の点に注意する必要がある。
⑴評価基準の明確化:絶対評価の評価基準を明確にすることで、評価の客観性と公平性を高めることができる。評価基準は、具体的で測定可能なものにする必要がある。例えば、「売上目標達成率」「顧客満足度」「プロジェクトの完了」など、具体的な数値や成果に基づいて評価を行う。
⑵評価者のトレーニング:評価者に対して、評価の目的や評価基準、評価方法に関するトレーニングを実施することで、評価のばらつきを抑えることができる。評価者は、社員の行動や成果を客観的に観察し、評価基準に照らし合わせて評価を行う必要がある。
⑶フィードバックの徹底:評価結果を本人にフィードバックすることで、社員の成長を促し、モチベーションを高めることができる。フィードバックは、具体的な事例に基づいて、良かった点と改善点を伝える必要がある。
⑷目標設定の工夫:社員の目標設定を組織全体の戦略目標と連携させることで、組織全体のベクトルを合わせ、目標達成に向けた取り組みを加速させることができる。目標は、SMARTの法則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)に基づいて設定する必要がある。
⑸評価結果の活用:評価結果を昇給、昇格、異動、研修などの人事処遇の決定に活用することで、社員のキャリア形成を支援することができる。評価結果は、社員の能力開発やキャリアプランニングにも役立てることができる。
絶対評価と相対評価の組み合わせ方は、企業の規模や業種、組織文化によって異なるものの、タナベコンサルティングでは、個々の働きぶりを把握している一次・二次評価者は絶対評価、組織全体を俯瞰して見ている三次評価者は相対評価にて行うことを推奨している。
また、三次評価者の相対評価はあくまでも評価者による評価のバラつきを確認するものであり、一方的に評価ランク別の出現率に当てはめるということではない旨、留意いただきたい。

絶対評価と相対評価の組み合わせによる効果
絶対評価と相対評価を組み合わせた人事評価を適切に運用することで、以下の効果が期待できる。
⑴社員のモチベーション向上:公平で納得感のある評価制度は、社員のモチベーションを高めエンゲージメントを向上させる。
⑵優秀な人材の定着:優秀な社員は、正当な評価を受けることで企業への愛着を深め定着する理由となる。
⑶組織全体のパフォーマンス向上:個々の社員の目標設定を組織全体の戦略目標と連携させることで、組織全体のベクトルを合わせ、目標達成に向けた取り組みを加速させることができる。
⑷公平性の確保:絶対評価と相対評価を組み合わせることで評価の偏りを防ぎ、より公平な評価を実現することができる。
⑸透明性の向上:評価の理由や評価基準を明確にすることで社員の不信感を解消し、評価制度への理解を深めることができる。
絶対評価と相対評価の組み合わせは、人事評価制度の最適化に向けて有効な手段である。自社の状況に合わせて、最適な組み合わせ方を選択し、社員の成長と組織全体のパフォーマンス向上を目指していただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画
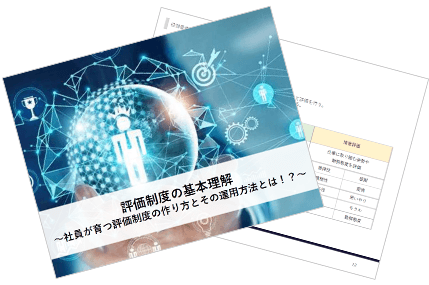
評価制度の基本理解
~社員が育つ評価制度の作り方とその運用方法とは!?~
単なるモノサシではなく、社員が育つ適切な評価制度の作り方、ならびにその運用方法を事例を交えて解説します。
この資料をダウンロードする



