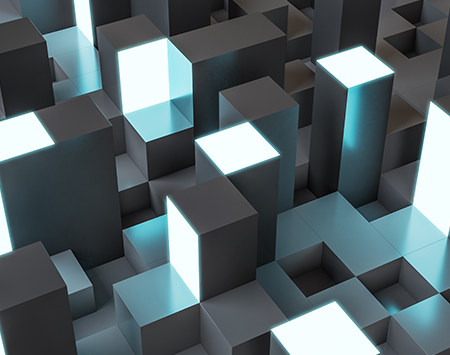人事制度は経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画と連動させましょう。

経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画に宿る未来への意志と未来の姿
内発的動機を引き起こすため、経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画にどこまで共感、共鳴できるのかが重要とされています。共感・共鳴を得ることは目的ではないですが、「経営とは社員の協力を得て、トップの想いを実現すること(タナベコンサルティング 幹部候補生スクールテキストより)」から、働く方々とそのご家族の賛同を得ることは重要な経営課題だと言えます。経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画には、経営の意志、世の中に対する存在意義、未来永劫目指すことを、経営者の魂と共に文言やデザインに吹き込みます。
ここで経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画が千差万別に理解されては、わが社の目指す有り様に近づかないため、理解の仕方、行動のあり方を示す必要が出てきます。表現が抽象的やアイコニックであったとしても、受け止め理解する上では、現実性、具体性、実現性、納得性が必要です。
これらを示し、行動に変換してゆく経営システムの1つが人事制度だと言えます。

トップ方針を咀嚼して行動レベルへ展開する
人事制度は経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画と連動しているのが最も納得性が高いと言えます。
従って人事制度の見直しを行うタイミングとしては、これらの経営方針が変わるタイミングです。人事制度はトップ方針と同様、トップからのメッセージであり、このメッセージを咀嚼して理解する必要があります。トップ方針を人事制度に向けて展開するとは、行動言語で評価軸に展開することです。行動の足並みを揃えて成果に向かうことが、組織と個人には求められます。理念に沿った行動、役割と責任に基づいた行動の両軸へ展開すると整合性が取れていきます。

「トップランカー(トップランナー)」だけから抽出した行動基準は再現性が低い
「この様に考えてくれたら」「この様に"指示を出さなくても"動いてくれたら」という方々、よく言われるトップランカー(トップランナー)からそのエッセンスを抽出し、表現して評価軸に置くというプロセスが以前からあります。「良い見本・理想の姿」である反面、再現性が低く基準が高くなりすぎる傾向があります。その背景の1つは、トップランカー(トップランナー)は、内発的動機づけで自身をドライブして行くという特徴があります。この様な方へ質問すると「当たり前ですよね?」「誰でもやっていると思っていました」等の反応が返ってきます。
この特徴から、トップランカー(トップランナー)が仰ったことをそのままの表現で展開するのではなく、その要素をさらに具体化と段階的に記載し、トップランカー(トップランナー)に成長するまでのステップにすることで、展開と説明が行いやすくなります。

モチベーションを下げてしまう人事制度の特徴
(1)自分の役割と責任範囲が代わり映えしない
企業によって考え方は多岐にわたりますが、「成果を出すのが先、希望が通るのは後」が大前提になっている企業が多いと言えます。この点は慎重に議論する必要があります。ネガティブに作用すると、自分自身の役割に対してマンネリ感と共に「これ位で仕上げれば良いだろう」との独自の価値観で日々の業務を行う方を増やしてしまう原因になります。
(2)新たな業務と部署が誕生せず、新たな活躍が見えない
経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画と連動して人事制度が運用されることが望ましいのですが、これらが改められても、そこに紐づいた業務、役割、責任が新たに誕生せず、気持ちの中に消化しにくい違和感を持たれてしまうことがあります。
先に業務を創造し、その後に社員をアサインする=新たな役割を担ってもらうことがセオリーです。社員の目線からは、新たな役割と仕事の中身を通して未来を確認することができます。

内発的動機づけにアプローチする
内発的動機づけが起こるきっかけは、興味関心が湧く、挑戦心が芽生える、自己承認できる、所属意識が高まる、クリエイティビティな業務を推進している、これらの内容が挙げられます。
多様性とは、人員不足を解消するために様々な人を雇用することやきれいごとではなく、新たな役割と責任を設計し、仕事として組織に展開し、具体的な行動で未来に向かうことだと言えます。この事実が組織に展開されない限り、本質的な組織の進化がなく、働く社員にとって毎年同じで新年度とは文字だけで、全く新しくない新年度が繰り返されることになってしまいます。
モチベーションを上げることを社員だけに求めるのではなく、新たな役割と責任、それに伴う評価と報酬をミッション・ビジョン・パーパス・理念・経営計画で発信していることに矛盾しないような設計が必要だと言えます。
まずは、経営理念・パーパス・ミッション・ビジョン・中長期経営計画を見直すタイミングに合わせて、ディスカッションを開始することから始めましょう。
関連情報
-
人事コラム人事制度の抜本的改革
-
人事コラム『人事制度構築の失敗事例』人事制度再構築を行うタイミングを見極める
-
人事コラム効果的な人事制度見直しのためのステップ
-
人事コラム人事制度改定の進め方と最適な運用手法
-
人事コラム人事制度の見直しにおける基本的な考え方について
-
人事コラム避けるべき人事制度設計と成功のポイント
-
人事コラム人事制度改革の失敗事例から学ぶ、企業が取るべきアクション
-
人事コラム最新の人事制度トレンド ~人事制度をアップデートし、持続可能な人的資本戦略を推進する~
-
課題解決人事制度完全ガイド~成功事例から最新トレンドまで一挙ご紹介
-
課題解決最近のトレンドのハイブリッド型人事制度とは
-
課題解決業績と連動した成長を支える人事制度構築のポイント
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
マーケティング&マネジメントDXコンサルティング
ゼネラルパートナー浅井 尊行
- 主な実績
-
- 中長期ビジョン策定
- MVV推進体制構築
- 後継体制構築
- 経営幹部育成
- ミドルマネジメント育成
- コミュニケーション チェーン構築
- 中期経営計画×プロモーション×オペレーション施策の合理的設計
- DXビジョン構築
- デジタル戦略マップ構築
- デジタル人材育成計画策定
- 営業DXシフト
- 人事制度再設計
- 人事考課制度再設計
- 考課者訓練
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト