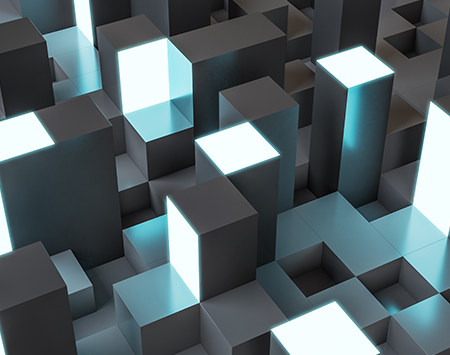人事コラム
戦略人事の視点から考える人事制度運用のポイント
オペレーションだけではない人事制度を最大限活用するポイントとは?
戦略人事の実現に向け、人事制度を正しく運用していくことが
ビジョンの実現に繋がる

戦略人事としての役割発揮の重要性
人事部門の役割として戦略人事が注目されている背景として、企業と社員個人との関係性が変化していることが挙げられる。
製造業を中心に「大量生産・大量消費」という経済システムで発展を遂げた多くの日本企業は、上層部の意思決定を現場の社員に忠実に実行するというトップダウン型の経営スタイルが主流であった。そのため部下が上司から指示を受けるためのコミュニケーションが重視され、上から下りた指示命令をいかに徹底して実行するかという組織文化が一般的であった。
しかし、先行きが不透明な昨今の経営環境下においては必ずしもトップが全ての解決策を示せるわけではない。社員一人ひとりのバックボーンやスキル・経験を尊重し、それぞれが意欲的に仕事に取り組み、階層・役職にかかわらず自律的・自発的に悩み続けることで創造性のある解決策が生み出される。
このように企業と社員の関係性の変化に応じて人事部門の役割についてもアップデートしていく必要があり、複数ある人事機能を円滑に運用していくことを主としたオペレーション人事から、企業戦略や社員一人一人の持てる価値に目を向けて、企業目標の実現を目指していく戦略人事としての役割が求められる。
複数ある人事システムの中でも戦略人事の観点から人事制度(人事フレーム・評価制度・賃金制度)の役割の重要性が高いため、本コラムにおいても人事制度にフォーカスして説明する。

戦略人事の視点から考える人事制度の運用における役割ポイント
戦略人事の役割を踏まえた人事制度の主たる運用ポイントは以下3点である。
1.評価結果の蓄積・分析
評価結果からあるべき評価分布が出ているのか確認いただきたい。
分析の着眼点としては以下の通り。
①評価ランクの出現率
②評価項目別点数×部署別の傾向
③評価項目別点数×等級別の傾向
④評価項目別点数×役職別の傾向
それぞれの分析結果から組織別・等級別・役職別に何が不足しているのかスキル・経験を紐解き、不足に対して対策を検討し、人材価値の向上に繋げていただきたい。
2.評価者に対する運用フォロー
人事評価は給料を決めるための仕組みではなく、半期に一度(もしくは通期に一度)評価を軸に自身の強み(点数が高い項目)と弱み(点数が低い項目)について振り返りを行い、弱みについてはどのように改善していくのかを評価期間に応じてPDCAサイクルを回し人材育成に繋げていくことが目的である。その認識を評価者が持てるように繰り返し、研修を行っていくことが重要となる。
3.人事フレームを軸としたサクセッションプランの作成
人事フレームとは、等級・役職のステップやキャリアの階層感を図に表したものを指す。人事フレームを軸に各階層ごとに何名いるのか、5年後・10年後の組織を踏まえる後任者は適性数いるかなどを把握し、サクセッションプラン(重要ポストの候補者育成)の作成に活かしていただきたい。
さいごに
人的資本経営の注目度が高まる中、人事部門に求められる役割や責任範囲は広がっている。
人事部門の主となる業務は、採用・教育・労務管理・人材管理(人事制度含む)であるが、運用を通じて得られるデータが経営の意思決定・方針の推進において非常に重要な役割を担う。そのため、各種仕組みを運用していく事を前提としたオペレーション人事だけではなく経営戦略の一貫として人事の役割を再定義する必要がある。本コラムにおいては人事制度の運用ポイントを説明したが、企業規模や人事部員のスキル・経験値を踏まえて何から変えていくのか検討することから始めていただきたい。
本事例に関連するサービス
関連動画