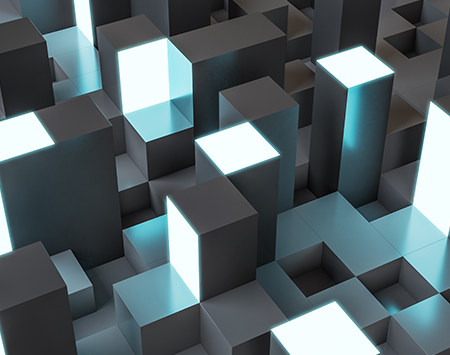人事コラム
最新の人事制度トレンド
~人事制度をアップデートし、持続可能な人的資本戦略を推進する~
最新の人事制度のトレンドを、「等級制度」「評価制度」「賃金制度」「教育制度」の4テーマに分け、事例を挙げながらご紹介
最新の人事制度トレンドをおさえる

【等級制度のトレンド】
(職務型へのシフト)
従来の日本企業では、年功序列や職能資格制度が主流であった。
しかし、近年では「職務型等級制度(=ジョブ型人事制度)」への移行が進んでいる。
職務型等級制度とは、社員の職務内容や責任範囲に基づいて等級を決定する仕組みであり、欧米企業で広く採用されている。
背景には、ジョブ型雇用の普及がある。厚生労働省の「令和4年雇用動向調査」によれば、ジョブ型雇用を導入している企業の割合は前年よりも約15%増加しており、特に大企業での導入が顕著である。
例えば、富士通は2020年にジョブ型雇用を全面的に導入し、職務内容を明確化することで、社員のキャリア形成を支援するとともに、グローバルな人材競争力を高めている。
職務型等級制度の導入は、透明性の向上や公平性の確保につながる一方で、職務内容の定義や運用の難しさが課題となる。
そのため、導入にあたっては、職務分析や職務記述書の作成など、慎重な準備が求められる。

【評価制度のトレンド】
(リアルタイムフィードバックの活用)
評価制度においては、年1回または2回の定期的な評価から、リアルタイムフィードバックを重視する流れが加速している。
これは、社員のパフォーマンスをタイムリーに把握し、迅速に改善点を共有することで、組織全体の生産性を向上させる狙いがある。
GoogleやNetflixなどの先進企業では、従来の評価制度に代わり、OKR(Objectives and Key Results)や1on1ミーティングを活用したリアルタイムフィードバックを導入している。
これにより、社員が目標に向けて主体的に行動しやすくなり、エンゲージメントの向上が期待される。
また、AIやデータ分析を活用した評価制度も注目されている。
例えば、ソフトバンクはAIを活用して社員の業績データを分析し、評価の客観性を高めている。
これにより、評価のバイアスを排除し、公平性を確保することが可能となる。

【賃金制度のトレンド】
(初任給の上昇と若手社員の賃金調整)
賃金制度においては、新入社員の初任給の上昇が大きなトピックとなっている。
経済産業省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によれば、2023年の大卒初任給の平均は約22万円で、前年よりも3%増加している。
これは、物価上昇や人材獲得競争の激化を背景に、企業が優秀な人材を確保するために初任給を引き上げていることが要因である。
しかし、初任給の上昇は既存の若手社員との賃金格差を生むリスクがある。例えば、2022年に初任給が20万円だった社員が、2023年入社の新入社員よりも低い給与水準にある場合、不公平感が生じる可能性がある。
このような状況を放置すると、既存社員のモチベーション低下や離職につながる恐れがある。そのため、多くの企業では、既存社員の賃金調整を行う動きが見られる。
例えば、ユニクロを運営するファーストリテイリングは、2025年3月に「グローバル水準での競争力と成長力の強化」を方針に掲げ、新入社員の初任給を現行の30万円から33万円に引き上げ、年収では約10%増の500万円強とする大幅な初任給改定を実施した。入社1~2年目で就任する新人店長の月収については39万円から41万円に引き上げ、年収では約5%増の約730万円としている。初任給だけで無く、全社における報酬体系も一新し、本部/営業の正社員は、年収が最大で11%アップ。加えて、個々の抜擢や要職への登用によっては、最大で54%もの賃上げを実施している。
これにより、初任給の上昇に伴う不公平感を解消するとともに、全社員のエンゲージメント向上を図っている。

【教育制度のトレンド】
(リスキリングとDX人材育成)
教育制度においては、リスキリング(再教育)とDX人材の育成が重要なテーマとなっている。
経済産業省の「未来人材ビジョン」によれば、2030年までに日本では約450万人のデジタル人材が不足すると予測されており、企業はこの課題に対応するために社員のスキルアップを支援する必要がある。
リスキリングの具体例として、日立製作所は「日立アカデミー」という社内教育プログラムを通じて、社員にAIやデータサイエンスのスキルを習得させている。
また、三菱UFJ銀行は、全社員を対象にデジタルスキルの基礎教育を実施し、DX推進に向けた組織全体の底上げを図っている。
さらに、オンライン学習プラットフォームの活用も広がっている。
UdemyやCourseraなどの外部サービスを利用することで、社員が自分のペースで学習できる環境を整備する企業が増えている。
これにより、社員の自己成長を促進し、企業全体の競争力を高めることが可能となる。
まとめ
最新の人事制度トレンドを見てみると、等級制度では職務型へのシフト、評価制度ではリアルタイムフィードバックの活用、賃金制度では初任給の上昇と既存社員の賃金調整、教育制度ではリスキリングとDX人材育成が注目されていることが分かる。
これらのトレンドは、企業が変化する社会環境に適応し、持続的な成長を実現するために不可欠な要素である。
しかし、これらの制度を導入する際には、企業の実情や社員のニーズを十分に考慮することが重要である。
人事制度の設計や運用においては、透明性や公平性を確保し、社員の納得感を得ることが成功の鍵となる。
企業はこれらのトレンドを積極的に取り入れつつ、自社に最適な人事制度を構築していくことが求められる。
本事例に関連するサービス
関連動画