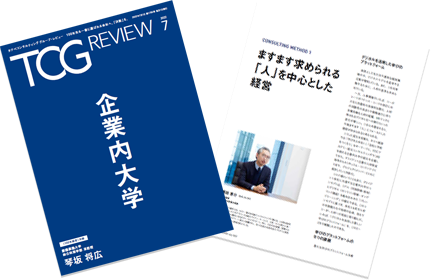時代に合わせた教育体系を構築する5つのステップ

はじめに
人的資本経営の高まりから、社員の教育体系を見直しを検討する企業が増えている。
背景として、労働力人口の減少に伴い人材の早期戦力化や中堅・ベテラン社員の能力開発、多様な働き方に合わせた学ばせ方など、従来の教育体系と近年の働き方の変化に不具合が生じていることなどが挙げられる。
教育体系の見直しが進む中で、本コラムでは近年導入が増えている「ブレンディッドラーニング」について紹介したい。
ブレンディッドラーニングとは
ブレンディッドラーニングとは様々な研修方法を混ぜ合わせた(ブレンドした)学習方法である。
以前より情報通信技術の進化に伴い、注目されていた学習方法ではあるが、コロナを機に急速に導入する企業が増えている。
例えば、Webを使用したe-learningなどの対面と非対面を組み合わせた学習方法がある。
他にも、対面研修の中に一部映像や音楽・SNSコンテンツを組み合わせた「メディアミックス」や年次や能力、性格など参加者の傾向を考慮してブレンドする「ラーナーミックス」、講義とロールプレイングやグループディスカッション、アンケート投票を組み合わせた「アクティビティミックス」などがある。

ブレンディッドラーニングのメリット
先ほど紹介した学び方を混ぜ合わせることのメリットについて3点紹介したい。
(1)視覚情報により学習効果を高め、予習・復習に活用できる【メディアミックス】
映像などを用いることにより、視覚や聴覚にアプローチが可能となり学習効果を高めることができる。
また参考動画を予習として活用することや、講義映像をアーカイブとして展開することで復習にも役立てることができる。
(2)参加者のバックグラウンドによるバラつきを減らし、学習効果を高める【ラーナーミックス】
グループワークなどの研修では年次や経験・知識によってバラつきが生じやすいが、バックグラウンドを考慮することで、グループ間による偏りを減らすことができる。
そのためそれぞれの特性や、レベルを合わせてグループワークに取り組むことができる。
(3)参加者の主体的な研修参加を促し、アウトプットを高める【アクティビティミックス】
講師による一方通行の講義ではなく、ロールプレイングやグループワークにより、学んだ事をアウトプットする機会や、参加者同士の意見交換を通して思考の整理、意見の深堀に繋げることができる。
ブレンディッドラーニングの導入ステップ
ブレンディッドラーニングを導入する際には、以下の5つのステップでカリキュラムを検討していただきたい。
(1)現状認識
まず、わが社の現状を定性・定量的に正しく把握することが求められる。
定性的に状況を把握する方法として、現場社員(管理職・一般職)へのインタビューがある。
インタビューの際は、評価や能力で偏りがないよう幅広く意見を収集することを意識していただきたい。
また、定量的な収集方法として、アセスメントツールがある。全社員を対象に広く意見を収集することで階層や年次、部署ごとに傾向を把握することができる。
(2)目標設定
目標設定では経営理念や役割要件などから、階層ごとに社員に求める「あるべき姿」を具体的に設定し、研修ごとに目標設定することが重要である。
現状の課題解決のために研修を実施するのではなく、あるべき姿から逆算して何を習得させるのかを設定する。
(3)カリキュラムの設計
目標を達成するためにどのように学ばせるかを設計する。
対面で伝える内容とオンラインなどで学ばせる内容を明確にし、それぞれのメリットを最大限活かせるよう設計することが望ましい。
(4)グループワークの検討
研修で学ぶだけでなく、理解度の確認やアウトプットの機会としてグループワークを検討する。
オンラインを活用することでWeb参加でもグループワークは可能であり、グループ間の交流や意見交換による研修効果の向上を目指していただきたい。
(5)継続なフォローとフィードバック
オンラインを活用することで、復習や進捗管理など継続的なフォローが可能である。
研修直後であれば意欲も高いが、時間の経過とともに研修効果は薄れていく。
そのため、Webを通して進捗管理やフィードバックに活用することで継続してフォローすることが重要である。

ブレンディッドラーニングの活用事例
ブレンディッドラーニングを活用した事例として以下3点を紹介する。
(1)予習動画としての活用
予習動画として活用するメリットとして、参加者の知識レベルを統一することができる。
また、研修のポイントを事前に理解させることで目的意識を持って参加させることができる。
(2)OJTの補足動画としての活用
OJTでは上司・先輩によって教え方に差が出ることや、教えることに時間が割かれ、作業効率の低下が懸念される。また1回で正確に覚えることも難しい可能性がある。
オンラインを活用することで、分からないことを反復学習することが可能であり、隙間時間を使って理解度を高めることができる。
また、教える側の時間削減や教える内容を均一化することができ負担軽減にもつなげることができる。
(3)継続学習ツールとしての活用
研修の動画のメリットとしてノウハウを蓄積することが可能である。
動画であれば、復習だけでなく入社した社員の教育ツールとしての活用や過去の成功事例なども残すことが可能である。
まとめ
社員の働き方や考え方が変われば、教育体系も時代とともに変化することが求められる。
ブレンディッドラーニングを活用することで社員の学習効果を高めるだけでなく時間削減・継続フォローなどあるべき姿に向けて効率的に学習させることが可能である。
教育体系を構築・研修を実施して終わりではなく、あるべき姿と現状を比較しながら年に一度は教育体系を見直す機会を設けていただきたい。
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフコンサルタント柴田 貴也
- 主な実績
-
- 金属商社:人事制度再構築支援
- 物流業:人事制度再構築支援
- コールセンター:人事制度再構築支援
- 金型製造業:事業再生支援
- 化粧品製造業:執行役員制度構築支援 など

 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト