人事コラム
社員研修を動画化するメリットとは
社員のスキルを効率的に向上させるポイント

現代の企業環境における社員研修の重要性
タナベコンサルティングでは、企業の未来を見据える方法として、期間ごとに異なる視点を用いている。1年後を見るには、決算書。5年後は、商品やサービス。つまり、商品やサービスがお客様や市場にどれほど受け入れられるかで判断する。しかし、10年後の予測となると、顧客のニーズや市場の変動を見通すのは非常に難しい。
10年後は「人」である。企業で働く人材によって生まれる差が、将来に大きな影響を及ぼす。したがって、人材をどのように育成し、その人材を基にどのような事業を展開するかが重要である。人材育成は極めて大きなテーマといえる。
私がお手伝いさせていただいているクライアント企業はここ数年非常に順調である。社長は、上述のポイントを理解し順調な間に10年後を見据え、「人材開発体系」を構築し、運用を始めた。しかし、その社長はよく「もっと早く、せめて5年前に人材育成に力を入れていれば、会社はさらに成長していた」と仰っている。必要性は感じていたが、なかなか手を付けられなかったとのことだ。
人材育成をしなくても、本業が順調であれば数年は潰れないし、やったところで1,2年で個人が激変することがあっても、企業全体が劇的に変化することは少ない。そのため後回しになりがちだが、肝心なのは気づいたときに始めることである。これが未来の発展につながる。
動画研修のトレンドとその背景
近年、企業研修の現場では、従来の対面型研修に加え、動画研修コンテンツを導入するケースが増えている。その背景には、若年層を中心に「動画で情報を得ること」が当たり前になっている現状がある。
GO TO MARKETが実施した「Web検索サービスに関するアンケート調査」(2022年12月)によると、15歳~29歳の若年層では、Googleに次いでYouTubeが検索エンジンとして利用されている。30代以上ではYahoo!検索が2位であることとは対照的な結果である。
こうした状況を踏まえ、社内マニュアルを従来のテキスト形式から動画形式へ移行する企業も増加している。アメリカの調査会社Forrester ResearchのJames L. McQuivey博士の研究によると、「1分の動画は、文字換算で180万語、Webページ換算で約3,600ページ分の情報量に相当する」という。動画は情報伝達の効率性という点でも、研修手段として非常に有効なのである。
トレンド・学びの効率化を踏まえると、動画を活用した研修は益々広がっていくと考えられる。

動画研修のメリット
動画研修のメリットは多くあるが、ここでは3点紹介したい。
1. 理解度・記憶率の向上
動画研修は、上記でも述べたがテキスト学習と比べて、視覚と聴覚の両方を使って情報を得られるため、理解度が格段に向上する。さらに、「いつでも、何度でも見返せる」という点が最大のメリットと言える。有名なエビングハウスの忘却曲線では人間の脳は1度覚えたことを、1時間後には半分忘れ、1日後には7割忘れ、1か月後には8割忘れていると言われている。忘れないために重要なことは繰り返し学習することである。動画であれば、重要なポイントを繰り返し確認することができる。復習しやすい環境を作ることで、記憶の定着を促進し、学習効果を最大化することが可能となる。
2. 場所と指導者の制約からの解放
従来のOJT研修では、指導者から直接指導を受けるために、時間と場所の制約があった。しかし、動画研修であれば、場所を選ばずに、好きな時間に学習することができる。
また、「指導者に質問しづらい」「指導者の時間を拘束してしまう」といったOJTにおける課題も、動画研修であれば解消できる。学ぶ側の心理的ハードルを下げ、学習意欲の向上に繋げることができる点も大きなメリットと言えるだろう。
3.学習内容の統一
指導者によって教え方が異なってしまうというOJT研修の課題も、動画研修であれば解決できる。全社員が同じ内容を、同じレベルで学習できるため、作業の標準化、品質の均一化を実現することができる。このことは企業のブランディングにも大きく寄与する。私が支援しているクライアント企業でも、動画研修導入によって、工場ごとのバラつきが解消され、より安全で効率的な作業体制を確立することができた。
動画研修導入のステップ
理念に基づいた人事制度や教育システムがすでに構築されている企業を前提に、動画研修導入をスムーズに進めるための5つのステップを紹介する。
1. モデル部署の選定:成功体験を生み出す
最初から全社展開を目指すのではなく、まずは成功体験を生み出すことが重要である。意識の高いリーダーやメンバーが多く、業務の統一効果が見込める部署を2~3つ選定し、モデルケースとして動画研修を導入するのが良いだろう。
2. 技術の棚卸し:可視化で「暗黙知」を「形式知」へ
既存のスキルマップや星取表を活用するか、なければ日々の業務を洗い出し、可視化していく。
業務の細分化:例えば、「カレーの作り方」という業務を、「食材準備」「炒める」「野菜を加える」「煮込む」「ルーを加える」「味の調整」といったように、具体的な作業レベルまで細かく分解する。
ポイントの整理:各作業におけるコツや注意点などを明確化する。例えば、「食材準備」であれば、「玉ねぎは繊維に沿って切る」「人参は乱切りにする」といった具合である。
重要なのは、これまで「当たり前」に行われてきた暗黙知を、誰でも理解できる形式知として記録することである。
3. 動画作成:現場の「匠の技」を記録する
各作業工程において最も熟練した社員に、実際に作業をしながら解説してもらう様子を撮影する。動画作成自体は、若手社員に任せることをおすすめする。編集作業を通して、ベテラン社員に質問をすることでコミュニケーションの機会が生まれる。そのことにより技術伝承もさることながら、チーム全体の雰囲気がとても良くなることが多い。
4. 活用方法の策定:学習しやすい環境を構築
動画を作成したら終わりではなく、実際に活用されて初めて意味を持つ。教育クラウドや共有フォルダなどを活用し、社員がいつでもどこでもアクセスしやすい環境を整備する。さらに、学習のタイミング(例:入社時研修、等級昇格時など)を明確化することで、計画的な人材育成を促進できる。
5. 全社展開:成功モデルを横展開
モデル部署で軌道に乗ってきたら、そのノウハウを全社に展開していく。

動画研修を成功に導くポイント
動画研修の導入を決定しても、いざ運用を始めるとなると「なかなか動画が増えない」「社員のモチベーションが上がらない」といった壁にぶつかるケースが多い。効果的な動画研修システムを構築するには、プロジェクト運用を適切に行うことが不可欠である。ここでは動画研修を成功に導くためのプロジェクト運用のポイントを3つ紹介する。
1. 完璧主義の打破:まずは作ってみる
動画作成においては、「まずは作ってみる」という姿勢が何よりも重要である。最初から完璧な動画を目指そうとすると、ハードルが高くなり、なかなか制作が進まない。多少クオリティが低くても、まずは形にすることを優先し、数をこなしていく中で改善を図っていけばよい。
重要なのは、モデル部署のモチベーションを維持することである。初期段階での過度なダメ出しは、モチベーション低下に繋がりかねないため注意が必要である。
2. モチベーション向上:適切な報奨制度の導入
動画作成は、決して容易な作業ではない。社員のモチベーションを維持するためには、適切な報奨制度を導入することが効果的である。
例えば、動画作成を事前申請制とし、承認された動画に対して報奨金を支給する方法などが考えられる。金額設定は企業によって異なるが、相場としては1本あたり500円~5,000円程度である。500円では効果が薄く、5,000円の会社では急速に動画数が増加した。
金銭的な報酬だけでなく、人事評価制度に動画作成実績を反映させる方法も有効的である。具体的な評価項目を設け、評価ポイントに加算することで、社員のモチベーション向上を図ることができる。
3. ナレッジ共有:動画作成のマニュアル化
モデル部署での成功事例を基に、動画作成のマニュアルを作成しておくことも重要である。動画作成に慣れていない部署でも、実際に社内で作成されたマニュアルであれば、抵抗感なく参考にすることができる。
全社展開をスムーズに進めるためにも、モデル部署は動画作成のノウハウを積極的に共有していくべきである。
さいごに
動画研修には、多くのメリットがあり、人材の成長を力強く後押しするものである。特に、若年層にとって、動画は最も身近な情報収集手段となっており、学習効果の向上や、効率的な人材育成に大きく貢献すると言える。
本稿では、動画研修のメリットから導入ステップ、そして成功に導くためのポイントについて解説した。重要なのは、完璧を求めすぎることなく、まずは小さく始めてみることである。成功体験を積み重ねながら、自社にとって最適な動画研修システムを構築していくべきである。10年後を見据えた人材育成は、企業の未来を左右する重要な投資である。動画研修という新たな武器を手に、力強い未来を切り拓いていこう。
本事例に関連するサービス

企業内大学(アカデミー)
設立コンサルティング
「学び方」を変えることで「働き方」が変わり、 更に魅力ある企業へと進化させます。企業内大学の設立により、人材成長の仕組みを構築します。
企業内大学(アカデミー)設立コンサルティングの詳細はこちら
関連動画
関連情報
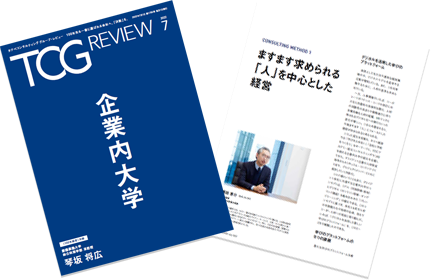
TCG REVIEW 企業内大学
持続的成長の基盤となる、デジタルとリアルを融合させた総合的な学習・育成システム「FCCアカデミー(企業内大学)」の設立・運営メソッドを提言し、社員の成長を自社の発展につなげるモデル事例を紹介します。
この資料をダウンロードする


