人事コラム
組織・人事分析とは?
~制度再構築の前に行うべきステップ~
機能するための制度構築は、正しい現状分析から
現状分析の正しい進め方を理解し、
制度構築のポイントを押さえる

組織・人事の現状分析の進め方
現状分析とは、現状を正しく把握し、特性や課題を理解することを言う。
組織・人事領域においては、主に組織構造や人事制度、教育制度、採用手法などが分析の対象とされ、分析手法は主に2つである。
1つ目は、関連資料や実績から分析をはかる「データ分析」である。
関連資料からは、どのような設計であり、どのような運用上のルールを設けているか、実績データからは、現実としてどのような現象が発生しているか、設計と実態の乖離はどこに生じているかなどの確認を中心に分析を実施する。
2つ目は、アンケートやインタビューから分析をはかる「ヒアリング分析」である。
設計とは別に、実際の運用上ではどのような状態となっているのか、運用する側・される側におけるギャップが何かなどの確認を中心に分析を実施する。
なお、分析を進める上では、最初にデータ分析を実施して事実を押さえ、その事実の要因を探るべく要点を絞ってヒアリング分析を実行することが効果的である。

組織・人事現状分析の課題の把握・情報収集
分析・調査を進める上で、何が課題であるかを把握することは重要であるが、この「課題」という言葉を誤って解釈される方が多い。
「課題」の定義は、「目指す姿」と「現状」のギャップ(差)であり、"解決できるもの"である。
つまり、単に数字が悪い、制度がないということがすなわち「課題」ではなく、比較対象は自社における「目指す姿」と比較して、そのギャップがどこに、どのように、どの程度発生しているかを把握することに着目しなければならない。
一方、自社の「目指す姿」も時代とともに変化するものである。自社の経営理念、業界を取り巻く環境を改めて捉えた時、思い描く「目指す姿」が我々の存在価値を高めていくために正しい姿なのかも、定期的に確認され、必要に応じたアップデートがされているか、またその姿が社員全員理解できるように周知されているかも確認すべき点である。
以上のことから、現状分析における課題の把握は、自社の「目指す姿」と比較した課題を把握することが必要であることに加え、自社の目指す姿にも課題がないかを把握するため、同業界や取り巻く外部環境の情報まで収集し、現状・目指す姿、業界データの3点を比較して課題を明確にしていくことが必要である。

組織・人事の現状分析の種類
事業(ビジネスモデル)や自社の強み・弱みを認識するためのフレームワークとして、SWOT分析や4P分析、3C分析などあるが、組織・人事領域における分析では、以下のような分析を実施することが有効である。
1. マネジメントシステム分析
戦略に応じた組織体制、経営の管理システムが整備されているかを分析
(1)経営の上位概念が中期経営計画→単年度計画→部門方針→個人目標へとブレイクダウンされ、個人の行動にまで落とし込まれている仕組みが構築されているか
(2)組織体制は中期的に取り組むべき重点実施事項を行っていくために適した機能、ユニット分けができているか
(3)組織内の情報共有を円滑に行う仕組みが整っているか
2. 人材構成分析
人員構成の特性を確認する分析
(1)年齢・勤続年数別・階層別の人員構成に偏りが生じていないか
(2)組織別の管理者比率に偏りが生じていないか
(3)入職・退職者の推移に異常が生じていないか
3. 人事制度分析
人事制度が自社の目指す姿を実現する人材の育成基盤として機能しているかを分析
(1)階級制度における各階層の役割や求められる姿が明確となっているか
(2)成長段階に求められる成果・能力・行動・姿勢に紐づいた評価項目が設定されているか
(3)評価の運用(評価基準の統一、評価調整の実施、評価者の定期教育)が適正に実施されているか
(4)賃金水準は同業界と比較して低くなっていないか
(5)評価制度の結果が、賃金の昇給や賞与などと連動する仕組みとなっているか

組織・人事の現状分析からの制度構築の進め方
正しい現状認識ができれば、必要に応じてその結果を活用した制度構築を実践していくことが望ましい。
制度構築を実施していくとなれば以下の手順で進めると、一貫性ある制度を構築することができる。
※以下は人事制度再構築に関する一連の設計プロセスである。
1. 目的の再認識と改善の方向性の検討
「今なぜ、制度を構築する必要があるのか」ということに対する改定目的や改定の成果目標を検討する。
2. 人事ポリシーの構築
自社の求める姿へ成長するために、「どのような人材を、そのように育成していくか」を明文化して制度の骨子を構築する。
なお、更に透明度を高くするためには、「どのような人物を評価するか」、「どのように報酬分配するか」まで示すことが望ましい。
3. 階級制度の整備、および階級要件の再定義
求める人材を育てるステップを再設計するとともに、各ステップにおける求められる姿を明文化する。
4. 評価制度の再構築
求められる役割が果たせているかだけではなく、自身の強みや課題が理解でき、継続して成長を促すことができる仕組みの構築と形骸化しない運用体制を整備する。
5. 賃金制度の再構築
報酬分配思想に応じた賃金支給項目の設計と階層別の賃金水準の設計、評価結果と連動する昇給や賞与分配の仕組みを構築する。
なお、制度構築には概ね1年程度の期間を要することが一般的である。短期間で作り上げるケースもあるが、結果的に議論不十分の結果、早い段階での制度修正や再検討が必要になる。
制度構築は会社の"未来づくり"であることも併せて理解し、十分な議論の上、目的を達成させるための制度構築に取り組んでいただきたい。
本事例に関連するサービス

組織・人事制度診断コンサルティング
部分的改修ではない、人事戦略・経営戦略と連動した人事制度構築・人事施策のために健康診断(現状認識)を通じて、課題の改善具体策およびプライオリティ(優先度順位)を明確にします。
組織・人事制度診断コンサルティングの詳細はこちら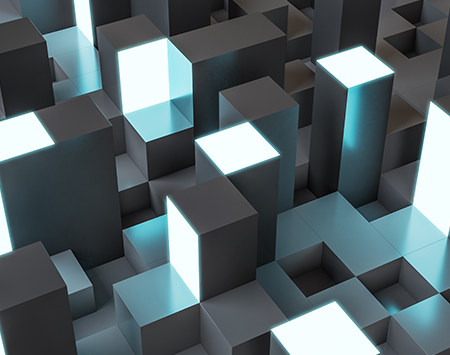
関連動画
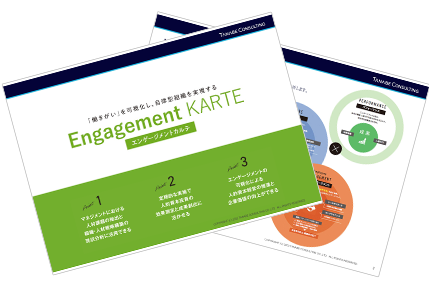
エンゲージメントカルテ(エンゲージメントサーベイ)サービス概要資料
Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)で、エンゲージメントを定期的に計測し、目指す指標とのギャップをどのように解決するのかを検討する必要があります。自立・自走する組織実現に向けた人的資本経営の取り組みに向けたベースとしてご活用ください。
この資料をダウンロードする

