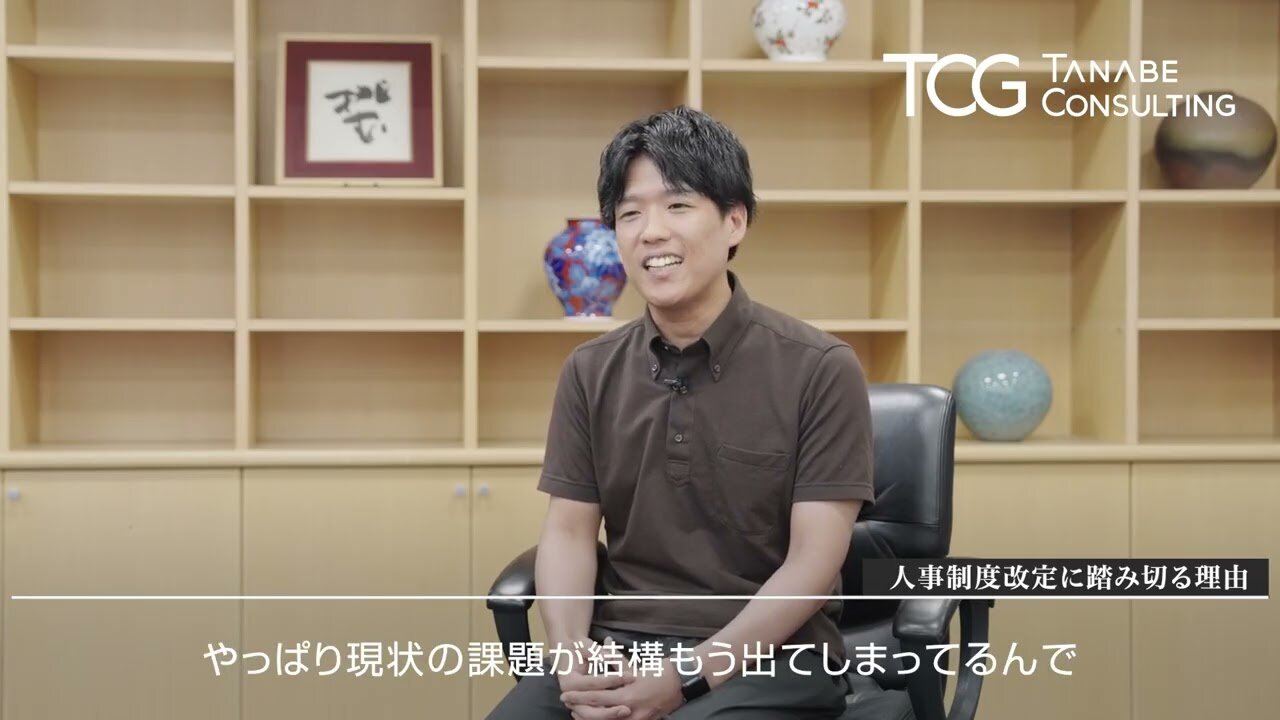人事コラム
社員が育つフィードバック面談とは?
~成長につなげるフィードバック面談の進め方とポイント~

フィードバック面談とは
フィードバック面談とは、評価者(上司)が被評価者(部下)に評価結果とその根拠を伝え、今後の課題や行動計画を話し合う面談のことを指す。タナベコンサルティングでは、フィードバック面談を「人材育成の土台(プラットフォーム)」と表現し、部下育成において欠かすことのできないベース部分と考えている。パーソル総合研究所「人事評価と目標管理に関する定量調査」によると、約70%の企業がこの面談実施を制度化しており、多くの企業で、一般的になっている。一方で、同調査によると、面談での納得感・満足度は低調であり、課題が散見しているとある。これだけ広まった仕組みであり、上司・部下ともに一定の経験をしているはずだが、上手く機能していない。その原因はどこにあるのか。
これには、様々な原因が考えられるが、大きくは3点だと推察している。
1.会社として、フィードバック面談の「進め方の体系化」がなされていない
2.上司(評価者)・部下(被評価者)両方への教育が実施できていない
3.現場において、査定通知の機会という認識に留まっている
(認識の擦り合わせ不足・次なる目標設定に繋げられていない)
上記を踏まえ、本コラムでは、フィードバック面談で部下の納得感を高め、成長に繋げていくために必要な考え方とステップをお伝えする。
お伝えする内容はあくまでベースとなるものであり、必要に応じて、それぞれの会社でアレンジを加え、自社ならではの仕組みにアップデートいただきたい。

フィードバック面談の進め方とポイント
この章では、1.当日までの流れ 2.当日の流れ の2点に分けて、お伝えする。
1.当日までの流れ
フィードバック面談を良いものにできるかどうかは、事前準備で決まる。何をすべきかと言えば、後述する当日の面談の各ステップを実施するための「質問」の準備である。何を「話すか」を準備する評価者は多いが、フィードバック面談は、相互の認識合わせの場であり、話の主体は被評価者だと認識すべきである。もちろん、こちらからの期待値や伝えるべきことの準備は前提であるが、その内容を伝えるのは被評価者が自身の考えを発信した後であり、いかにその発信を促すかが重要である。そのためには、情報収集や事実の整理を行い、「質問」を準備した上で、当日のシミュレーションをし、面談に臨みたい。
2.当日の流れ
当日は、限られた時間の中(一般的には30分~1時間程度が目安)で、以下のステップを踏み、話を展開すると良い。
STEP1:アイスブレイク
<ポイント>普段見知った関係でも、被評価者は身構えているものである。凍った氷を溶かすように、場を和ませ、肩肘張らない空気感を作る。業務と関係のない話題でも構わないので、場をほぐすことを最優先とする。
↓
STEP2:面談の目的を発信
<ポイント>なぜこの場があるのかを上司(評価者)から伝える。面談を有意義に進めるために、お互いが同じ目線となるよう認識を一致させる。結果の通知だけでなく、その結果も踏まえつつ、「今後どのような成長曲線を描いていくのか」を認識合わせする場であることを明確に伝える必要がある。
↓
STEP3:評価の通知・説明
<ポイント>評価結果の通知後、結果に対し、何がどう良かったのか、不足していたのかを明確にする。この際には、評価基準(着眼点)を軸に、評価期間の具体的行動を根拠とした内容を伝えていく。
↓
STEP4:未来志向のフィードバック(認識合わせ含む)
<ポイント>STEP3で伝えた内容について、本人の認識や考えを引き出し、認識合わせをしていく。特に、本人の自己評価(もしくは認識)と上司評価にギャップのある項目について、認識している基準の一致を図る。その上で、部下(被評価者)の役割要件や評価項目と照らし合わせ、成長のためにはどのような方向性が良いかを擦り合わせる。
↓
STEP5:今後の取り組み事項の目線合わせ
<ポイント>STEP4で擦り合わせた方向性を踏まえ、次の評価期間において、何をどこまで実施し、どのレベルまで到達するかを決める。その際には、部下の口から自発的に取り組むことが言えるよう促すことが重要である。上司はその内容を尊重し、アドバイスやサポートすることを伝えるべきである。
この5つのステップは全評価者共通のものとし、他に自社として対話すべきテーマがあれば、アレンジを加えると良い。いずれにしても、各ステップにおいて、どのような質問をするか、どのような展開で話を進めていくのか、当日までの準備が肝要であることを改めて認識いただきたい。

企業におけるフィードバック面談の事例
前章でお伝えしたようなフィードバック面談のノウハウを会社全体として体系化(ルール化)し、全評価者が現場で漏れなく実践することが重要である。これが、評価に対する被評価者の納得度を向上させ、社員が育つ風土を醸成していくからである。ここで、フィードバック面談において、全社での取り組みで、成果を高めている会社を2社ご紹介する。
1.週1のフィードバック面談を全社員が実践する事例
大阪府に本社を構える某企業では、毎週の特定曜日が全社員面談の日と決めている。年間・月次・週次での目標を予め決め(目標設定内容は、全員の内容を全社員が閲覧できるようになっている)、該当期間が過ぎると指定の振り返りフォーマットに被評価者(部下)が記入し、毎週の面談に臨む。面談で対話したことは、人事システムに評価者(上司)が入力し、決めたことが記録され、また次回の面談で振り返りを行っている。これだけ短スパンでの面談を即実践することは難易度が高いが、目標設定→実践→振り返り→次行動設定のサイクルを確実に実践していける仕組みに落とし込めている好事例である。実践とともに、その実践を可視化できる形が理想である。
2.人事制度改定を機に、評価者・被評価者全員の研修参加
兵庫県に本社を構える某企業では、全社員参加型で研修を実施している。評価者に対し、繰り返し実施をすることはもちろんであるが、被評価者にも定期的に実施をしている。内容は、評価制度の理解促進・評価リテラシーの向上・自己評価における認識合わせが主である。評価制度を効果的にするためには、被評価者側も正しい認識を持ち、評価結果を主体的に自身の成長に活かす姿勢が必要である。同社では繰り返し実施をすることで、徐々に評価への納得度が高まっており、人を育てることに関心の高い組織になっていることを実感されている。業務の手を止めることになる部分は避けられないが、会社として得るものも多く、皆さんの会社でも少しずつできることから始めていただきたい。
さいごに
これまで捉えていたフィードバック面談への認識と比較していかがだっただろうか。コンサルティング現場において、ルールはあるものの、実践ができていないというケースが大半を占めている。会社として、なぜフィードバックという機会があるのかを評価者に正しく伝えられていないことに起因していると感じている。ルールの発信のみで、実施状況は現場任せ、現場は評価結果を伝えることに終始し、できるだけ短時間で済まそうとしている現場実態も多くあるのではないだろうか。この結果が、冒頭にお伝えした納得度の低調さを生んでいると推察する。
納得度の前提には、被評価者(部下)が思い描くキャリアを把握した上で、そのために必要な方向性を対話することにある。上司からの期待値も伝えながら、次の評価期間をどのように行動していくのかを決め、その動機付けを行っていく。フィードバック面談は評価期間終了後のみ実施するものではなく、普段の立ち話による短時間の対話もフィードバック面談である。各社において、上司が親身になって部下の声に耳を傾け続け、どのように社員の成長に向き合うのか。本コラムでご紹介したポイントをベースに、各社に合った社員の成長に寄り添う仕組みを検討いただきたい。