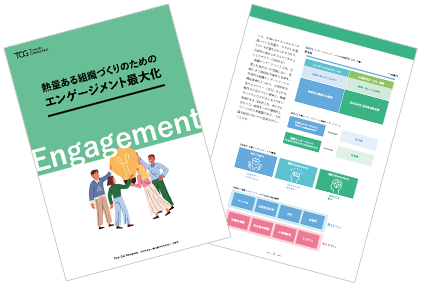人事コラム
エンゲージメントが低い原因と向上のための効果的アプローチ方法を解説
~効果的なアプローチと取るべきアクション~

エンゲージメントとは
はじめに、エンゲージメントとは、婚約・約束・契約・誓約といった意味合いを持つ単語である。
一方、人事の世界におけるエンゲージメントとは、「組織(企業)と個人(社員)のつながりの中で育まれる自発的な関係性」を指し、一般的には社員の持つ会社に対する愛着心や思い入れと説明される。
特に、代表的なエンゲージメントとしては、社員の仕事そのものに対する心理状態を表す「仕事エンゲージメント」と、会社や組織に対する心理状態を表す「組織エンゲージメント」の2つに分けることができる。
(1)仕事エンゲージメント
「仕事と社員との関係性」を指し、働きがい(やりがい)を表す指標である。
モチベーション、レジリエンス(精神的回復力)、ウェルネス(身体的・精神的健康)などがこれに当たる。
(2)組織エンゲージメント
「組織と社員との関係性」を指し、働きやすさを見る指標である。心理的安全性、人事諸制度の充実度、金銭的・非金銭的な報酬などがこれに当たる。
まずは、エンゲージメントの定義を整理させていただいた上で、本コラムでは、組織におけるエンゲージメントが低い要因とその対策について、お伝えしたい。

エンゲージメントが低い要因
アメリカの調査会社・ギャラップ社の2022年の調査によれば、日本企業に属する社員のうち、熱意にあふれる社員の割合は全体の5%にとどまり、調査を始めてから4年連続で過去最低の記録となっている。
では、なぜ日本企業はエンゲージメント指数が低いのであろうか。
結論としては、組織に属する社員一人ひとりの持ち味や特徴を発揮できていないことだと筆者は考える。
具体的な要因に関して、エンゲージメント区分の切り口から見てみる。
(1)仕事エンゲージメント(働きがい)
①働く意義や目的意識の欠如
自身の役割や貢献が全体の目標や成果にどのように影響するのかが理解できていない
②成長機会の欠如
日々の業務を通じたキャリアアップや自己成長の機会が設けられていない
(2)組織エンゲージメント(働きやすさ)
①コミュニケーションの欠如
組織内における仲間意識や一体感に欠けており、社員同士や上司とのコミュニケーションが取れていない
②人事評価の不公平さ
業務実績や仕事への取り組みを正当に評価・処遇されていない
③ワークライフバランスの欠如
長時間労働および不規則な勤務によってプライベートの時間が圧迫されている

エンゲージメント向上のためのアプローチ
では、どのようにしてエンゲージメントを高めていくべきか。
具体的なアプローチ方法としては、以下のステップに則り対策をしていく必要がある。
【ステップ①:エンゲージメント指数を図る】
はじめに、エンゲージメントの現状を正確に理解し、課題や改善点を特定することが重要である。
具体的には、エンゲージメントサーベイの実施、データ分析( 生産性・離職率 等)や1on1の実施があげられる。
【ステップ②:明確な目標設定】
現状の問題点を押さえた上で、組織として目指すべき姿を明確にする必要がある。
ここで言う目指すべき姿は、具体的なエンゲージメント指数を「いつまでに、どの程度」向上させていくかを指す。
【ステップ③:アクションプランの策定】
エンゲージメント指数の目標に基づき、具体的な施策を設計する。
まずは、大枠のテーマを決めることから始める。
例えば、仕事エンゲージメント:成長機会の創出/組織エンゲージメント:フィードバック文化の醸成 等である。
次に、テーマ別のプロジェクトチームの設置とチーム内で役割分担を行う。
ここで重要な点は、メンバーの役割と責任を明確にすることと「誰が・いつまでに・何を・どうするか」を明確にすることである。
【ステップ④:モニタリングの実施・行動施策の見直し】
アクションプラン策定後は、定期的に行動施策を振り返ることが重要である。
加えて、ステップ①の現状分析段階で実施したエンゲージサーベイの再実施やKPIのモニタリング( 生産性、離職率 等)を通じて、ステップ③で設定した行動施策の効果検証を行うことも効果的である。
仮に、成果が見られない施策については、手法を見直すか、他のアプローチを試みるといった転換も必要である。
さいごに
エンゲージメント指数の向上は、企業の成長と成功に直結する重要な要素である。
エンゲージメント指数が高ければ、生産性やチームワークが向上し、顧客へのサービス品質も向上することだろう。
そのために、まずは自社のエンゲージメント指数を測り、現状を把握することから始めていただきたい。
自社における強み・弱みは、どこにあるのか?弱みの部分は、どのようにして改善をしていくか?
上記の問に対し、可能な限り多くのメンバーを巻き込み、議論するプロセス自体もエンゲージ向上に向けた良い取り組みだと言えるだろう。
また、このような取り組みは、定期的に実施することを推奨する。
企業であれば、業績等の決算書分析は少なくとも年1回は、実施するだろう。
ただし、「人」に対する分析はいかがだろうか。
ぜひ、エンゲージメントサーベイ等のツールを活用し、エンゲージ指数を測る機会を定期的に作っていただきたい。
本事例に関連するサービス

Engagement KARTE
(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)
人的資本投資において重要となる指標を明確化し、人的資本経営の推進と企業価値の向上をサポートします。
Engagement KARTE(エンゲージメントカルテ・エンゲージメントサーベイ)の詳細はこちら
関連動画
関連情報