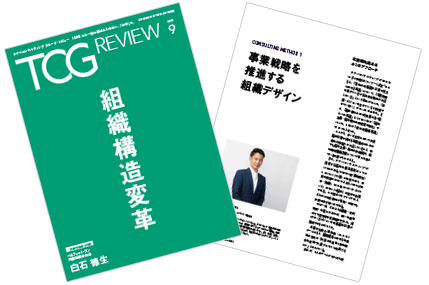人事コラム
組織開発とは?
組織開発の役割と手法を概観する
組織開発によって目指すべきポイントや考え方・手法を解説

組織開発とは何か
「組織開発」という言葉を聞いて、どのような実践を、誰が、何に対して行うものなのか、イメージを掴みかねている方々が多いと推察される。なぜならば、組織開発では扱う領域が広く、意味も曖昧で実体を捉えにくいという特徴を持っているためである。「27通りの組織開発の定義の中に、60個も変数が存在している状況」と、ある研究(Egan 2002)でも示されているほどだ。
しかし、定義が曖昧なままでは組織開発が何なのかをイメージ・実践することは困難であるため、本コラムでは組織開発の代表的な(※)定義である次のものを使用する。
「組織開発とは、組織の健全性、効果性、自己革新力を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」(Warrick 2005)
この定義が示すように、組織開発の目的は単なる業績向上に留まりません。従業員がいきいきと働ける健全な文化・風土、目的を達成するための効果的なプロセス、そして外部環境の変化に柔軟に対応できる自己革新力の3つの要素を同時に追求することが、組織開発の核となります。これらの要素は、組織が持続的に成長し、変化する現代社会で成功するための不可欠な基盤を築きます。
※組織開発において、「何を」良くすることを目指すのか、組織開発の定義に共通する言葉を検討した結果、健全性・効果性・文化・組織の革新力という言葉が抽出されている(Cummings & Worley 2015 等)。この中で、3つの単語が使用されている定義が、上記Warrickによるものである。
組織開発とは

組織開発と人事施策・人材育成との違い
組織開発、人事施策、人材育成は、いずれも組織と人に働きかける活動であるが、その目的とアプローチには明確な違いがある。これらを混同すると、効果的な組織変革は実現できない。ここでは、それぞれの役割を整理し、組織開発が持つ独自の立ち位置を明確にする。
人材育成は、社員個人のスキルや能力を向上させる「個」へのアプローチである。研修やOJT(On-the-Job Training)を通じて、個人のパフォーマンスを高め、キャリア形成を支援する。人事施策は、採用、評価、報酬、異動といった組織の「制度」に焦点を当てるアプローチである。公平な評価制度や、成果に応じた報酬体系を構築することで、組織目標の達成を促す。これらの活動は、組織のパフォーマンスを高める上で不可欠であるが、個人の能力や組織の制度という「点」や「線」のアプローチに留まる傾向がある。
一方、組織開発は、組織全体の関係性、文化、プロセスといったシステムそのものに働きかける「面」のアプローチである。個人の能力や制度がどれだけ優れていても、チーム間の連携が取れていなかったり、部門間の対立があったりすれば、組織全体の成果は最大化されない。つまり、組織開発は、人材育成や人事施策が効果的に機能するための土壌を耕す役割を担っているのである。個々の能力や制度を最大限に活かし、メンバー間の相乗効果を生み出す「健全性」「効果性」「自己革新力」を追求する活動こそが、組織開発の本質であると言える。
組織カルチャーの変革ポイントとは?

組織開発では何を目指すのか(なぜ組織開発が必要なのか)
こちらの定義に則れば、組織開発では「健全性」「効果性」「自己革新力」を高めることが目的となる。
組織の健全性とは、社員の生活やプロセスの質を示している。具体的には、日常業務における対人関係が良好なものか、個人と組織の間に繋がりを感じることができるか、と言える。
組織の効果性とは、組織全体のパフォーマンス(望ましい目標を達成する力)を示している。組織が効果的に仕事を進めて、成果を出すことができるかどうか、と言える。
最後に、自己革新力について。経営環境は常に変化しており、組織はこの環境変化に適応することが求められる。いま現在の環境下において、健全性と効果性を発揮できていたとしても、未来に対して備えるべく、学びを通じて変化に適応する力を身につける努力を怠ってはならないのだ。
ではなぜ、組織はこういった状態を目指して動いていく(組織開発をする)必要があるのか。
その理由は、組織というものの性質にある。メンバーが集まっただけでは、それは組織とは言えずただの「集団」のままと言える。ある共通の目的に向かって、各々の役割分担を行ったうえで、メンバー同士が互いに協力し合うことが、組織を成立させる要件である。しかし、社会心理学者のスタイナーは、組織において何らかの課題に取り組む際の生産性を予測する概念として、次の式を提唱している。
実際の生産性=潜在的生産性-欠損プロセスに起因するロス
この考え方はプロセス・ロスと呼ばれており、複数メンバーが集まる組織において、仕事をサボる(手を抜く)人が現れたり、コミュニケーションがうまくいかなくなることで、かえって非効率性を生み出してしまうことを示している。人が集まっただけでは、組織として適切に機能し、成果をあげられるわけではない。ここにこそ、組織開発が必要な理由がある。組織とはそもそも、組織自らのプロセス・ロスを防止し、メンバー同士の相乗効果や相互支援によって、意図的に成果をあげるための取り組みをしなければならないのだ。

組織開発における変革(発達)の対象はなにか
上述した組織開発の定義において、「組織を理解し、発展させ、変革していく」とあるが、組織の「何を」変革するのかまでは言及されていない。そのためここでは、Cummings & Worley が提唱した分類を使用する。
まず、組織には「ハードな側面」と「ソフトな側面」がある。ハードな側面とは、組織構造や規則、制度などの形あるものや明文化されたものを指す。一方でソフトな側面とは、人の意識やコミュニケーションのあり方、信頼関係やモチベーションといったように、人と人との間で起こっている人間的な側面を指す。
組織開発において変革する対象は、ソフトな側面であるヒューマンプロセスへの働きかけから始まった。一方で、組織開発が発展する歴史の中で、ビジネス上のニーズに応えるべく、現在ではハードな側面である戦略や構造、制度といったものへの働きかけも組織開発に含むとされている。
整理をすると、組織開発における変革の対象として、①戦略的働きかけ:組織の中長期的な戦略を、組織メンバーの個人レベルまで浸透させる取り組み等、②技術・構造的働きかけ:組織構造や仕事の進め方の変革等、③人材マネジメントによる働きかけ:報酬体系や評価制度の改善等、④ヒューマンプロセスへの働きかけ:人と人との間に起こっている関係性を高める活動等、の4つに分類することができる。

組織開発における手法はなにか
組織開発の定義を再度確認すると、「計画的で協働的な過程」とある。また、手法を検討する際に大切なのは、自社や自部門の課題を明確化しておくことである。そのうえで、働きかけるべきは戦略なのか、技術・構造なのか、人材マネジメントなのか、ヒューマンプロセスなのか、優先順位を見定める必要がある。本コラムにおいては、ヒューマンプロセス(関係性)を対象とし、計画的・協働的な手法を紹介する。
上記手法には、「診断型組織開発」と「対話型組織開発」の2つがある。
昨今ではHRテックが各企業へと多く導入されたことにより、エンゲージメントサーベイ等の診断(調査)実施も盛んである。こうしたサーベイの結果を組織のメンバーへとフィードバックして進める手法が、診断型組織開発の代表例と言える。サーベイには、「経営理念や組織の価値観に共感しているか」「職場コミュニケーションは活発か」といった質問項目があり、その項目におけるYES(NO)の割合から現状を把握し、YESの割合を増やすにはどうすればよいか、という観点から行動計画を考えていく。客観的に望ましい目指す姿(YESの割合という正解)と現状とのギャップを埋めるためのアプローチと言える。
一方で、対話型組織開発では、正解は組織メンバーの中にある、と考える。人によって望ましい姿は違う(客観的な理想の姿は存在しない)という前提のもと、対話を通じて、メンバー間の認識の違いや、物事の捉え方の違いを認識していくことで、個々人の行動変容を促していく。
ただし、上記はあくまでもアカデミックな分類を記載しているに過ぎない。実務における組織開発においては、どちらか片方だけを行うのではなく、組織の現状に応じて双方をうまく組み合わせて進めることが肝要である。「有用である」と認識できたものについては、あの手この手で組み合わせ、課題を解決していくことが求められる(例えば、診断型組織開発では、客観的に組織課題を抽出することができるため、上司や経営層の理解・納得が得られやすいという利点があるため、まずはそこから着手する等)。極論すれば、組織開発という手法や内容に拘らず、成果をあげられる(組織の健全性・効果性・自己革新力を高められる)のであれば、何をしても良いのである。

組織開発を推進するステップ
立教大学・中原淳教授および南山大学・中村和彦教授は、その共著において、診断型にしても対話型にしても、組織開発を進める共通のステップがあると提唱している(下記3ステップ)。
==========================
ステップ①:見える化
組織の状態・抱えている課題を可視化する
↓
ステップ②:ガチ対話
可視化された課題を、関係者一同で向き合い、対話を重ねる
↓
ステップ③:未来づくり
自分たちの組織のあり方を、関係者一同で自ら決める
==========================
「見える化」とは、サーベイやヒアリング、対話等を通じて、組織課題を眼に見える形にすることである。そして、「ガチ対話」において、その課題に対して関係者一同で向き合い、解消を目指して話し合いを行う。ただし、この段階では1つの意見に集約したり、意思決定までをする必要はない。各自の意見を出し合い、お互いの意識や認識のズレが明らかにすることが重要となる。最後の「未来づくり」において、組織としての1つの合意を作っていく。これからの組織を、当事者としてどのようにしていきたいのかを議論し、自分事として意思決定まで行う。メンバー全員が、自分たちの組織に関する未来に関して同じビジョンを共有できている状態を目指す。
本コラムでは名称のみの紹介とするが、2000年代に広まった組織開発の手法には、オープン・スペース・テクノロジー、ワールド・カフェ、アプリシエイティブ・インクワイアリー、フューチャー・サーチのような手法が、独自に開発・発展してきた。これら組織開発の手法(進め方)は、上記のような3ステップで進行される。様々な手法はあれど、各手法には共通点が見いだせ、上記3ステップに集約されていくというのが、両氏の主張である。なお、これらの手法を実践するに当たっては、書籍を読むだけでは困難であるため、まずは自らが実際に体験することを推奨する。

組織開発を成功させるための鍵
組織開発の手法やステップを理解したとしても、それを成功させるには不可欠な要素がある。それは、組織を構成する人々の当事者意識と、変革を導くリーダーシップである。
組織開発は、一部の担当者が主導するものではない。サーベイや対話を通じて課題が「見える化」されたとしても、その解決を他人任せにしては意味がない。組織の未来は、その中にいる一人ひとりが「自分たちの課題だ」と捉え、自ら行動を起こすことによってはじめて形作られる。変革への熱意と責任感がなければ、取り組みは単発のイベントに終わり、持続的な変化は生まれないのである。
また、トップからミドル、そして現場の各階層におけるリーダーの役割も極めて重要である。リーダーは、組織開発の目的を明確に伝え、変革の意義を組織全体に浸透させる必要がある。また、対話を通じて意見の対立が起きた際には、それを恐れず、むしろ健全な議論として受け止める姿勢が求められる。心理的安全性の高い土壌を自ら率先して築くことで、メンバーが安心して意見を出し、主体的に関与できる環境が生まれる。
手法やプロセスはあくまで道具に過ぎない。組織開発を真に成功させる鍵は、参加者全員が変革の担い手となり、リーダーがその推進役として機能することである。
関連動画
関連情報