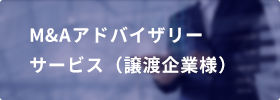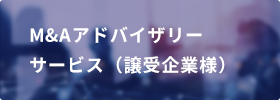M&A情報
M&Aの意向表明書とは?
その役割と記載時の注意点を解説
2023.06.01
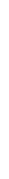
M&Aにおける意向表明書とは
M&Aにおける意向表明書とはLetter of Intent(LOI)とも呼ばれ、譲受企業候補が譲渡企業に対して提出するもので、名前のとおり、譲受企業候補の譲受に対する意向を譲渡企業に対して提示する内容です。
譲受企業候補が複数いる場合、譲渡企業は譲受企業候補を選定する必要があります。各社より意向表明書を提出してもらい、それを基に交渉を進める企業を選定・絞り込みます。
具体的な記載内容としては、譲受企業の企業概要やM&A実施の目的、希望譲受価額とその算定根拠、M&Aスキームや条件などがありますが、意向表明書を出しただけでは法的な効力はなく、最終契約の締結に向けた具体的な内容(独占交渉権など)については、基本合意書(MOU)にて交わされることが多いです。

意向表明書の目的と提出までの流れ
意向表明書を提出するまでのM&Aディールの流れを譲受企業の視点から確認してみましょう。
譲受企業は、案件情報を入手した後、初期的な検討を行います。その結果、案件に対して関心がある場合は、より具体的な検討のため詳細情報の収集と並行して一次情報の収集・確認を目的とした譲渡企業との面談(トップ面談)を実施します。トップ面談を経て前向きに検討する場合、デューデリジェンスの前に、意向表明書の提出をします。デューデリジェンスは譲渡企業にとって会社の情報を開示するのでリスクと隣り合わせです。意向表明書の提出をデューデリジェンス前に求めることで譲受企業の譲受に対するコミットメント度合いを確認する狙いがあります。
前述の通り、意向表明書には譲受の目的や予定している譲受価額、役員の処遇などの現時点で想定している諸条件、クロージングまでのスケジュールなどを記載します。一般に意向表明書には、法的拘束力を持たせませんが、譲受企業候補が提出した意向表明書の内容を全面的に反故(ほご)にすることは通常ありません。そのため、意向表明書を出すということは譲受企業は基本的に譲受に対して前向きであり、想定外の問題がない限りは譲受プロセスを進めていきたいという意思表示として機能します。
意向表明書提出後は譲渡企業がその受諾を行い、基本合意契約締結後、デューデリジェンスを開始するという流れが一般的です。一次意向表明があり、デューデリジェンス後に二次意向表明を行うというケースもあります。
意向表明書に記載する内容とは
改めて、意向表明書に記載する内容とポイントを整理していきます。意向表明書は譲渡企業にとっては譲受企業が、譲受後にどのような経営方針を持つのか、また従業員に対する処遇はどのように考えているのか等を確認し、譲渡するに適した相手なのかを判断する材料です。
そのため、意向表明書に記載する基本的な内容としては大きく譲受条件に関する内容と譲受後の経営方針に関する内容となります。各カテゴリーの詳細な記載項目は概ね下記のとおりですが、その他譲渡企業が記載を希望する内容がある場合や譲受企業候補が記載しておきたい項目がある場合は追記することもできます。
【譲受条件に関する内容】
(1)自社の概要・沿革
(2)譲受を希望する理由
(3)取引スキーム
(4)譲受価額とその算定根拠
(5)保証債務等の取り扱い
(6)役職員の雇用に関する内容
(7)今後予定しているデューデリジェンスの内容について
(8)クロージングまでの想定スケジュール
【譲受後の運営方針に関する内容】
(1)譲受後の経営方針
(2)役職員の処遇に関する内容、後任人材の選定について
(3)商号や屋号の取り扱い
(4)予定されている組織再編に関して
(5)主要取引先との取引に関して
【その他】
(1)公表について
(2)排他的交渉権の付与について
(3)取引の前提条件について
(4)取引の実行に際しての必要な手続きとそれに要する時間について
(5)現時点の社内決議レベル
(6)譲受資金の調達方法について

意向表明書の書き方
続いて、実際に意向表明書(LOI)を作成する際の書き方や手順を整理します。
STEP1 宛先・件名
冒頭に譲渡企業の正式社名と代表者役職氏名を記載し、件名は「意向表明書」と明示します。ファイル名も同一表記にしておくと、譲渡企業の社内回覧が進みやすくなります。
STEP2 前文(趣旨説明)
株式譲渡のケースの例ですが、「当社は貴社の発行済株式を株式譲渡の手法により取得することを検討しており、下記のとおり譲受意向を表明いたします」のように簡潔に宣言しましょう。合わせて、期待しているシナジー効果を1〜2行添えておくと、読み手の関心を惹きやすくなります。
STEP3 企業概要
譲受企業の設立年、資本金、売上高、主要事業、上場の有無などを表形式でまとめます。沿革やグループ会社図は別紙にし、本文をコンパクトに保つと読みやすくなります。
STEP4 主要取引条件
①取引スキーム、②想定譲受価額と算定根拠、③資金調達方法、④クロージングまでの想定期間の4項目をセットで記載するのが標準です。
譲受価額は「●億円〜●億円(EBITDA×●倍)」のように幅を持たせ、調達方法では自己資金比率や融資承認の有無を明示すると、実行力を示せます。
STEP5 取得後の運営方針
経営体制、役職員の処遇、ブランド使用方針などを箇条書きで示します。譲渡企業が懸念しやすい雇用不安や社名変更の有無について、先回りして記載することがポイントです。
STEP6 前提条件・独占交渉権
デューデリジェンス完了や取締役会決議など、成約の前提条件を列挙し、独占交渉期間を「本書受領日から3ヵ月間」など具体的に設定します。途中解除条項や重要事項判明時の条件変更可否もここに含めると、後工程でのトラブル防止につながります。
STEP7 有効期限・法的効力
本書がノンバインディングであり法的拘束力を伴わない旨を明記し、回答期限(例:受領後2週間)を設定します。これにより譲渡企業の意思決定スピードが向上します。
その他
末尾には代表取締役の署名・押印欄を設け、実務窓口としてアドバイザーや弁護士の連絡先を記載してください。
また、ページ番号を振っておくと差し替え時の混乱を防げます。紙提出の場合は原本2通を用意し、PDFデータを併送すると社内共有が容易です。
以上のフォーマットを活用すれば、譲渡企業は各買い手のLOIを横並びで比較しやすくなり、初期交渉の円滑化や全体期間の短縮が期待できます。
M&Aの意向表明書と基本合意書の違い
M&Aにおける契約文書の種類を説明します。一般的にまず、秘密保持契約書(NDA)が交わされ、次に意向表明書(LOI)、その後に基本合意書(MOU)、最後に最終契約書(DA)が締結されます。
よって意向表明書はM&Aの初期段階で交わされる法的拘束力のないものであり、譲受企業の意向を明確にするためのものです。
逆に譲渡企業は、譲受企業候補先の絞り込みを行うために、意向表明書の提出を求めるにすぎません。
一方、基本合意書は譲受企業と譲渡企業の双方が基本的な譲渡条件等に合意したことを証する書類です。
M&Aの条件交渉が実施された後に、より詳細な取引条件を定めた契約となり双方の合意が必要となり、条文毎に法的拘束力を設定する場合があります。
以上が、意向表明書と基本合意書の違いになります。
意向表明書の法的拘束力について
繰り返しとなりますが、一般的に、意向表明書は法的拘束力を持つことはありません。デューデリジェンスが完了していない段階での意向表明は、単なる「譲受する意思」を伝えるものです。デューデリジェンスの結果を考慮して初めて、最終的な成約に移るかどうかを決定します。しかし、意向表明書が法的拘束力を持たないとしても、実際にはM&Aのその後の交渉に記載内容が活用されるため、譲受企業が合理的な理由もなく、意向表明書の記載内容を一方的に撤回するケースは少ないです。
意向表明書作成時の注意点
最後に、意向表明書作成時の注意点について整理して解説します。
1. 法的拘束力と意向表明書の性格
前述のとおり、意向表明書に記載する項目は譲受条件の基本的な方向性を示すものとなりますが、譲受企業、譲渡企業間で法的拘束力を持たせないことが一般的です。意向表明書の基本的な性格としては、譲受企業候補から譲渡企業に対する一方的な意思表示です。(ノンバインディングオファー)
その後に予定されているデューデリジェンスの結果を踏まえて、特に譲受条件については変動する可能性があることや、譲受にあたっての前提条件がある場合はその旨を記載しておくと今後の交渉において双方で大きな認識の食い違いが生じることを減らせるでしょう。
法的拘束力がないとはいえ、意向表明書は最終的に合意する条件のベースとなるものですので、その提出にあたっては細心の検討が必要です。
2. 提示価格の妥当性チェック
意向表明書を作成する際は、まず提示価格が市場相場から極端に乖離していないかを社内外で二重チェックすることが重要です。高すぎればデューデリジェンス後の価格変更が不可避になり、信頼低下というデメリットが生じます。逆に低すぎると初期段階で検討から外されるため、バリュエーションは複数手法で裏付けを取りましょう。近年はM&Aアドバイザーが簡易バリュエーションを無償で実施してくれるケースもあるので活用しやすくなっています。
3. 資金調達の可否と金融機関承認
次に、資金調達の可否や金融機関承認の取得期間を甘く見積もらないことです。ローンコミットメントレターを「提出予定」ではなく「取得済」とするだけで、譲渡企業は資金実行リスクが低いと判断しやすくなります。調達費用が金利上昇で増える場合の影響度合いも、補足資料で示しておくと親切です。
4. 独占交渉権設定時の留意点
独占交渉権を求める場合は、交渉が停滞しないよう期限と解除条件を併記し、追加開示が遅れた場合に期間を自動延長するなど柔軟な条項を設けると双方にとってストレスが少なくなります。
5. 法務面の確認と規制対応
法務面では、弁護士のリーガルレビューを必ず受け、独占禁止法・外為法の届出が必要となる取引かどうかも確認しておきましょう。特に海外子会社を含むケースでは、クロージング遅延リスクを最小化するため、各国当局の許認可が下りるまでのバックアッププラン(長期クロージング条項の有無)を記載しておくと安心です。
6. 重要事項判明時の対応方法
さらに、意向表明書には後日「重要事項が判明した場合は協議のうえ条件を変更し得る」と盛り込みつつも、変更が価格に与える影響を具体的に数値シミュレーションしておくと、交渉がこじれにくくなります。最終契約段階で修正してもらう前提で曖昧に書くより、初期段階でリスク共有しておく方が結果的に時間とコストを節約しやすいからです。
上記まとめとして、
①相場感に基づく現実的な価格
②取得資金の支払能力を裏付ける書面
③譲渡企業の懸念に配慮した独占交渉期間設定
この3点を押さえた意向表明書は、譲渡企業から前向きなフィードバックをもらう確率が高まります。社内リソースが不足する場合は専門家チームを早期に組成し、財務・法務・税務の各分野を網羅的にレビューしておくことが重要になります。

小野 樹
M&Aコンサルティング事業部
ゼネラルパートナー
金融機関や会計事務所とパートナーシップを築き、後継者を育成する企画や取引先企業が抱える経営課題とコンサルティングソリューションをマッチングするアライアンス事業を推進。M&A部門の事業化、仕組みづくり、商品開発、実績づくりを行い、大手企業のバイサイド支援から中小・個人企業のセルサイド支援まで幅広い実績を持つ。
- 主な実績
-
- 大手生活品メーカーの同業買収に関するバイサイドFA
- 中小システム開発会社のM&Aアドバイザリー
- 中堅建設業の同業買収に関してのデューデリジェンス
- 地場ゼネコンのM&A戦略構築支援
- リサイクル関連会社の企業買収に関するセカンドアドバイザリー
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など