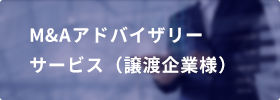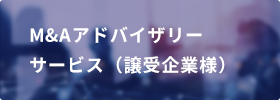M&A情報
M&Aの退職金スキームとは?
節税ポイントや売主・買主のメリットを紹介
2022.11.17
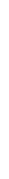
M&Aにおける退職金スキームとは
M&Aにおける退職金スキームとは、企業の買収や事業承継の際に、株式譲渡の対価の一部を役員退職金として支払う手法です。このスキームは、M&A取引における節税対策の一環として用いられ、売り手と買い手の双方にとって経済的なメリットをもたらします。具体的には、売り手側は譲渡時の手取り額を最大化でき、買い手側は買収時の手出し資金を抑えることが可能となり、退職金スキームはM&A取引を円滑かつ効率的に進めるための重要な手段の一つです。
退職金スキームの目的とその重要性
退職金スキームの目的は、M&Aにおける税務上の負担を軽減し、取引の双方にとって最適な経済的条件を整えることです。売り手にとっては、役員退職金として支払われる部分が退職所得控除により課税額が下がり、株式譲渡益課税よりも低くなり手取り額の増加を期待できるケースが多くあります。一方で、買い手にとっては、退職金として支払われる金額が対象会社の税務上の損金になり節税効果を得ることと、買収金額を下げて買収に必要な資金を抑えることができます。但し、株式譲渡対価は買い手側が株主に払うという資金の動きに対して、役員退職金は対象会社から退任役員に支払われますので、対象会社に十分な余剰資金があるか、役員退職金を支給してキャッシュフローに影響がないか、現預金が減り自己資本比率等が変わることで悪影響がないか等の確認が必須となります。
退職金スキームを適切に活用することで、双方メリットを享受することができ、企業の成長や発展に寄与することが期待されます。
M&Aにおいて役員退職金の仕組みを活用して手取り額を最大化する方法
M&Aにおいて、手取り額をいかに多く残すかは譲渡側として非常に大きなポイントです。退職金スキームを使えば、手取り額を増やすことができると聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。M&Aの取引は高額になるため、受け取り方法の違いによって、最終的に手元に残る金額が大きく変わることがあります。これまで築き上げてきた会社を譲渡する際に、手取り額を少しでも多くしたいと考えるのは当然です。
具体的には、役員退職金の仕組みをうまく活用して税負担を軽減し、手元に残る金額を最大化する方法が有効でしょう。具体的には、「会社を譲渡するタイミングで退職金を支払い、株価を圧縮して株式を譲渡する」というのが、株式譲渡+退職金スキームです。会社の譲渡対価をそのまま受け取るよりも、自身の代表退任に伴う退職金のルールを活用することで、手取りを増やせる可能性があります。中小企業では代表取締役が株主であることが多いため、株式譲渡で得られる対価と役員退職による報酬を組み合わせて受け取ることが可能です。

役員退職金活用による譲渡・譲受のメリット
譲渡側にとってのメリットは、「手取り額の最大化」です。株式譲渡の場合、譲渡益に対する税率は一律20.315%です。一方、退職金にかかる税金は、退職所得金額の計算の際に退職所得控除(役員の勤続年数に応じて変動)と1/2計算が適用されるため、非常に優遇されています。その結果、実質的な税率は0%~27.5%(退職所得金額により累進課税)となります。退職金にかかる税率を計算し、最適なバランスを見極めることで、手取り額を最大化することが可能です。譲渡対価の金額によっては、資本金を超える額のすべてを役員退職金として受け取ったほうが、最終的に手取り額が増えるケースもあります。
譲受側にとってのメリットもあります。それは「譲受時の資金負担の軽減」です。役員退職金は譲渡企業が役員に支払うため、その支払い原資は譲渡企業の現金や預金(または現物資産の場合もある)から拠出されます。つまり、株式譲渡対価の一部を役員退職金として設定することで、譲受側は初期の資金負担を軽減することが可能です。
さらに、「対象会社の損金算入」も譲受側の重要なメリットです。株式取得に要した資金は損金算入できませんが、一部を退職金として設定することで対象会社での損金算入が可能となります。その結果、退職金を支払った年度、もしくは翌事業年度以降に発生する課税所得との相殺が可能となり、節税効果を得ることで対象会社でのキャッシュの蓄積や追加投資等に充てることができます。

役員退職金活用による譲渡・譲受の注意点
役員退職金を活用することによって譲渡・譲受それぞれにメリットがあることはお話ししましたが、注意すべき点もあります。譲渡・譲受それぞれの立場で解説します。
・譲渡側の注意点
株式譲渡益からは株式譲渡のために外部アドバイザーへ支払った報酬や譲渡に要した費用を控除することができますが、株式の譲渡価額を低くしすぎると当該費用を控除できなくなるケースが出てくる可能性がありますので考えて譲渡価格を設定(交渉)することが必要です。また、役員退職金を利用することで手取り額を増やすことができる一方で、退職金の額を過剰に設定すると税務上のメリットを享受できなくなる可能性があります。具体的には、役員退職金として支払われる金額が不相当に高額である場合、その一部は損金として算入されず、結果的に税負担が増えることになります。このような事態を避けるためには、適切な退職金額を算定することが重要です。
役員退職金の支給額は一般的に「功績倍率方式」によって算出され、以下の計算式が用いられます。
役員退職慰労金の支給額 = 退職時の報酬月額 × 役員勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は、役員の職責や業務に従事した期間に応じた倍率であり、同種事業や類似事業規模の役員に対する退職給与の状況を考慮して設定されます。したがって、功績倍率を適切に設定するためには、専門家の知識を活用することが推奨されます。
譲渡側は、これらを踏まえて、株式の取得価額や上述の譲渡に要した費用等、最終的に手元にいくら現金が残るのかを慎重に検証する必要があります。
・譲受側の注意点
譲渡企業が退任する役員に対して、不相当高額な退職金を支払った場合は退職金のうち不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。そういった事態が起こらないよう、退職金額を定めることが、中小企業のM&Aでは多く見受けられます。このスキームを活用することで、退任する役員や譲受側にとって税務メリットを享受することができます。ただし、役員退職金は支給額、支給方法、支給のタイミング等により一部または全額が役員退職金として認められないケースがあるので注意が必要です。
上記のように譲渡側としては、最終的に手元に残る所得を最大化するために、譲渡価額や退職金の額を慎重に設定することが求められます。一方、譲受側としては、譲渡企業が支払う退職金の金額や支給方法が税務上適切であるかを確認することと、支給後の対象会社のキャッシュフローの影響やB/S変動の影響も想定することが必要です。
事業譲渡の場合の考え方
事業譲渡の場合は買主にとって役員退職金の支給は関係ありませんが、売主にとっては役員退職金を活用することで税務メリットが発生することがあります。事業譲渡の対価は会社に支払われるため、売主(株主)が直接資金を受け取ることはできません。そのため、事業譲渡益は会社の利益になり法人税が課税されることになります。当該年度に同程度の損金(別事業への投資等)が発生すれば、課税額は少なくなりますが、事業譲渡による益金に対する損金が存在しない場合には、役員退職金を支給し損金計上することで利益を圧縮することができます。ただし役員を退任する場合には会社清算前提での退任ということであれば別ですが、事業を継続していくためには新役員の就任が必要になる可能性もあるため注意が必要です。

小林 隼人
M&Aコンサルティング事業部
チーフマネジャー
新聞社にて新聞販売店の経営・営業支援業務に従事後、独立系M&A仲介会社に入社。主にエネルギー系企業のM&Aなどを経験後、当社に入社。企業の事業承継課題も目の当たりにしてきた経験を踏まえ、現在はM&Aを中心としたコンサルティングを数多く手掛け、企業のあらゆる経営課題解決に取り組んでいる。
- 主な実績
-
- LPガス会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 産業資材卸会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 機械器具卸会社の譲渡側M&Aアドバイザリー
- ビルメンテナンス会社の譲受側M&Aアドバイザリー
- 建設会社の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
- 人材派遣会社の譲受側M&Aアドバイザリー
- 製造業(半導体関連)の譲渡側・譲受側M&Aアドバイザリー
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など