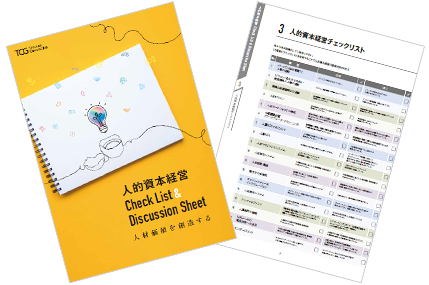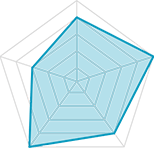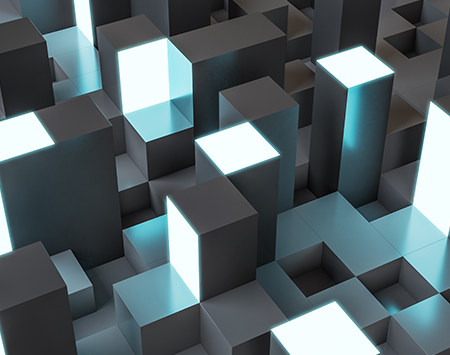人事コラム
効果的な人事制度見直しのためのステップ
~人事制度改革と変革のポイント~

人事制度見直しの背景と必要性
企業経営は言うまでもなく、ヒト・モノ・カネのバランスで展開される。
「モノ」のバランスとは、主に在庫の適正化であり、設備投資の適正化である。「モノ」の管理の巧拙が不稼動在庫の残高という形で目に見えてわかる。
「カネ」のバランスとは、キャッシュフローであり、借入の適正化である。「カネ」の管理の巧拙も分かりやすい。キャッシュフローが悪くなれば、借入金を増やさざるを得なくなる。「モノ」と「カネ」の管理の巧拙は、不具合が目に見えるためわかりやすい。
一方、 昨今は人的資本に代表される目に見えづらい「ヒト」に対する関心が高まっている。
生産年齢人口は減少局面に入り、「採用」の難易度が増し、苦労して採用したヒトを「育成」し、「活躍」させ、「定着」させる善循環の流れをうまく展開できる企業が、成果を出し始めている。
「採用」→「育成」→「活躍」→「定着」の流れの中で、特に「育成」・「活躍」・「定着」の部分において、人事制度が寄与する割合は高い。このような背景から、人事制度の見直しを進めている企業が増加している。

人事制度が果たしている機能
最初に認識しておかなくてはいけないことは、「人事制度は給料や処遇を決めるだけのシステムではない」ということである。
「経営管理(マネジメント)機能」・「教育(エデュケーション)機能」・「査定(コントロール)機能」の順番で重要度を認識してもらいたい。
むろん、人件費を決めるための「査定(コントロール)機能」は人事制度の大切な役割である。しかしこれは機能の一部に過ぎない。重要視すべきは、人材を育てるための「教育(エデュケーション)機能」である。また、何よりも重要な機能として、人材の戦略推進力を高めるための「経営管理(マネジメント)機能」としての役割である。
「経営管理(マネジメント)機能」・「教育(エデュケーション)機能」・「査定(コントロール)機能」の3つの機能がバランスし、適正な運用がされ
れば、戦略を推し進める組織力が向上し、またその組織を構成する上司・部下など各人の能力が向上するのである。結果として、企業の業績向上に繋がっていく。

人事制度見直しの際に点検すべき項目
1.人材棚卸分析
現在の人員構成や、各階層ごとの人材レベルを分析し、課題を抽出する。年齢ピラミッドの形で表現し、ある年代では多く、ある年代は枯渇している等の状況を明確化する。これから「育成」していく若手社員層に対して、トレーナーを担う年代層は潤沢かなどの観点で点検する。言わずもがなの部分はあるが、図示すると偏りのバランスがはっきり見え、どのような制度改革をしていくべきか強化課題が見えやすくなる。
2.生産性分析
労働分配率、1人当たり人件費など財務的分析により、課題を抽出する。今後賃上げの要請がますます強まる可能性が高い。とは言え、労務費をいたずらに増やせば固定費は増え、企業の損益分岐点を押し上げてしまう結果となる。一方、賃上げ余地を感じにくい制度になれば、社員のモチベーションが上がらず、むしろ就労感が低下し、業績の低下や従業員の離職などのリスクが高まる。採用時の企業の魅力にも影響を及ぼす。どのような方向性に着地させるにしても、バランスが重要である。
3.人事システム分析
①人事戦略(人材ビジョン・人事方針)、②人事フレーム(等級制度)、③評価制度、④賃金制度、⑤昇進・昇格の要素について、点検し、課題を抽出する。そもそも人材ビジョン・人事方針等を明確にしていない企業も見受けられる。基準が明確か、公平性はある程度担保されているか、業務に必要な取得資格などが、何らかの形で反映されているかなどの観点で確認する。
4.運用体制分析
運用における資料関係の整備、必要な研修、サポート体制について点検し、課題を抽出する。

効果的な人事制度見直しのための具体的なステップ
1.人材ビジョン・人事ポリシーの明確化
どのような人材を評価・育成したいのかという「人材ビジョン」と、そのためにどのような人事システムをつくるのかという「人事方針(ポリシー)」の構成でまとめていくと良い。「どうありたいのか?」という姿を明文化する。社風や風土により、何となくこうだろうという感覚は皆持っているが、明文化するとなると難儀するケースが多い。ここを整理し、言葉を紡ぎ出し、明文化する意義は充分にある。
2.人事フレームの設計
職能等級・役割(職務)等級・職種など組織・マネジメントに即した人事のフレームであり、社員のキャリアパスや、役割に対する認識を深めることを狙いとし、これが評価制度や賃金制度を作るベースとなる。グレードの数、働き方により複線型にしていくか等が検討ポイントとなる。近年ではジョブ型を検討し導入する中堅・中小企業も増加している。
3.評価制度の設計
人事フレームに基づき、各フレームごとの評価項目や方法などを設定する。上司にとってはマネジメントの指針に、部下にとっては成長のマイルストーンとなる。評価段階数(5段階~7段階程度が多い)、評価基準などを決める。
4.賃金制度の設計
「賃金体系」を確立、人事フレームに連動し、賃金のスケールや分配方法を設定する。その他、各種手当などの福利厚生部分も策定する。基本的には今後の賃上げにも対応可能な制度設計を目指す。初任給を上げると、結果的にベースアップせざるを得ない会社が多く、等級の賃金スケールの上限・下限額の設定や重なりをどこまで許容するかの方針が必要となる。
5.昇進・昇格のルール設計
評価制度をベースに、どのような人材を昇格させ、あるいは役職を与えるのかなどその決定方法を策定する(場合により降格基準も)。

人事制度を見直す際に大事なこと(さいごに)
今後、明らかに変化の幅の大きい世の中が予想されている。今時点で完璧なものを求めるあまり、人事制度の展開が遅れると、作り上げた時に、既にアップデートが必要な環境になっている状況も充分に有り得る。
ベストよりもベターの思想でスピーディに組み上げていくことが大事である。運用8割の思想、組み上げるというよりも、マイナーチェンジ前提で、人事制度をパワーアップしていく展開イメージを持って取り組んで欲しい。
パーパス経営の浸透や、採用の難易度アップにより、人事制度に求められる「教育(エデュケーション)機能」も更にパワーアップが必要であろう。また、65歳定年に向けた対応も求められてくるなど、どのみち人事制度を作り上げて10年変えずに使うということは考えにくい。マイナーチェンジを前提とした、柔軟性のある制度設計と運用に向き合って欲しい。
本事例に関連するサービス
関連動画