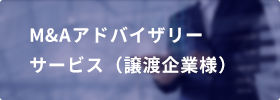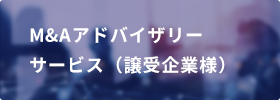M&A情報
PPAとは
2025.09.17
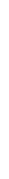
PPAとは何か
PPAは「Purchase Price Allocation」の頭文字を取った略語で、日本語では「(M&A時の)取得原価の配分」という意味です。
M&Aでは「のれん」が発生するケースが多いです。「のれん」は譲受価格と帳簿上の純資産価額との差ですが、買い手が対象会社に簿価以上の価値を見出したものを「超過収益力」として認識しているといえます。
PPAの概念を簡単に言うと、譲受時に認識したのれんについて、具体的に何の価値として認識し、どのような根拠に基づいて計上しているのか、その内訳を明示しようという考え方です。
もともと、国際会計基準(IFRS)ではPPAが必須でしたが、日本基準においても2010年から段階的に導入されています。
日本国内においても戦略としてM&Aが活発化するに伴い、上場企業におけるのれんの総額は年々増加しています。それは裏返すと将来の減損リスクも比例して高まっているといえます。投資家サイドも無形資産であるのれんの収益への貢献度に関してシビアに見ており、企業側はより一層、情報開示と説明責任が求められるようになりました。
このように上場企業では必須となっているPPAですが、次に具体的にどのような場合にPPAが要求されるのかみていきましょう。

PPAが求められる場面とは
上述にてPPAはM&Aで認識したのれんについて個別具体的にその価値を識別し、評価するものとして説明しましたが、PPAを行う目的はそれだけにとどまりません。
PPAは広く無形資産の評価に関する考え方であるため、M&Aで発生したのれんのみならず、他にも「裁判目的で無形資産の評価を行う」場合や「相続や贈与で無形資産に関する課税額を算出しなければならない」場合、「無形資産の売買などの取引目的で当該無形資産の評価をしなければならない」場合など、PPAが必要とされるケースはM&A以外でも様々です。
上記シチュエーションからも、PPAが評価対象とする無形資産がのれんだけでなく、無形資産全般に関するものということがわかります。
無形資産とは具体的には、特許などの知的財産関連、ノウハウなどの競争優位性関連の無形資産、ロイヤリティや許認可など契約・ライセンス関連、顧客情報や顧客との関係性など顧客関連の無形資産、その他人材や組織、商標やブランドなどに紐づくものなどがあります。

M&AにおけるPPAの実務
ここまでPPAの目的や概念の説明を行ってきましたが、ここからはM&AにおけるPPAの実務について解説します。
PPA実施に際して、まずは「いつ誰がやるのか」という点についてみていきます。
いつやるのかという点に関しては、原則、M&Aが完了した時から1年以内に実施することが義務付けられています。譲受のタイミングや決算期との兼ね合いもありますが、実務的にはクロージング時点から半期以内に完了しているケースが多いようです。後述しますが、PPAの作業は専門的なプロセスであるため、自社内だけでなく、PPAの実務を担当する会計士や監査法人とのやり取りが発生するため、一定の時間が必要です。PPAの結果については絶対的な正解はありません。そのため、PPAの実施方針(評価対象物の特定、評価手順などの評価方針、評価結果)については監査法人と事前にある程度認識のすり合わせが必要です。事前の資料分析も含めて、実務が完了するのは通常3~4ヶ月程度かかるものと考え、実施スケジュールの検討をするとよいでしょう。
注意点として、PPAの基準日はM&Aのクロージング日となり、基準日時点でのBSがベースとなるため、対象会社の経理状況によってはBSの確定作業自体に時間が必要な場合があるため、DD時点からPPAのスケジュールには留意しておく必要があります。
次に、誰が行うかという点に関しては、譲受企業が実施主体となります。上述のとおり、評価の実務は会計士やコンサルティングファームなどの専門家に依頼することになりますが、対象会社に関する情報や資料提供、無形資産に係る評価方針の決定などは、譲受企業が主体的に動く必要があります。
続いてPPAの実務の流れを解説します。
PPAの作業は大きく分けると無形資産の「識別」とその「評価」の2フェーズに分類できます。
作業の全体の流れを俯瞰すると、下記のような手順になります。
(1)対象会社の情報収集、資料分析
(2)インタビュー
(3)無形資産の測定
(4)レポート作成
(5)監査人レビューおよびフォロー
上記(1)および(2)で評価対象とする無形資産の識別を行い、(3)で無形資産の評価を行います。
その後(4)および(5)で結果のとりまとめと監査法人のチェックを受けるという流れになります。
まず、(1)の対象会社の情報収集、資料分析フェーズでは、単に対象会社に関する財務的、組織的な分析のみならず、対象会社が置かれている市場環境や競合環境など事業的視点での分析も行います。この際、必要な情報や資料を対象会社で保有していない場合もありますので、その場合は追加的に調査・分析、資料作成などの業務が発生することがあります。PPAでは無形資産の識別・評価においては、譲受企業がどのような目的でどういった戦略に則してM&Aを実施したかという目的や背景なども考慮しますので、対象会社だけでなく、譲受側でもその意義・目的を整理しておきましょう。
(2)のインタビューでは無形資産の識別を行うため、譲受企業が対象会社の何を目的に、何の価値に着目して譲受したのかヒアリングを通じて確認します。PPAでは分離要件といって、無形資産をそれ単独で分離して識別可能なものと、分離できないものを分けて識別するという手引きになっています(日本基準)。具体的に言うと、分離可能なものとは、法律上の権利や法律上の保護はないもののそれ単独で譲渡可能なものを指します。例えば、著作権や特許、ブランドや企業秘密の工程や製法などの無形資産がそれに該当します。
(3)の無形資産の測定では、識別された無形資産について、その価値を評価する作業を行います。
無形資産の評価方法は無形資産の種類により様々です。大別すると企業価値バリュエーションと同じようにコストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチによりそれぞれに適した評価方法を選択して評価を行っていきます。ここでも評価にあたって必要な情報が十分でない場合は、追加的な調査や一定の仮説に基づいて試算していくことになります。
(4)ではここまでの無形資産の識別のプロセス、評価方法、算定結果をまとめ、(5)で監査法人のレビューを受けることになります。監査法人レビューでは、書面およびインタビュー形式での質疑応答を行い、必要に応じて追加対応を行います。
PPAの結果は、最終的には財務諸表に反映されるため、(5)で監査法人に結果が受け入れられるまでフォローアップを行うことになります。
大まかには上記の流れでPPA実務は行われますが、実際は案件ごとに個別の論点がありますので、案件に応じて社内、専門家、監査法人と意見交換をしながら進めていきます。

PPA実施の注意点
最後にPPA実施にあたっての注意点をお伝えします。
まず、PPAの実施主体はあくまで譲受側であるため、監査法人やステークホルダーに対する説明責任は譲受企業にあります。そのため、評価実務は専門家に依頼したとしても、そのプロセスや評価ロジック、結果については評価人と共通認識を持ち、内容について十分に理解しておく必要があります。
また既述のとおり、無形資産評価には絶対的な正解があるものでもないので、客観的な情報に基づき、合理的に見積もることができる範囲で評価を行うことが重要です。情報の制約などにより一定の仮説に基づいた試算も多分に行われるため、試算の前提や制約条件について事前に理解しておきましょう。

丹尾 渉
執行役員
M&Aコンサルティング事業部長
2017年からM&Aコンサルティング本部の立上げに参画。M&A戦略構築からアドバイザリー、PMIまでオリジナルメソッドを開発。その後5年間で延べ80件以上のM&Aコンサルティングに携わる。「戦略無くしてM&Aなし」をモットーに、大手から中堅・中小企業のM&Aを通じた成長支援を数多く手掛けている。
- 主な実績
-
- 上場企業の新規事業開発を目的とした譲受側M&Aアドバイザリー
- 上場企業子会社の事業戦略からM&Aまで一貫性を持たせた戦略構築
- 上場企業子会社の買収調査のためのビジネスDD、財務DD、労務DD
- 中堅企業の事業ポートフォリオの転換によるビジネスモデル変革支援
- M&Aを初めて実施した中堅企業のPMI支援
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など