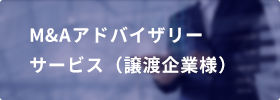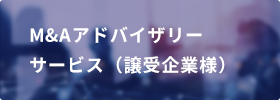M&A情報
M&A手数料の計算方法を解説!レーマン方式とは
2023.11.13
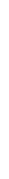
気になるM&Aの費用
M&Aにかかる費用総額は売り手か買い手かによって大きく異なります。
買い手の場合は、取得対価(譲渡金額)に加えて、専門家に支払う費用、登記費用などがあります。
専門家とはM&Aアドバイザー会社、デューデリジェンスを実施する会社(税理士、弁護士、社労士等)及び登記に関する司法書士が一般的にあげられます。
一方、売り手の場合はM&Aアドバイザーに支払う報酬以外には、特段大きな費用はありません。
買い手は、M&Aのプロセスで、初期分析のための調査や交渉が進んだ場合におけるデューデリジェンス時に会計事務所や法律事務所に調査費用が発生する一方で、売り手は調査を受ける側なので、そのような費用が発生しないためです。ただし、売り手側でも株式譲渡契約書の確認を弁護士に相談し、譲渡対価の受取方法などを税理士に相談することをお勧めします。その際、通常別途費用が発生することが一般的です。
売り手にかかる費用はアドバイザー報酬のみというケースがほとんどです。このアドバイザー報酬は成功報酬体系となっていることが多く、M&Aが成立した際、譲渡対価の受け取り時にその対価から支払うというケースが多いです。会社によっては着手金として、アドバイザリーサービス契約の締結時に数十万円~百万円程度の費用が必要な場合もあります。この着手金は成功報酬の内金となるケースもあれば、成功報酬とは別枠となるケースもあります。

成功報酬の算出方法レーマン方式とは?
では、成功報酬はどのように算出されるのでしょうか。
M&Aの成功報酬の多くは、「レーマン方式」という手数料体系に則っています。レーマン方式とはM&Aの取引金額に応じてそれに乗じる料率が逓減していく手数料体系のことを言います。取引金額が上がれば上がるほど手数料が下がっていく方式となります。
「レーマン方式」で算出した場合、具体的には下記のような計算方法になります。
取引金額が5億円までの部分・・・5%
取引金額が5億円~10億円以下の部分・・・4%
取引金額が10億円~50億円以下の部分・・・3%
取引金額が50億円~100億円以下の部分・・・2%
取引金額が100億円超の部分・・・1%
既に前述しましたが「レーマン方式」ではこのように、取引金額が大きくなればなるほど、乗じる手数料率が下がっていく仕組みになっています。例えば、取引金額が2億円の場合は、「取引金額が5億円までの部分」に該当しますので、料率は5%となり、「2億円×5%=1,000万円」がアドバイザーに支払う手数料ということになります。以上がレーマン方式の計算方法になりますが、ここで注意しなければならないのは、例えば取引金額が50億円の場合、「50億円×2%=1億円」ということではなく、50億円を分解して、 「5億×5%+5億×4%+40億×3%=1億6,500万円」という計算になります。

レーマン方式の種類
レーマン方式には以下のような4つの種類があります。それぞれの特徴について説明します。
・株式方式
実際に譲渡された株式の譲渡対価をそのまま報酬の基準とする方式。報酬額を最も抑えることが出来る。
・オーナー受取額方式
株式の譲渡価格に、会社がそのオーナー経営者や親族から借りている借金の額を加算して報酬の基準とする方式。M&Aで売り手側のオーナーは、会社を買い手側に引き渡した後に、会社に貸していたお金を返してもらうことが出来る。
・企業価値方式
株式の譲渡対価に、借入金残高を加えた額を報酬基準額とする方式。会社を売却したことで株式の売却による資金を得るだけでなく、会社が金融機関などから借りていた負債もなくなるため、その分価値が上がるという考え方によるもの。
・移動総資産方式
株式の譲渡対価に負債総額を加算した金額を報酬の基準にする方法。企業価値方式に買掛金や未払金などの負債が加算された金額が報酬基準額となる。報酬額で言うと、最も大きくなる。
レーマン方式では、方式次第で支払う報酬は大きく変わるため、M&Aの対象となる企業をしっかりと調査した上で最適な選択を取りましょう。
レーマン方式のメリット・デメリットと注意点
レーマン方式のメリット・デメリットと注意点をご紹介します。
・メリット
1.M&Aにかかる費用を大まかに把握できる
2.大規模な案件ほど報酬率が下がる。
3.料金形態が成果報酬のため、成約しなかった場合には費用を払う必要がない。
レーマン方式は報酬率がシンプルな仕組みで構成されているため、M&Aにかかる費用を把握しやすいです。株式の評価額や負債状況を調べれば、実施前から大まかな出費計算が出来、資金計画に組み込むことが可能です。また、大規模な案件ほど報酬率が下がるという点もレーマン方式ならではの特徴です。なお、レーマン方式は制約になった時点で報酬を支払う手法のため、仮にM&Aが成立しなかった場合は、費用を支払う必要がないこともメリットの1つとして挙げられます。
・デメリット
取引金額が小規模な案件の場合、最低報酬額の設定のために、譲渡対価の割に費用が高額になってしまう。
例えば、最低報酬額が1,000万円の場合、取引金額(株価)が5,000万だとして、上記レーマンテーブルによれば「5,000万×5%=250万円」ですが、最低報酬額が1,000万なので、アドバイザー費用は1,000万となってしまいます。この例ですと、アドバイザー費用が譲渡対価の2割に及ぶことになります。このように小規模のM&Aの場合は分が悪くなってしまいます。
一口にレーマン方式と言っても、一律ではなく、最低報酬額や料率の設定、取引金額の定義など微妙に違いがあるので、アドバイザーを選ぶときはこのような点も注意して選定する必要があります。
・注意点
注意点としては、「取引金額」の定義が各社によって異なることです。取引金額を株価としているところもあれば、移動総資産としているところもあります。
株価は株式についた価値の金額なので、売主が受け取る金額が基準になるという考え方はスムーズに受け入れられる場合が多いのではないでしょうか。一方で移動総資産の場合は、株価+負債を取引金額とするという考え方です。当然ながら取引金額は株価だけの場合より大きくなり、アドバイザーに支払う費用も膨らみます。売り手は株価レーマン、買い手は移動総資産レーマンと分けて設定されているケースもあります。
また、レーマン方式では最低報酬が設定されている場合が多いです。この最低報酬金額も各社各様ですので、事前に確認しておきましょう。
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など