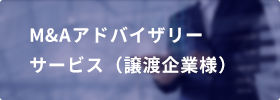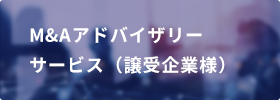M&A情報
後継者不在の解決策としてのM&A
2021.09.30
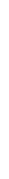
大廃業時代。後継者不在は、わが社だけではない。
日本の企業は、全約380万社の内、97%がファミリー企業と言われている。旧来より、家を守る文化が日本には強くあるが、全国各地で2代目・3代目と、祖父・父の代から親族で事業承継して経営を繋いでいる企業が多い。特に、中小企業はほとんどがファミリー企業である。
しかしながら、昨今、"後継者不在"という課題が顕在化してきている。背景には、子供がいないことや都市部一極集中で地方へ帰ってこない、価値観の変化から跡を継がせない等、様々な要因は想定されるが、中小企業360万社の内の約3分の1にあたる127万社が後継者不在と言われている。
経営者の年齢も上がっていく中で、"息子に継ぐ"という選択肢を取れない経営者は、早急に事業承継の方法を考える必要があるのではないだろうか。

事業承継の選択肢は、廃業か売却。 売却は悪か?
企業の進む道は4つしかない。①存続か、②倒産か、③廃業か、④売却である。
この内、健全な企業で後継者不在の場合は③or④の選択肢から選ぶことになる。
売却(つまりM&A)という手法は、以前よりもイメージが変わってきているとはいえ、地方ではいまだにネガティブなイメージを持つ経営者は少なくない。
結論からお伝えすると、「M&Aは企業を存続させる最も有効な手段の一つ」であると言える。
これは、選択肢の ③廃業と④売却を比較すると明白である。
例えば、従業員の雇用継続は廃業では不可だが、売却では可能となる。
得意先・協力先の継続取引も同様、廃業では不可だが売却では可能だ。
オーナーの手残り資金で考えると、棚卸資産や設備などは、廃業だと一般的には処分価格となるが、売却では簿価で取引されるケースが多い。金融機関からの借入金は、廃業では当然返済が必要だが、売却では引継ぎの上で個人保証も解除される場合がほとんどである。
つまり、結果として廃業と売却を比較すると、従業員の雇用継続・取引先の継続という社会的貢献と、オーナーの手残り資金という経済性の両面から、売却という手法が優位である場合が多いのである。

事業承継にM&Aという選択を、経営をつなぐM&A
「こんな田舎の中小企業を買いたいという先はあるのか?」という声を良く聞く。
田舎でも、赤字や債務超過であっても、買い手が現れる可能性はある。なぜなら、会社の価値をどう感じるかは、企業によりそれぞれ違うからである。
実際、筆者は何社も赤字・債務超過企業の成約実績があるが、"技術・ノウハウ"、"エリア・商圏"、"取引先"などに魅力を感じられ、成約に至っている。
M&Aの取引形態は様々あるが、中小企業の場合はほとんどが株式譲渡か事業譲渡のどちらかとなっている。
株式譲渡というのは、オーナーの保有する会社の株式を譲渡し、経営権を譲り渡す手法である。
事業譲渡は、会社の法人格は残したまま、事業(取引や従業員、設備 等)のみを売却する手法である。
この2パターンの内でも、株式譲渡の方が多く選択されている。なぜなら、株式譲渡は自社の状況を全く変えることなく売却できるシンプルな取引であるからだ。例えば、社名を変える必要がない、従業員との雇用契約をし直す必要がない、取引先との契約を締結しなおす必要がない、等である。(一部例外を除く)
実際に、株式譲渡を行っても社名を変えないケースは増えてきており、そうするとM&Aが行われたことすら外部からは分からないということもある。
M&Aをするなら、良い相手先と適切な条件でするべきである。
そのためには複数の選択肢(候補先)を持ち、条件比較ができるという状況がベストだと考えられる。もちろん、特定1社との相対取引が悪いということではないが、一般論では情報が多いに越したことはない。
そのような、モテる状態に持っていくためにはどうしたら良いか?を最後に記載する。
ポイントは、買い手側がリスクと感じることを減らす。ということにある。
1.不正がないか。
粉飾決算や、法令順守違反、社会保険未加入、租税滞納 等があると、どんな会社も買いたいとは思わないだろう。
2.株式の分散、取りまとめ可能か。
株式を100%譲渡するという取引が前提となる場合が多いため、遠縁の親族に分散していたり、取りまとめ困難な状況だと、そもそも取引の実行ができない。
3.会社と個人の分離ができるか。
オーナーや親族の自宅、自動車、貸付などはないか。逆に個人所有の事業資産はないか。あるとしたらM&A取引にあたり綺麗に整理ができるか。
4.社長に過度に依存していないか。
社長が辞めると取引がなくなる、従業員が辞める等の可能性は買い手側が気にするポイントの一つである。過度に依存をしているようなら幹部社員へ徐々に移行体制を取っていくか、M&A後の円滑な引継ぎプランを考える必要がある。
5.自社の魅力と適正条件とのバランス
自社の売りはどこにあるか?大手との取引、優秀な技術者、独自製品、商圏、安定した収益など様々あるポイントから自社の売りを考える。また、その自社の魅力と財務内容を掛け合わせたのが売却代金となるので、高望みしすぎない適正な条件かどうかも重要である。
人はいずれ死ぬが、企業は生き続けられる。
経営をつなぐために、後継者不在の場合はM&Aという選択も検討してはどうだろうか。
トピックス:M&A以外の選択肢
本項では後継者不在の企業が取るべき道としてM&Aによる事業承継について言及しておりますが、参考までに、M&A以外の選択肢についても少し掘り下げたいと思います。
●社員から承継者を探す
本項では家族や親族への事業承継について触れていますが、従業員から承継者候補を探し、事業を譲渡するケースも存在します。
従業員であれば事業理解は十分であり、社内や取引先、融資機関の理解を得やすいのがメリットですが、大きな課題があります。それは承継者候補の資金問題です。オーナー経営者の場合は経営権の譲渡にあたり、株式の譲渡も伴います。すると承継者は株式取得のための資金が必要となりますが、その十分な資金を持っていない場合が殆どです。融資も断られた場合はその後継者への承継を断念せざるを得なくなります。譲渡対価を減額して対処する場合もありますが、現経営者のリタイア後の資金が減るため事業譲渡をするメリットが小さくなってしまいます。
●IPO(株式公開)
自社株を市場に公開し、上場させることも選択肢の一つではあります。会社の知名度が上がり社会的な信用を得ることで、より良い後継者を社内外から募ることが可能となります。また、自社株売却による利益で、リタイア後の資金が最も大きくなるのがIPOです、しかし、言うまでもなくIPOには数年単位での準備期間や多額のコストがかかります。その上成功確率は低く、中小企業経営者が単純にリタイアや事業承継のために行うにはハードルが高すぎる選択肢です。


小野 樹
M&Aコンサルティング事業部
ゼネラルパートナー
金融機関や会計事務所とパートナーシップを築き、後継者を育成する企画や取引先企業が抱える経営課題とコンサルティングソリューションをマッチングするアライアンス事業を推進。M&A部門の事業化、仕組みづくり、商品開発、実績づくりを行い、大手企業のバイサイド支援から中小・個人企業のセルサイド支援まで幅広い実績を持つ。
- 主な実績
-
- 大手生活品メーカーの同業買収に関するバイサイドFA
- 中小システム開発会社のM&Aアドバイザリー
- 中堅建設業の同業買収に関してのデューデリジェンス
- 地場ゼネコンのM&A戦略構築支援
- リサイクル関連会社の企業買収に関するセカンドアドバイザリー
おすすめ記事
最新記事
M&Aお役立ち資料

"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル
~サービス概要~
総合経営コンサルティングファームだからできる"経営をつなぐ"唯一無二のM&Aコンサルティングモデル。本資料ではサービス概要から近年のM&A市場動向、コンサルティング事例までをご紹介します。

事業承継・M&Aを成功させる
ための事前準備チェックリスト
譲渡に向けて事前に準備はできていますか?譲渡企業向けにM&Aを成功させるための事前準備チェックリストをぜひご活用ください。

2023年度 M&A・事業承継に
関するアンケート
2023年に実施したアンケート調査から見えてきた各企業が考えるM&A、事業承継とは?
アンケート結果をもとに企業が抱える課題を解決する「成長M&A」のポイントについて解説します。
関連記事
相談会
事業承継・M&Aに関する相談会
- 事業承継期を迎えているが後継者がいない
- 成長が鈍っている事業の譲渡を検討している
- 資本力を得て、もっと会社を成長させたい など