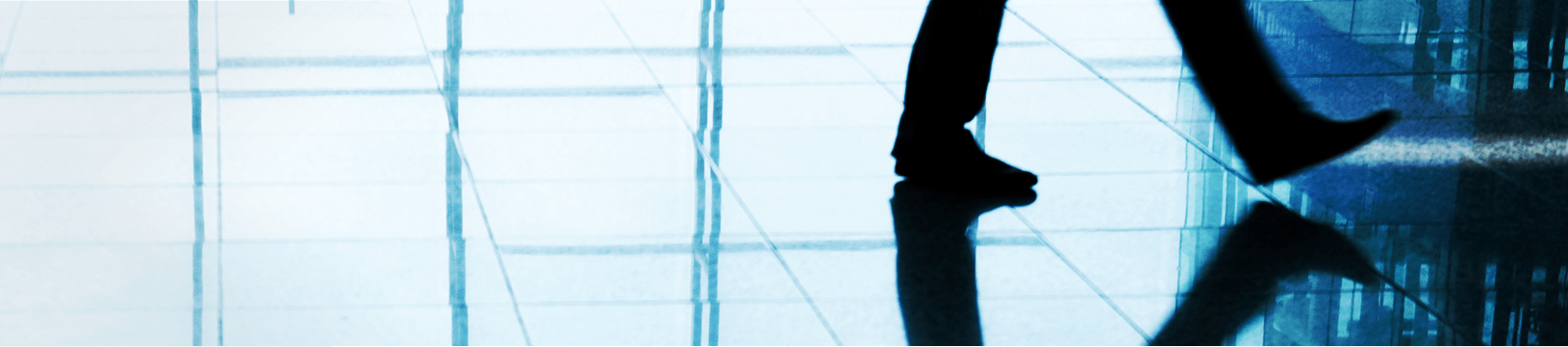ウェルビーイング経営とは
人事の世界で徐々に市民権を得ている概念にWell-being(ウェルビーイング)という言葉がある。
ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に良好で、仕事もプライベートも満たされている状態を指し、これらが満たされていくよう組織としての環境を整えていく手法をウェルビーイング経営と言う。
昨今、働き方改革やDE&I(ダイバーシティエクイティ&インクルージョン)や健康経営に注目が集まる中、すべての施策の共通目標である「幸せ」の実現に焦点を当てたウェルビーイング経営を自社の経営戦略として取り入れる企業が増加傾向にある事を日々のコンサルティング現場より実感している。

単一的ウェルビーイングと集合的ウェルビーイング
従来は、社員一人一人が身体的・精神的・社会的にも満たされるように向き合う概念として、「単一的なウェルビーイング」を中心に考える企業が大半であった。
単一的ウェルビーイングへのアプローチはどこまでいっても個人が身体的・精神的・社会的に満たされているかどうかの追求に終始するため、組織に対するインパクトとしては弱い。
近年では、ある目的に対して集合したチームがお互いに配慮・尊敬し合いながら、ウェルビーングと向き合う概念である「集合的ウェルビーイング」への関心にシフトしつつある。
集合的ウェルビーイングの特徴としては、以下のような視点が挙げられるため、自社のウェルビーング経営を考える上でご参考いただきたい。
・この組織・チームとして育んでいきたい幸せに対する世界観が明確である
・この組織・チームとしての幸せを追求するための価値観が明確である
・お互いのウェルビーングに対する敬意や配慮があり、一体感や繋がりを感じられる

ウェルビーング向上を通じた企業価値の向上(事例研究)
ここでいくつかのエビデンス(根拠)をご紹介しておきたい。
「ハーバードビジネスレビュー」において発表された研究結果では、幸福感の高い社員は、そうでない社員と比べて創造性は3倍、生産性は31%、売上は37%高いという結果が出ている。
また、「ウェルビーング活動と企業業績に関する実態調査」では、ウェルビーングに対して取り組んだ企業は、売上高や営業利益がウェルビーングに取り組んでいない企業と比べて上昇率に約2倍の差が出る結果となった。(N=500社)
TOYOTAでは、単に車の生産台数の維持を目的にするのではなく、「幸せを追求することで、結果がついてくる」をポリシーとして掲げている。
味の素では、ウェルビーングが浸透する以前から「味の素で働いているだけで健康になる」を目指し、健康診断の見える化や全社員面談を通じたメンタルヘルスサポートを継続実施されている。
筆者のクライアント先のA社においても、「共に働く社員のプライベートが充実していないければ最高のパフォーマンスは発揮できない。」を全社の価値観として強く訴求されており、直近期最高益を実現している。
押さえていただきたいのは、ウェルビーング経営が企業成長の後押しに繋がっているという相関関係である。

ウェルビーング経営の実践に向けて
さいごに、ウェルビーング経営の実践に向けて何より大切になるのが、経営層や経営幹部の「ウェルビーング・リテラシー」の強化である。
※ウェルビーング・リテラシーとはウェルビーングに関する知識やウェルビーングを理解しようとする力を指す。
経営層や経営幹部が心底理解せずして、組織への浸透はあり得ない。
最近では、CHOを単に(Chief Human Officer=最高人事責任者)として捉えるのではなく、CHO(Chief Happiness Officer=最高幸福責任者)として捉え、役割発揮する企業も増えてきている。
自社で働く社員の「幸福」という観点に対して、どれだけのこだわりや想いをもって、向き合っていけるかがポイントとなる。
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部 エグゼクティブパートナー浜西 健太
- 主な実績
-
- 大手IT業:人事制度再構築コンサルティング
- 大手建設業:人事制度再構築コンサルティング
- 大手卸売業:人事制度再構築コンサルティング
- 中堅美容業:人事制度再構築コンサルティング
- 中堅介護福祉業:人事制度再構築コンサルティング
- 中小製造業:中期ビジョン策定コンサルティング
- 中小サービス業:マーケティングコンサルティング
- 中小製造業:マーケティングコンサルティング
- 中小サービス業:採用コンサルティング


 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト