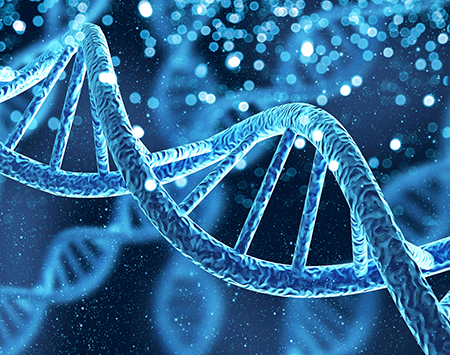人事コラム
ビジョン実行・ビジョン実現型の組織をつくる
~ビジョンを実現するために、風土と人を育み、マネジメントシステムを稼働させる~
組織戦略について

コンサルティングの現場では、固有名詞が先に挙がりそこに役割と責任を当てはめてゆくアプローチが見られる。換言すれば、未来志向で実施するべきテーマを掲げながらも、現実は実行できそうな社員、または取り組んでくれそうな社員に可能な限り実行してくれることを期待しながら、組織図に展開する方法である。
このアプローチでは毎年同じ組織になる。また散見されるのは、部門名を"それらしく"変えながらも、実際は先述の様に設計してゆくことである。『何をやるかも重要だが、それよりも誰がやるのかの方が重要』とは、コンサルティングの現場から得られる教訓である。
ここで皆様と共有したいことは、『何をやるのか』を合理的に決定しながらも『誰が』やるのかを決める際に、人柄やこれまでの実績を先行させながら、ある意味で現実的に決めてゆくと、特定の人材に依存した非常に脆い組織になってしまうということである。
このアプローチには、組織の成長発展という観点が欠落している。組織の力で何を成し遂げるのか?組織の連携でどの様に実行するのか?そして、どの様な経験を重ね組織として成長するのかが重要である。これらに期限、担当、役割、責任を設定するのが組織戦略の前提となる。
ビジョン実行・実現型組織のスタートはビジョンの浸透と理解
シンプルに申し上げれば、ビジョンと数字を理解できている社員の人数が多い組織が強いと考える。また組織の中にポジティブに考える方が多い方が実行スピードが早く、また上手くいかなかった際の代替案が出てくるスピードが早い。多くの企業が内包している課題は「経営の実効性が低く、企業の生産性・効率性も低い」という点で共通している。
筆者のコンサルティング経験からも同様に考えており、人事考課、分配を含むマネジメントの仕組みは、評価や福利厚生に視線が落とし込まれ、『ビジョン実行・実現型組織』がテーマとして挙がるものの、置き去りにされている事実がある。
今一度『ビジョンは組織行動で実現する』という視座を持っていただきたいと考える。このために2点の重点事項がある。
①採用~プレゼンスの発揮~育成力を持たせる~定着のフローを再設計
採用に関してはどちらの企業も工夫されて取り組まれているが、採用後の放任が目に付く。多様性とはいうものの 辻褄合わせのOJTであったり、"社内下請け"の様な扱いをしたりと目に余るのが現状だ。 個々のプレゼンスを発揮させ、そのテーマにおいてはリーダーシップを発揮させる場面を用意するのが、経営陣の 役割だと言える。その後に人を育てるという仕事をどんどん若手に経験させ、そこを評価していただきたい。
②ビジョンの浸透
まずは、少なくともわが社のビジョンを知っている状態にすること。現場の社員が『何故この組織になっているのか』
を知らされないまま組織図を見ても自身の名前がどこにあるのかを見て、同僚、先輩、後輩、上司を見てそれで
終わってしまう。組織図は学校時代のクラス編成ではなく、ビジョン実行組織であり、コミュニケーションパイプ
(指示命令系統)である。
ビジョンとはわが社のあり方であり、そこに向けての推進体制が組織である。したがって、組織編成の由来はビジョンに
たどり着く。この重要な理由の周知を徹底したい。
組織力の不確実性を前提条件にし、再現性を高める

コンサルティングの経験から、組織図で設計した通りにすべての部署が機能している企業は多くはない。組織内に問題が発生する度に対応してゆくのでは、年中人と組織に振り回される。これに加えキャッシュフローへの対応が加われば、組織と人が置き去りになり、組織内に内包する問題への対応全てが後出しになる。この様な状態になると『ビジョン実行・実現型組織』からかけ離れた状態になる。
まずは自社の組織力の実態をつかみたい。個別面談から始まり、SWOT分析、モラールサーベイ、最近では社員のエンゲージメントを図る分析手法もある。これらの分析の目的は、組織内に問題を発生させている部門や個人を特定するのではなく、何が組織内の実行の足枷になっているのかを検証し、手を打っていくことにある。すべてを精神論や正論で片付ける、またすべてを合理的に解決できることもない。折り合いをつけてゆくのは、どこまでいってもわが社のビジョンにある。ビジョンに対しては上下関係はない。
再現性に関して、換言すれば、特定の社員や部署に依存しない組織をつくることである。ここに関しては今一度社員育成を見直していただきたい。筆者の経験から、70%の企業が新入社員研修以降の研修が機能していない。研修の足並みを揃える。カリキュラムを自社のビジョン実現に向けた内容と未来に必要なスキルのインプットに合わせる必要がある。
組織戦略とは、ビジョン実現と実行に焦点を合わせ、採用~プレゼンス発揮~育成力醸成~定着~安定活躍のストーリーを構築し、個が互いに刺激し合う環境を整備することにあると考える。多様性とはよく使われる言葉であるが、我流の成長には限界があり、個の特徴を活かしあうことが思いもつかない成果を上げられ、一人でできないことがチームであれば提案と提供ができる事実を体験させることで、真に多様性を受容することができるのだと、筆者自身の経験から考えている。