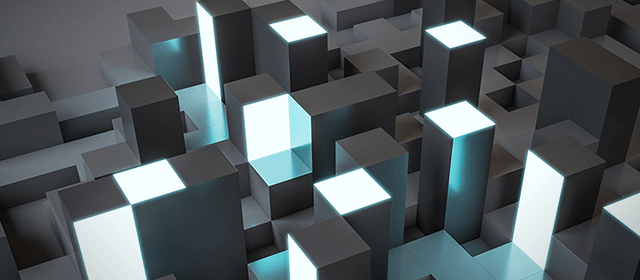人事コラム
“人生100年時代”を見据えたシニア社員を活躍させるシニア人事制度とは
年齢を軸にした一律に賃金の引下げや、安易な職務にスライドさせるなど近視眼的な制度に陥っていませんか?
多くの企業が陥っている年齢を軸にした処遇決定からの脱却

2021年4月に施行された高年齢者雇用安定法に伴い、各社65歳までの雇用確保措置の対応が求められている。
我が国における高齢化問題・生産年齢人口の減少などの諸問題を鑑みると60歳以上の社員(以下シニア社員)の生産性を最大化していく事が未来の企業繁栄を考える上では必要不可欠である。
しかし多くの企業では依然として法対応(就業機会確保等)のための制度運用に留まっており、シニア社員のモチベーションアップ・成果に着眼を置いた制度になっていない。
定年後の一律賃金引下げや、安易な職務にスライドさせる制度ではモチベーションを低下させるような制度に陥らないために、制度構築をしていく上で押さえておくべき視点を下記に3点に示す。
シニア社員の活躍に着眼を置いた制度設計の3つの視点
- 目的の明確化
- 大前提として、何のためにシニア向けの人事制度を設計するのか、その目的を明確にする事が重要である。制度設計を進めていく中で選択を迫られることは多くあるが、迷った際に目的に立ち返る事で、軸(目的)のぶれない制度にする事が出来る。また、シニア向けの人事制度設計をすることが、そのまま会社から社員へのメッセージとして活用することができる。
- 賃金制度設計
- シニア社員のモチベーションアップを踏まえると報酬を上げていく事も必要であるが、現実的にすぐに原資を捻出する事は難しい。現役世代の各種手当の支給定義見直しなど現役社員とシニア社員とのバランスを見ながら賃金制度を設計する必要がある。場合によっては抜本的な賃金制度改革に踏み込んでいく事も選択肢の一つである。いずれにせよモチベーションを考える上では少額でも本人の成果や役割(貢献)に報いる賃金制度を構築する事が重要である。
- 支援体制の仕組化
- 制度設計だけではなく、支援体制についても検討しておく必要がある。まずはシニア社員と上司がコミュニケーションをしっかりと取る事が必要。シニア社員は若手社員よりも仕事に対する考え方が多様化する傾向にあるが、仕事に何を求めているのか上司が理解出来ていないケースが多い。まずは個々に向き合い対話する時間を年間スケジュールの中に組み込み、ヒアリングした内容から役割の難易度や処遇について再検討するきっかけにして欲しい。
これから本格的に人生100年時代を迎える我が国においてこれらの視点を踏まえ、自社にとって最適な制度を模索してみてはいかがだろうか。