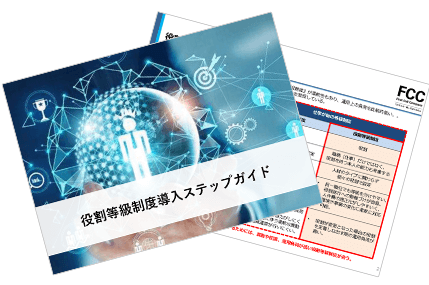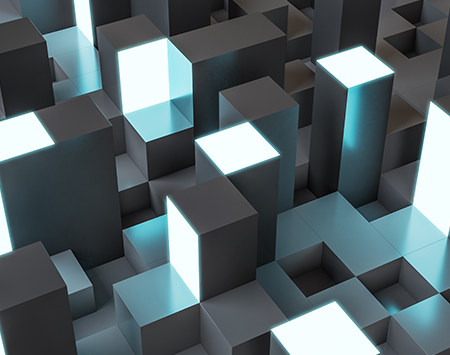役職と等級の分離運用について理解し、
自社に最適なカタチを見つけ出す

役職と等級の基本概念
役職と等級は、組織において社員の位置づけや役割、給与などを決定するために用いられる基準です。これらは似たような役割を果たしますが、目的や活用方法に違いがあります。
1. 役職(ポジション)
(1)定義:
社員が組織内でどのような職務や責任を持つかを示すもの。(例:課長、マネージャー)
(2)目的:
組織構造を明確にし、業務における責任範囲や意思決定のレベルを示す。
(3)特徴:
一般的には役職が高くなる(昇進)につれ、意思決定権や責任範囲が広がる。
2. 等級(グレード/レベル)
(1)定義:
社員のスキル、経験、業務遂行能力に基づいて分類されるもの。
等級やグレードで表現されるものもあれば、いくつかの等級をまとめてステージと表現することもある。
(2)目的:
主に給与や昇進の基準として活用される。
役職が同じであっても、等級が異なれば給与水準や待遇面が変わる可能性がある。
(3)特徴:
一般的に等級は、経験年数や業務遂行能力、実績に応じて決定される。
これはキャリアパスや社員の能力開発計画にも活用され、等級が上がる(昇格)することにより、社員はより高い役割を発揮できることを認められたと捉えることができる。

役職と等級を分離させる理由
人事制度において役職と等級を分離する理由は、組織の柔軟性を高め、より公平かつ効果的な人材配置を行うためです。メリットとしては下記が挙げられます。
1. 組織の柔軟性を高められる
役職と等級を分離させることで同じ職種内でも異なる等級の人材を配置することができます。例えば、同じマネージャーという役職でも、業務の難易度や規模に応じてシニアレベルやジュニアレベルのマネージャーを配置でき、組織にとって最適な人員配置を柔軟に行うことができます。また、組織を再編成する際には、等級を軸に役職のみ調整することで対応が可能です。
2. 評価・昇進・昇格の透明性と公平性を高められる
役職ごとの業務の種類や責任範囲を明確にしつつも、昇格や昇給は等級に基づいて決定することで、業務内容とスキルを分けて評価できるようになります。この仕組みによって、社員の業務遂行能力や成果を正当に評価することが可能になります。また、キャリアパスが明確になることにより、社員がキャリアビジョンを描きやすくなります。管理職としてマネジメント業務に携わるのか、一方で専門職として専門性を磨いていくのかなど、社員自身の意思を尊重することができるため、企業に対する帰属意識の向上も見込まれます。
3. 若手社員の活躍を促進できる
等級と役職を分離させる大きなメリットの一つが、若手社員の活躍促進です。役職と等級を分離させることで、若手社員でも適性があれば役職に就くことができます。それによって若手社員の早期活躍を支援し、企業としての新陳代謝を高めることができます。

役職と等級の効果的な運用方法
役職と等級の分離運用は、適切な運用方法をとることで組織内の人材管理や社員のモチベーション向上に寄与できますが、同時にいくつかの注意点が必要です。
1. 効果的な運用方法
(1)役職要件と等級要件の明文化
各等級で必要なスキル・経験の明文化と合わせて、各役職における役割や責任範囲を明文化させることによって、社員の更なるキャリア開発を効果的に支援することができます。
(2)キャリアパスの複線化
管理職を目指す道と専門性を高める道の複数のキャリアパスを構築します。それによって、社員が自身のスキルや目標に応じたキャリアを描くことが可能になり、幅広い人材の育成・成長を支援することができます。
(3)報酬制度の最適化
報酬制度は、等級や役職に基づいて設定し、能力・役割・成果・責任に応じて報酬が決定するようにします。
それによって、社員のモチベーションを引き出し、より活躍を支援することができます。
2. 注意点
(1)役職と等級の混同
先述の通り、役職要件と等級要件をそれぞれ明文化することが必要です。これらが混同してしまうと、評価が曖昧になってしまい、社員が自信の立場やキャリアパスを誤解する恐れがあります。
(2)役職と等級の不均衡を防ぐ
昇格しても昇進しない場合、社員が「役職が変わらないのに役割が増える」と感じるリスクがあり、不満が生まれる可能性があります。そのため、昇格した際には、役割範囲についても目線合わせする必要があります。
(3)人事評価の公平性の確保
役職と等級の評価基準やプロセスが異なる場合でも、評価の公平性を確保しなければなりません。評価が一貫性を欠くと、社員のモチベーションは低下し、信頼関係が崩壊してしまう恐れがあります。
さいごに
役職と等級を分離して運用することで、組織はより柔軟で公平な人材配置を実現でき、社員のモチベーションや成長を効果的にサポートできるようになります。この制度は、社員が自身のキャリアパスを明確に描きやすくするとともに、多様なキャリアの選択肢(成長機会)を提供することにも繋がります。役職や等級に基づく評価や報酬の透明性を高めることで、組織の一体感と信頼が醸成され、活気ある組織が生まれやすくなります。
適切な運用によって、社員一人ひとりのスキルや能力を最大限に引き出し、組織全体の成長促進に繋げていきましょう。
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
コンサルタント稲垣 咲香
- 主な実績
-
- 中堅電機工事業:人事制度運用支援、採用戦略
- 中小物流業:人事制度再構築コンサルティング
- 中小商社:人事制度再構築コンサルティング
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト