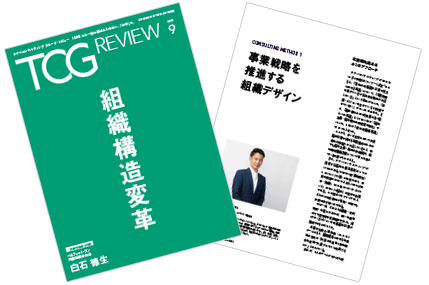人事コラム
組織カルチャーの変革ポイントとは?
組織カルチャーを育むことが、これからの時代を生き抜く企業の競争優位の源泉となる。

組織カルチャーの必要性
かつての日本企業の多くは「三種の神器」と呼ばれる年功序列、終身雇用、企業別組合に基づき、日本的経営によって企業基盤を固めていた。
組織マネジメントの在り方についても「大家族的」であり、組織と個人はひとつの共同体である事を前提に企業として成長していた。
高度経済成長の中、大量生産・大量消費が前提でモノを作れば売れる時代であれば上手く機能していたのかもしれないが、現代においてはどうだろうか。
「社員は会社の方針に従う」、「社員は時間を惜しまず一生懸命働く」などといった旧来的な組織マネジメントの考え方では企業の優位性を損なう原因にもなり得る。
先行きが不透明な時代だからこそ、同質的な人材ではなく多様な人材を受け入れ、透明性のある組織マネジメントを目指す事が重要であり、「組織カルチャー」を見直すという新たな経営技術を経営者や人事責任者が身に付ける事がこれからの時代を生き抜くためには必要になると考える。

組織カルチャーの定義
組織カルチャー(文化)と似た言葉として組織風土というものがある。
それぞれ目に見えないものであり定義し難いものであるが、タナベコンサルティングでは、
組織文化:ルールやツールを使用し、意識的に"育む"もの
組織風土:文化が浸透し、無意識に"行動に表れている"もの
としている。
このように定義してみると、組織風土は時間をかけて醸成されていくものに対して、組織文化は仕組みやルールを整備していく事で意識的に育むことができるものとして捉えることができる。

良い組織カルチャーを育んでいる企業の3つの特徴
1. カルチャーフィットに徹底して向き合う
⇒良い組織カルチャーが育まれている企業の特徴として、採用活動を通じて企業のこだわり、価値観、考え方がフィットしているのかを見極めている。
また、入社後も個人面談などを通じて社員が向かう方向性と会社としての方向性が揃っているのかを定期的に振り返る仕組みも必要である。
2. "アイデンティティ"を軸にした自社なりの組織カルチャーの再定義
⇒組織カルチャー自体を他社から真似して取り入れることはできない。
組織カルチャーはその企業毎のアイデンティティ(個性)によって育まれるものであり、独自性が組織カルチャーとなり、結果的に社員の帰属意識を高めていくことに繋がる。
3. 新たな成功体験の創出
⇒組織カルチャーは創業時の理念・志から脈々と受け継がれていることが大半である。
しかし、経営理念は不変的なものに対して、組織カルチャーは可変的なものである。
つまり、経営理念は大事にしつつ、新たな成功体験を積み上げていくことが良い組織カルチャーを育むことに繋がる。
社員一人ひとりが理念やビジョンを自分事として捉えることがカルチャー浸透に繋がる。
さいごに
組織カルチャーは目に見えづらく曖昧なものであり、組織カルチャー改革に取り組んでいる企業はまだまだ限られている。
そのような背景のもと、タナベコンサルティングでは「新しいものを生み出す組織カルチャー研究会」を発足し、定期的に経営者や人事責任者など、複数の組織カルチャー改革に取り組もうとしている方々と実際に組織カルチャー改革に取り組んでいる実践企業に訪問している。
訪問企業はエリアや企業規模や業種を設定せずに、幅広い視点から学びを深める場となっている。
「ビジョンや方針に対する共感が得られていない」、「様々な施策や制度を導入しているがなかなか浸透しない(上手く機能していない)」などに悩まれている場合は、ぜひ参加を検討していただき、組織カルチャー改革に向けたヒントを掴んでいただきたい。
本事例に関連するサービス

組織・人事制度診断コンサルティング
部分的改修ではない、人事戦略・経営戦略と連動した人事制度構築・人事施策のために健康診断(現状認識)を通じて、課題の改善具体策およびプライオリティ(優先度順位)を明確にします。
組織・人事制度診断コンサルティングの詳細はこちら関連動画
関連情報