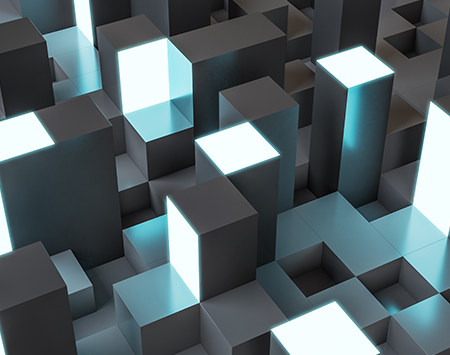人事コラム
経営者のための『戦略人事』入門
〝アフターコロナ〟を戦い抜くために業績をつくる人事へとアップデートする。
はじめに
この度、経営コンサルティング本部 九州本部 古田勝久 執筆の「経営者のための『戦略人事』入門」がダイヤモンド社より刊行致します事をご案内申し上げます。
書籍刊行に先駆け、執筆した古田勝久に著書への思い、そして"戦略人事"についてインタビューしました。
これからの人事部・HRとはどのような組織になっていかなければならないのかを熱く語っていただいております!
経営者必見の内容となっておりますので、ぜひご一読くださいませ!
これまでのキャリアを教えてください
大学卒業後に、愛知県にある自動車部品メーカーに就職しました。そこで主に人材育成を中心に、人事領域の業務に携わってきました。
もともと、大学時代は教育学部に所属しており、人材・組織に興味があったこともあり経営に寄与する人材育成に強く興味を持つようになりました。
その後、地元・九州の食品製造・販売の会社に入社し、採用や教育、人事全般に関わる機会を得る事ができました。その中で、次世代経営人材を育成するプログラムを企画・開発する機会があり、経営についてさらに強い関心を抱くようになり、タナベコンサルティングへ入社しました。
人事業務全般を網羅されたキャリアを歩まれ、そこで気づいたことは何でしょうか?

人事が経営者のパートナーでなければならないということです。これまで、特にコロナ前までは、人事制度を設計・運用する、勤怠管理・給与計算などの定型的な業務を行うという印象が強い部署でしたが、これからの人事部には会社にイノベーションを起こす役割も求められてくると強く感じています。
多様な人材・働き方を受け入れ、人材を育成・定着化させ、活躍できる機会と職場を人事部がつくることでイノベーションを創出し、コロナ後でも持続的に成長できる新しい組織として会社が生まれ変わることができるからです。
人事が定型業務・インフラ運用だけではなく、経営戦略に直結する機能を担い、経営のパートナーとして企業成長に貢献することが理想の形となるのではないでしょうか。
人事・HR領域はまさに経営に直結する機能という事がわかりました。今回、"戦略人事"というテーマで書籍を刊行されましたが、なぜこのタイミングで執筆・刊行されたのでしょうか?
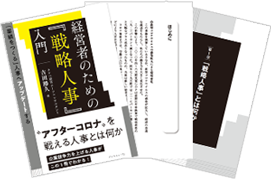
新型コロナウイルスの感染が広がり始めたことにより、「対面接触しない」とう守り(リスクヘッジ)のために、多くの企業がテレワークやシフト勤務など、出勤しないという働き方を半ば強制的に導入されました。
もともと働き方改革の流れもあって、一部の企業ではすでに制度としては導入されていましたが、それは、多様が働く中で、会社に集まり仕事をする働き方が大多数の中で、育児や介護が理由でそれがかなわない一部のマイノリティを対象にしたものが大半でした。それが急に、一律的に全員対象になったことは大きな環境変化だったと思います。当初はどの企業も「その場しのぎ」「いつかは元に戻る」と思っていたことと思います。
ところが、新型コロナウイルスの影響が長引き、政府からはニューノーマル(新しい生活様式)が提言され、満員電車で通勤、会社に集まって仕事をする、対面での営業活動、飲ミニケーションなど、これまでの常識は通用しなくなってきました。つまり、その場しのぎと思っていた働き方は、新しい働き方として定着していくことになったのです。そしてこれに対応しなければ、社員は働くこともできず、経営が成り立たないという状況に追い込まれたわけです。
ここが、人事が戦略性を求められるようになったターニングポイントです。
経営資源である人材に、どう働いてもらい、どう育成し、どう評価していくのか。コロナ後の環境に適応した人材マネジメントが出来ないと、会社が存続できない状況になって、人事が管理機能ではなく、戦略的にマネジメントをする機能へと変化しなければならない状況になったのです。
では、経営に直結する人事の在り方はどのようなものなのか。
戦略的な人事とは何か、まさに今、経営者に伝えたい。
そしてコロナ禍であっても100先も一番に選ばれるファーストコールカンパニーを1社でも多く増やしたいと思い執筆しました。
コロナ禍でニューノーマルが提言され、これまでの常識が通用しなくなった時代、この戦略人事が及ぼす企業や社会的影響はどのようなものなのでしょうか。

企業や社会に大きなイノベーションを起こすことが出来ると考えています。これまでの管理型人事と戦略人事の一番の違いは、経営に直結するかしないか、という違いがあります。そもそも、新型コロナウイルスだけではなく、働き方改革による多様な人材の確保、少子化による人材不足、人材の流動性の高まりなど、働く人の価値観や人材の関する経営環境は変わっていきました。
ところが、新卒一括採用など、同質化・一律化というこれまでの日本の人事の常識は(結果的に)変わることなく今に至っています。しかも、人事施策が目標を達成できなくても、即経営に影響があるという事は少なく、特に事業戦略を検討する場に人事部長がいないという事も珍しくはなかったと思います。
しかし、今からは経営を止めない為の人事をしていかなければ新しい環境に適応できず、会社が存続できない状況になっています。
環境適応の1つに、多様な人材・働き方を認めることが挙げられると思います。多様な人材が集まれば、今までと違う視点やアイデアが組織の中に生まれ、意思決定にも多様性が生まれるとイノベーションの創出が期待できます。
人事が経営に直結する機能として役割を発揮できるかどうか、それは人事の在り方そのものについて経営者が考え方を変えられるかどうかにかかっていると思います。例えば、新卒採用にしても、広報解禁や入社日をすべての企業が横並びで行う事が競争力強化や差別化になるのでしょうか?このような「今までの常識」から変えられるかどうかということです。しかし、新卒を通年採用したい、採用活動は独自のスケジュールでやりたいといっても、すぐに一社では対応できるものではありません。求職者(就活生)の動きもあるからです。結局、社会全体がその仕組みや方法論について変わっていかなければなりません。そこを先駆的に取り組んでいけるかどうか、まさに経営者の「決断」ですね。社会全体がこのような価値観の変化に対応していければ働く人の多様性も高まり、結果的にイノベーションが起きやすい世の中になっていくと思います。
読者にこの本を通じてどのような姿になってほしいでしょうか。
読了したときに、経営者の人事に対する価値観が変わっている事を望みます。前段でもお伝えした通り、これからは人事が経営のパートナーとならなければなりません。経営を取り巻く環境が変わっている中で、「人事=事務、管理をする機能」ではなく、「業績に直結する戦略部門」という位置づけとして認識を新たにしていただきたいです。
書籍のなかでは、採用、処遇・評価制度、育成について改善の方向性を具体的に述べています。最終的には自社のミッション、事業戦略と照らし合わせて「自社の戦略人事」を描いていただきたいと想っています。
ありがとうございました。最後に一言お願いいたします。
これまでの常識が通用しなくなったこの時代、人事は企業の存続に直結する機能といっても過言ではないです。
戦略人事を実現できるかどうかは、経営者のパラダイムシフトから始まります。この書籍をきっかけに、自社の戦略人事を実現し、ファーストコールカンパニーになりましょう。