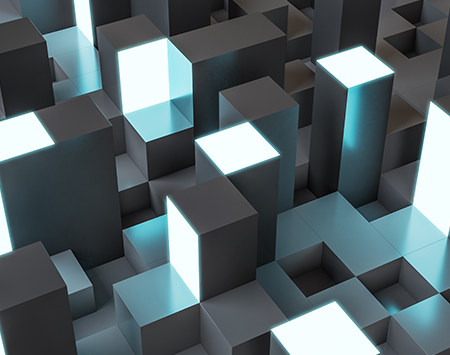人事コラム
等級間の差がわかりにくく、
実力や成果の出ている社員でも下位に配置されている
実力や成果に応じたメリハリのある評価制度を運用するには?
評価制度を点検する

等級間で評価の差が分かりにくい主な要因は、①年功要素が強く実力や成果を出した社員にメリハリのある評価を与えることができない、②企業規模の拡大や会社のビジョンが更新されているにも関わらず評価制度が更新されていない、③評価者の教育不足、以上3点が考えられる。
①について、日本企業の多くは職能資格制度をベースとした"能力基準"の人事制度を運用しており、一定の時間を経て能力が向上することを前提としているため、メリハリのある評価がしずらい環境にある。また、ある企業では等級数が多すぎて、その差が分かりずらいということも発生している。②については、企業規模や会社のビジョンが変われば求められる社員像も変化する。そのため、評価制度も変更しなければ過去の基準に沿った"あいまい"な評価を下すことになり、活躍人材が評価されない結果になりかねない。③について、仮に100点満点の評価制度であっても上司の評価者能力が低ければ運用段階で0点である。
柔軟性の高い自社オリジナルの評価制度を構築する

経営環境が激しく同一労働同一賃金、テレワークなどの働き方や働き手の価値観が変化している今日においては、柔軟性の高い自社オリジナルの評価制度へのバージョンアップを検討いただきたい。ある会社では人材力が企業成長の要であることから、1~2年で評価を含む人事制度そのものの見直しを掛けている(その結果、変更しない場合もあり得る)。バージョンアップの着眼として下記をご参考にしていただければ幸いである。
- 会社ビジョンとの連動
- その評価制度が求める人材が活躍した時、会社のビジョンは実現されるのか。
- ハイブリッド型評価制度
- 職務評価の評価要素を検討する。一般社員層は能力基準を中心とした評価要素で構成し、中間層から管理者層に上がるにつれて職務評価の要素を強めていくハイブリッド型の評価制度も検討されたい。
- 人事各種制度との連動
- 教育制度や給与制度との連動は問題ないか。当たり前のことであるが意外に出来ていないケースも多い。