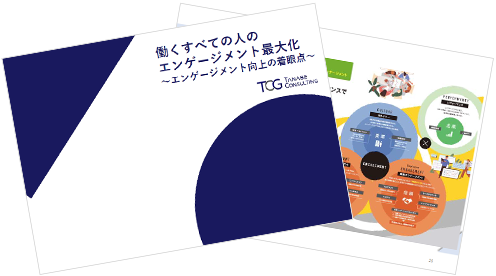QC活動を通して、自社のエンゲージメント向上につなげる

QC活動とは
QC活動とは品質管理(Quality Control)を向上させることを目的とした企業の改善活動のことである。1950年代にアメリカのエドワーズ・デミング氏が統計学を用いて品質管理する手法を日本に伝え、1960年代に日本独自に進化させたものがQC活動の始まりである。
高度経済成長期では、製造業を中心に業務改善活動が活発に行われ、各現場における小集団でのQC活動は定着していった。一方で、近年では業務の負担が増えることや働き方の変化、QC活動の効果を実感しにくいなどの理由でQC活動を見直す企業も増えつつある。
本稿では、QC活動のメリット・デメリットをおさえながら、効果的な進め方やQC活動を通してエンゲージメント(社員の貢献意欲や企業・製品への愛着)を高めるポイントを紹介したい。
QC活動のメリット・デメリット
はじめに、QC活動のメリットとデメリットについて考えていきたい。
メリットは以下の3点である。
(1)視座を高め、現状認識力の強化
QC活動では個人の業務ではなく、会社や部署における課題を洗い出し改善に取り組むため、俯瞰して現状を把握して考える必要がある。QC活動を通して現状認識力・問題発見力を伸ばし、参加者の成長につなげることができる。
(2)課題に対する当事者意識の醸成
課題に対して不平・不満で終わるのではなく、どのように解決するか考える機会となる。
管理職手前の人材など、QC活動を通して自社の課題を自分たちで解決する、当事者意識を醸成する効果がある。
(3)部署間を超えたコミュニケーションの活性化
QC活動では部門を超えてプロジェクト型で進める機会が多い。共通の目的、課題解決を目指すことで普段接点のないメンバーともコミュニケーションを取る機会を増やせる。
デメリットは以下の3点である。
(1)効果測定が難しい/すぐに表れにくい
QC活動は予め任期を決めて活動することが多い。そのため、任期の間に具体的な成果がでれば効果を実感できるが、すぐには表れにくいこともある。効果が表れにくいと参加者は達成感など実感しにくくなる可能性がある。
(2)業務の負担が増える
QC活動は通常の業務をこなしながら活動することが多いため、業務量の増加や時間がかかる可能性がある。
その結果、生産量の低下など通常業務に支障がでないよう配慮が必要である。
(3)評価につながりにくい
QC活動は直属の上司が必ず参加するかは未定であり、小集団で課題に取り組むため、個人の取り組み姿勢など評価しにくい点がある。
QC活動に取り組むことで自身の成長や関係性の強化が期待できるが、参加することによる負担増や効果については慎重に検討する必要がある。

QC活動の効果的な進め方とエンゲージメントを高めるポイント
メリット・デメリットを踏まえた上で、QC活動を個人の成長だけではなく、自社に対するエンゲージメント向上にも繋げていきたい。そのために効果的な進め方と高めるポイントは以下の3点である。
(1)所属する部署の理解と業務調整
QC活動を効果的に進める上でまずは所属する部署の理解が必要である。業務量を調整した場合、参加者以外のメンバーの負担が増えることを想定し、上長から正しくメンバーに周知する必要がある。
また、参加者もQC活動と従来の業務を平行して行えるよう、上長と相談しながら進めることがポイントである。
(2)ゴール(あるべき姿)から逆算して考える
QC活動を例年続けている企業にありがちなのが、QC活動に参加することが目的になるケースである。
活動を進める上で、目的はなにかゴールから逆算して目標設定することが重要である。
また、定期的に中間報告を実施することで、ゴールからズレていないかなど確認しながら進めることを検討したい。
(3)教育研修と連動させる
QC活動を効果的に行う企業の例として、単に集まって進捗を共有し合うだけではなく、分析する手法や考え方などの研修を行っている。QC活動を通して、インプットの学ぶ機会とアウトプットの活動を通して参加者の成長につなげることを意識したい。
エンゲージメントを高めるポイント
QC活動を通して、自社のエンゲージメントを高めるポイントとして以下3点を意識していただきたい。
(1)環境・社会貢献など、業務改善のみに限らないテーマも考える
QC活動の意味としては品質や業務効率の改善が趣旨ではあるが、エンゲージメントの観点から考えると、「改善」を自社の取り巻く環境などに広げていきたい。
例えば、水や洗剤の使用量を減らす取り組みは会社のコスト削減だけでなく、環境にも良い影響を与える。
他にも地域から愛される会社になるための取り組みなど、会社の存在価値を高めることで、自社のエンゲージメント向上につなげることができる。
(2)コミュニケーションの時間を設ける
忙しい中、限られた時間を使って進めるため、どうしても進捗報告や打ち合わせが優先しがちになるが冒頭は意識してコミュニケーションを取る時間として活用したい。自部署の様子や最近の出来事などお互いを知る機会をつくることで、参加者同士の関係性を深めるだけでなく、自部署以外の理解を深めることができる。
また冒頭に機会をつくることで、心理的安全性を高め、活発なディスカッションにもつながる。
(3)活動報告会・表彰制度を設ける
効果的に進めるポイントでもお伝えしたが、ゴールを決めて取り組むため、活動報告する機会を設けたい。
効果測定をすることはもちろん、報告を聞くことで社内への浸透、次のメンバーの活動にもつなげていくことができる。
また個別の評価がしにくい分、取り組みに対してフィードバックや表彰などで報いる仕組みも検討したい。
さいごに
時代の変化に伴いDXやAIの進化により業務改善のスピードは飛躍的に高まっている。
そのため、QC活動についても時代の進化に合わせた活動に変えていく必要がある。
大切なことは、課題の「点」を解決するために集まるのではなく、自社だからこそできることや自由に発言できる風土、認め合う文化を醸成し取り組むことを目指していただきたい。
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
チーフコンサルタント柴田 貴也
- 主な実績
-
- 金属商社:人事制度再構築支援
- 物流業:人事制度再構築支援
- コールセンター:人事制度再構築支援
- 金型製造業:事業再生支援
- 化粧品製造業:執行役員制度構築支援 など
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト