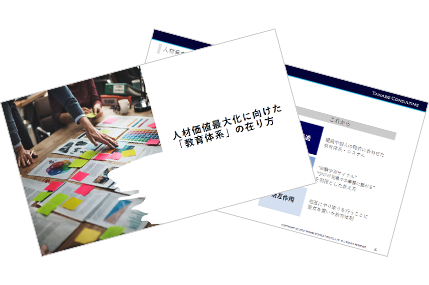自社のことが大好きな
コンピテンシー人材を選抜し、
リファラル採用チームとして展開する
リファラル採用とは何か

状況変化が激しい昨今、新卒採用からすぐに成果を生み出す中途採用へのシフトが進んでいる。一方、優秀人材を獲得するための採用コストは年々上昇傾向にあり、有料広告のみに依存した採用戦略には限界が来ている。このような中、新たな取り組みとして「リファラル採用」の活用により、人との繋がりで採用を成功している企業が増えてきている。
リファラル採用とは、既存社員などから知人・友人の紹介によって採用する方法である。昔から縁故採用などは存在していたが、ポイントは若手社員を含めた全社員からの紹介を受け入れ、これまで以上に採用成功の可能性を広げていることにある。しかし、筆者がコンサルティング現場においてよく耳にするのが、「社員が連れてきた社員だから処遇が難しい」「採用できたのにも関わらず、社風になじめず、パフォーマンスが発揮できていない」「プロジェクトを組成・推進しているものの、日常業務を優先し実質活動が行えていない」など課題は山積みである。
リファラル採用のメリット

リファラル採用の主なメリットは下記の通りである。
1.マッチングの高さと信頼性
リファラル採用のメリットと言えば、まずはこれである。既存の社員からの紹介であるため、当然ながら思考やスキルがマッチした人材を紹介してくれているはずであり、人間的にも信頼できる人物であることが多い。それが結果的に定着率の高さにも繋がっていく。
2.コスト削減
リファラル採用は紹介であるためコストが掛からない。ただ、紹介者にメリットが何もないというのも寂しいので、紹介者にお礼として金一封を支払ったりしている企業も多い。それでも、求人広告やエージェントを利用することと比べれば、格段に採用コストは安くなる。
3.迅速な採用プロセス
紹介者が候補者の情報を事前に提供してくれるため、面接や選考プロセスが迅速に進むことが多い。また紹介者にも動機付けなどに協力してもらえるので、採用決定率も高くなる。
リファラル採用のデメリット

一方で、リファラル採用には下記のようなデメリットがある。
1.多様性が欠如しがち
既存社員のネットワークに依存するため、同じような背景や考え方を持つ人が集まりやすく、リファラル採用ばかりに頼っていると、組織内の同質性が高くなり過ぎてしまう。
2.偏見のリスク
紹介者からの事前情報があるのは良いことであるが、それが先入観を生んだり、あの人の推薦だから大丈夫だろうと、客観的な評価ができなかったりする。紹介者からの情報はあくまで参考に留め、客観的に評価するというスタンスが大事である。
3.内部関係の複雑化
紹介者と被紹介者が上司部下の関係や同僚になると、プライベートな関係性が職場に持ち込まれたり、本人同士の関係性が入社前と変わってきたりすることがある。そうなると職場内での人間関係のトラブルの元になるリスクも懸念される。また、仮に被紹介者が期待に応えられなかったり、すぐに辞めてしまったりした場合、紹介者の社内での評価も落とすことに繋がってしまう。
リファラル採用は、適切に運用すれば非常に効果的な採用手法であるが、デメリットも考慮してバランスを取りながら戦略的に活用していくことが重要である。
リファラル採用成功の3つのポイント
上記内容を踏まえ、成功企業から導かれる成功のポイントは大きく3つある。
- 1.全社員一斉ではなく、自社が大好きなコンピテンシー人材から始める
- 全社員で始めると他人事になりやすく、動きが鈍くなってしまう。従って、少人数を選抜して進めることが望ましい。さらに、選抜する人材は自社が大好きなメンバーが良い。なぜならば、能動的かつ熱意を持って自社の魅力や特徴を語れるからである。
- 2.現場のリアルを伝えられる紹介ツールを作成する
- 自社の魅力や特徴に加え、自社の課題・改善策などを盛り込む。中途採用者にとって、リアルの声(良いことばかりでなく問題点)を聞けることが信頼を生み出し、入社後のギャップ解消にも繋がる。
- 3.最終的に見極め、口説くのは経営陣である
- 自社のコンピテンシー人材がスカウトしてきた中途採用者を最終的に見極めるのは、経営陣の仕事である。リファラル採用で成功している、ある会社は経営陣が自宅まで出向き、面談されている。このプロセスを加えることによっても入社後のギャップ解消に繋げている。
リファラル採用の今後の展望

リファラル採用については、今後も効果的な採用手法として活用されていくであろう。展望としては、いくつかのトレンドや技術の進化が影響を与え、下記の様に進化していくものと考えられる。
1.テクノロジーの進化とAIの活用
AIや機械学習を活用したリファラル採用システムが登場し、紹介プロセスの効率化や精度向上が期待される。これにより、適切な候補者のマッチングがより迅速かつ正確に行われるようになる。例えば、AIが既存の従業員のネットワークを分析し、最適な候補者を自動的に推薦するシステムなどである。
2.ソーシャルメディアの活用
LinkedInやFacebookなどのソーシャルメディアを活用したリファラル採用が増加するであろう。これにより、社員とソーシャルメディア上で繋がりのある多様な候補者が紹介される可能性が高まる。例えば、企業がソーシャルメディア上でリファラルキャンペーンを実施し、社員が自分のネットワークに求人情報をシェアするなども考えられる。
3.データドリブンなアプローチ
リファラル採用の効果をデータで評価し、最適化するアプローチが進むであろう。これにより、どのようなリファラルが成功しやすいか、どの従業員が優れた紹介者であるかなどが明確になる。
4.多様性とインクルージョンの強化
多様性とインクルージョン(D&I)の重要性が増す中で、リファラル採用もこれに対応する必要がある。社員に対して多様な候補者を紹介するよう奨励するプログラムやトレーニングが導入されるであろう。例えば、D&Iを重視したリファラルボーナス制度や、多様なバックグラウンドを持つ候補者を紹介した社員に対する特別なインセンティブなどである。
5.従業員エンゲージメントの向上
リファラル採用は従業員エンゲージメントを高める手段としても注目されている。社員が自分のネットワークを活用して会社に貢献することで、企業への帰属意識が高まることが期待される。
採用力のある会社を一言で言うと、「自分の大切な友人を紹介したいと思える会社」である。それは正に「リファラル採用力の高い会社」と言えるのではないだろうか。今後、本格的な人不足の時代を迎えるに当たって、リファラル採用ができる会社になることは、非常に重要な経営マターと言えるであろう。
この課題を解決したコンサルタント

タナベコンサルティング
HRコンサルティング事業部
エグゼクティブパートナー盛田 恵介
- 主な実績
-
- 上場・中堅ゼネコンのアカデミー構築・運用支援
- 中堅スーパーのアカデミー構築・運用支援
- 中堅飲食業のアカデミー構築支援
- 金属加工・製造業のアカデミー構築支援
- 中堅建設業の人事制度構築支援
- 中堅製造業の次世代幹部育成・ジュニアボード運営支援
- 中堅サービス業、建設業、製造業企業の中期ビジョン策定
- 卸売業、サービス業、建設業、製造業の社内アカデミー構築&人材育成支援
 経営者・人事部門のためのHR情報サイト
経営者・人事部門のためのHR情報サイト