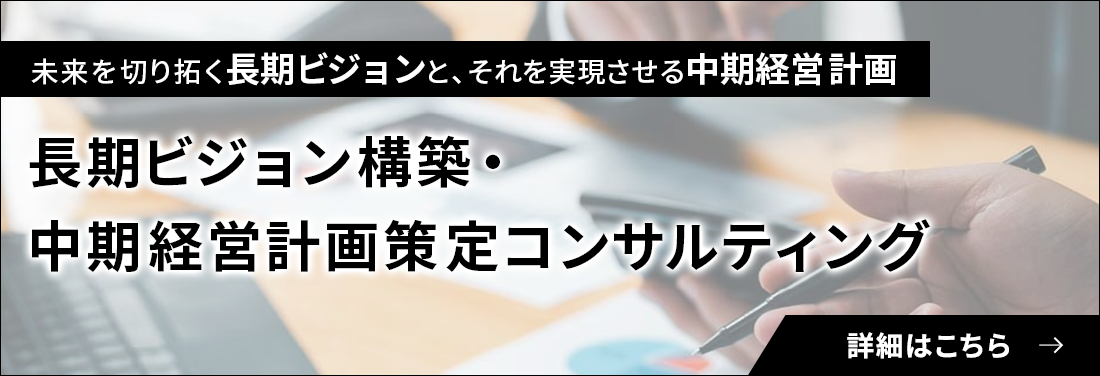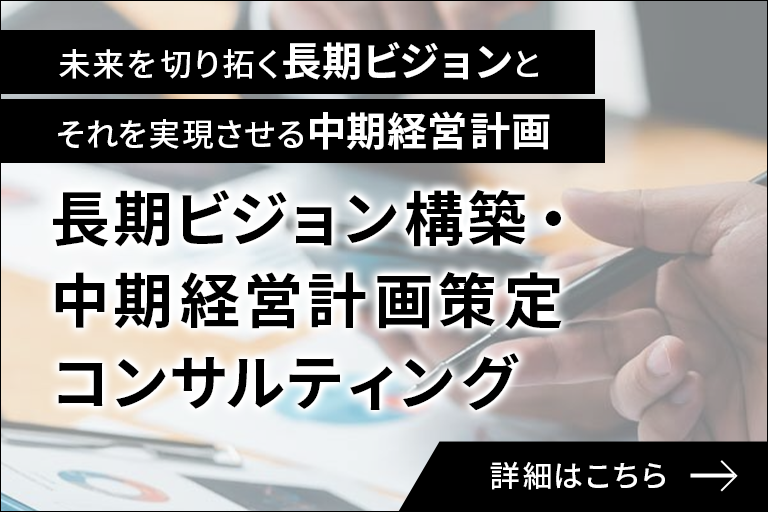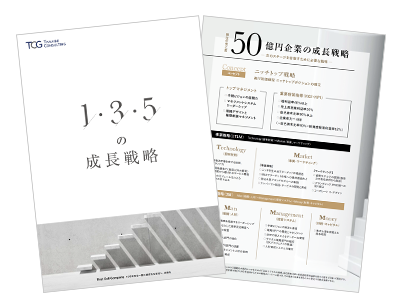COLUMN
コラム
閉じる
データで見る東京証券取引所の現状
(1)現在の上場社数
日本初の証券取引機関は、1878年に設立した東京株式取引所。その後、変遷して第二次世界大戦後の1949年に東京証券取引所として設立しました。そして、組織変更して現在の株式会社東京証券取引所になりました。(今後は、東証と記載)
東証の株式市場は、プライム1,834社、スタンダード1,441社、グロース545社、TOKYO PRO Market79社の区分で合計3,899社が上場しています。(出所:日本取引所グループ、2023年8月4日時点)
(2)上場企業の創業100年以上の企業数(出所:東京商工リサーチ社)
日本の企業は、世界の創業100年以上企業の4割、200年以上企業の6割を占める長寿企業の宝庫と言われます。それでも、国内企業数約385万社の内、創業100年以上企業数は、4万2,966社で1.2%です。
その内、東証に上場する創業100年以上企業は、688社で、内訳は、東証プライムが432社(構成比62.7%)で最も多く、次いで東証スタンダードが238社(同34.5%)で、東証グロースはゼロです。
(3)売上規模で見る100年以上企業は

出所:東京商工リサーチのデータをもとにタナベコンサルティング作成
売上高1億円未満企業が18,942社(構成比44.1%)、売上高1億円以上10億円未満企業が15,683社(同36.5%)、売上高10億円以上100億円未満企業が6,353社(同14.8%)であり、売上高100億円以上企業は1,988社(同4.6%)で大企業が占める割合は意外にも低いと言えます。
誤解を恐れず言えば、企業規模を拡大することは、創業100年以上の永続企業にすることが難しくなることを意味します。
(4)東証の上場企業の中期経営計画の開示状況

出所:CCReB Clipのデータをもとにタナベコンサルティング作成
東証上場企業の中期経営計画の開示割合は、3,720社中1,923社で51.2%。上場区分では、東証プライムが70.2%、東証スタンダードが36.5%、東証グロースが25.8%でPRO Marketはゼロとのデータがあります。
中期経営計画の作成、開示ともに義務ではないので問題ではないのですが、東証プライム以外は、総じて少ないのも事実です。
(5)中期経営計画の開示年数

出所:CCReB Clipのデータをもとにタナベコンサルティング作成
中期経営計画の策定期間は、3ヵ年が69.8%と多く、次いで5ヵ年で18.9%と全体の88.8%を占めます。圧倒的に3ヵ年が多いことが分かります。一般的に、10年後のあるべき姿を描くことを長期ビジョンであり、3ヵ年から5ヵ年の事業計画が中期経営計画と捉えればいい。
以上の結果からも上場企業の中期経営計画のスタンダードは3ヵ年です。

記載内容の項目とポイント
(1)事例に学ぶ中期経営計画の発想法(その1:日産自動車)
かつて業績不振に苦しんでいた日産自動車がルノーとのアライアンスを機に、一流企業への復活をかけて中期経営計画にストーリー性とメッセージ色を明解に示し、社内外にインパクトを持たせた事例は、大変参考になると思いますので、ここで紹介します。
①アライアンス直後に発信された「日産サバイバルプラン(NSP)」(2000~2001年度:2年)
まさしく、会社を再生させるための経営計画
②「日産180」(2002~2004年度:2年)
再生を完了し、利益ある成長へ軸足を移動する経営計画
③「日産バリューアップ」(2005~2007年度:3年)
更なる発展と価値創造に向けた経営計画
④「日産GT2012」(2008~:途中中断で計画変更)
ステークホルダーの信頼と共に、長期的な成長を目指す経営計画。ただし、金融危機など経営環境の急激な悪化で、途中で中断し、リカバリープランを実行
⑤「日産パワー88」(20011~2016年:6年)
新規市場、セグメントを含む世界市場での成長を加速させるための経営計画
⑥「日産M.O.V.E to 2022」(2017~2022年:6年)
持続可能な成長を実現し、新技術とビジネスの両面で自動車産業をリードしていくことを目指す経営計画
⑦事業構造改革「NISSAN NEXT」(2022年5月に発信し、現在、継続中)
収益性を重視しながらコストを最適化することで、持続的な成長と安定的な収益の確保を目指す経営計画
以上の日産自動車の経営計画がすべて達成したとは言えない部分と世間の批判と注目を集めたこともあったと思うが、自社の成長ストーリーに思いをはせ、常に社内外にインパクトを与える経営計画には学ぶ点が大いにあると思います。
参考:https://www.nissan-global.com/JP/COMPANY/PLAN/
(2)事例に学ぶ中期経営計画の発想法(その2:旭化成)
2022年5月に創業100周年を迎えた旭化成の新中期経営計画2024「Be a Trailblazer」(2022年4月11日発表)では、「次の100年に向けて我々は新たな挑戦を続けます」をテーマに社内外に向けて発信されており、大変、参考になると思いますので紹介します。
①旭化成が中期経営計画に込めた、ステークホルダーに伝えたいテーマ5点
・アニマルスピリッツで地図のない道を切り拓き、新しい伝統を創る
・利益成長/ROE/ROICを重要指標とした持続的な企業価値向上
・「挑戦的な成長投資」と「構造転換や既存事業強化によるキャッシュ創出」の両輪
・スピード/アセットライト/高付加価値を追求する戦術
・次の100年も価値を提供し続ける為のサステナブルな経営基盤の継続強化
②事例に見る中期経営計画の全体構成(大項目)
・前中期経営計画の振り返り
・旭化成が目指す姿
・新中期経営計画2024~Be a Trailblazer~
1.基本方針・目標
2.領域別事業戦略
3.経営基盤強化
参考までに、前中期経営計画の振り返りの売上高と営業利益とその率の発表内容で見ると、2021年の売上高計画2兆4,000億円に対し、実績が2兆4,530億円。営業利益2,400億円、営業利益率10%に対し、実績が2,131億円、営業利益率8.7%と売上高計画は達成したが、営業利益目標、営業利益率目標は計画値に届きませんでした。
中期経営計画期間の最終年度の2021年に大きく回復し、「新中期経営計画2024」に期待の持てる結果であると思います。ステークホルダーからすると「サステナブルな経営基盤の継続強化」に期待できる内容であったと言えます。
また、次の成長を牽引する10のGrowth Gears(GG10)と題して、重点的にリソースを投入して、現状、営業利益に占める構成割合35%を2024年には50%へ、そして、2030年度には、利益構成割合を70%まで構成割合を高める計画を打ち出しています。
そのテーマは、「次の成長の為の挑戦的な投資」と「構造転換や既存事業強化によるキキャッシュ創出」を軸に「スピード」「アセットライト」「高付加価値」を事業ポートフォリオの基本指針として打ち出しています。いずれにしても、いまに社内外のステークホルダーに対し、いかにインパクトを持たせ企業の未来に対し期待感を持たせるかが中期経営計画策定におけるポイントになります。
参考:https://www.asahi-kasei.com/jp/company/strategy/
中期経営計画の策定に抑えるべきポイント
(1)定量、定性計画の社内外のステークホルダーへの約束
未来のことは、誰しも正確に予測できるものではないはずです。例えば、世界的パンディミックとなった新型コロナウィルスや主権国家が他の主権国家に攻め入ったウクライナ危機などは、2008年に発生したリーマン・ショックや1995年の阪神淡路大震災、2011年の東日本大震災を経験した経営者でも予想しえなかった危機であったと思います。
それでも、未来を語るのが中期経営計画であり、預言者の領域ではありません。その意味では、中期経営計画の持つ特性として未来予測の正確性を問うものではなく、自社とステークホルダーの間で「これで未来に向かいましょう」と相互納得性を問うものであるべきです。
平たく言えば「健全な思い込み」をいかに得られるかが中期経営計画を策定するにあたってのポイントだと言えます。企業業績は結果であり、未来計画は企業の意思なのです。言えば、定量、定性計画のステークホルダーへの企業の思いの約束です。
(2)未来に向けて「新」をテーマにした事業計画を示すことは有効
いかなる経営環境でも中期経営計画は、成長戦略を前提にします。自社の属している市場の成長が見込まれるのであれば幸運だが多くの場合、成熟市場に属することのほうが多いように思います。結果として、他社との熾烈な競争環境にあることのほうが一般的です。
そのような状況でも、中期経営計画を作成する上では、右肩上がりの計画を組むことが前提になります。既存事業の拡大に加え、新商品、新市場、新分野(すでに手掛けているものも含む)を中期計画に織り込む必要があります。「新」を大胆に織り込むと、中期経営計画の説得力と納得性が格段に増します。前述の日産自動車と旭化成の事例で確認してみます。
①日産自動車
電動車のラインナップの拡充
・2026年までに、電動化への投資2兆円、電動車20車種、グローバル電動車モデルミックス44%以上
・2030年までに、EV19車種を含む電動車27車種、グローバル電動車モデルミックス55%以上
②旭化成
主要事業3分野 マテリアル事業(2021年売上高11,920億円→2024年12,300億円)、住宅事業(2021年8,240億円→2024年9,300億円)、ヘルスケア事業(2021年4,230億円→2024年5,300億円)のすべてにおいて成長計画を開示していますが、特にヘルスケア事業の成長率が大きくなっています。
常に将来を見つめ事業を育てる社風が根づいている証であると言えます。
(3)ビジョン、ミッション、バリューを示すパーパス経営の重要性
中期経営計画を開示するに当たって、ぜひ、考慮すべきことはパーパス(企業の存在意義)をステークホルダーに対し明確に示すことが極めて重要です。
パーパスは、目的、意図を指す用語であり、似た言葉にミッション、ビジョンがあります。ミッションが企業の果たすべき使命であり社会に対する役割、ビジョンが企業の実現したいあるべき姿です。企業目的の視点からすると重なりあっており、パーパス、ミッション、ビジョンを無理に区別する必要はありません。
むしろ社内で3ヶ月から1年ほどの時間をかけ、徹底して討議し、社内外に納得性と共感性を得られる内容に醸成することに注力すべきです。企業として真摯な姿勢で事業目的を発信し、社員をはじめとするステークホルダーに対し、強烈なメッセージを発信することが肝心だと言えます。現在のVUCA(不確実性の時代)に不可欠な企業のあるべき姿勢です。
結果として、継続的な企業成長につながる重要な要素であります。ぜひ、中期経営計画でも強いメッセージを発信していただきたいと考えます。以下、事例を参考にしてください。
事例1:ソニー「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす」
事例2:ユニリーバ「サステナビリティを暮らしの"あたりまえ"に」
事例3:味の素「アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとのウェルネスを共創します」
事例4:ネスレ「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」

最後に
東証に上場している企業すべて、有価証券報告書と称して過去の経営活動結果である財務諸表を公開する義務があります。もちろん、その内容において偽装があれば大きな罪になり、社会からも批判を浴びなんらかの制裁が下るのが一般的です。
中期経営計画はどうでしょう。前述したように東証上場企業が必ずしも作成し開示しているわけではありません。東証プライム企業といえども開示企業は、約7割程度です。大事なことは、中期経営計画の開示義務はなくとも、企業が経営を営む上で、社員、ステークホルダー、社会に対し、未来に向けた強い意志を示すことは極めて重要だと言えます。
中期計画の作成年数は自由です。10ヵ年の長期ビジョンでも、3ヵ年から7ヵ年の中期計画でもいい。どういった未来を描き、自社が社会に対し、どのような義務を果たすのか、ぜひ、強いメッセージを発信していただきたいと思います。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト