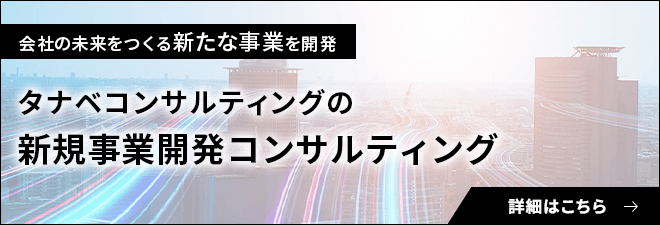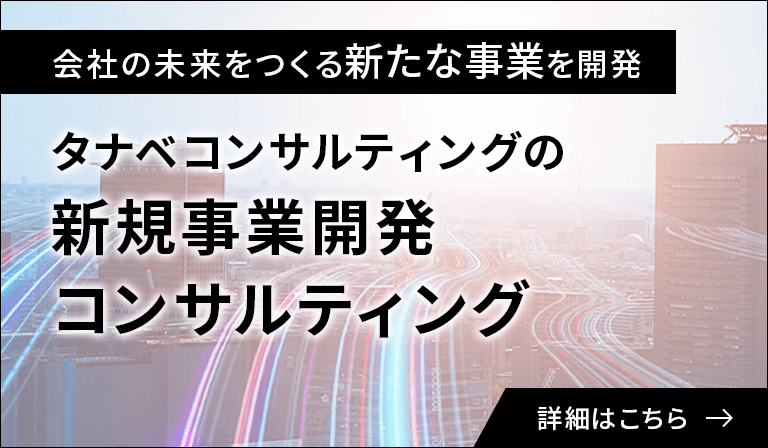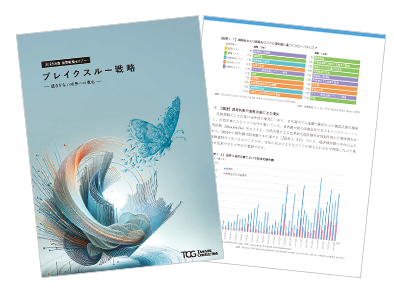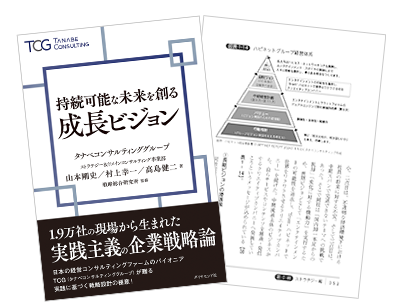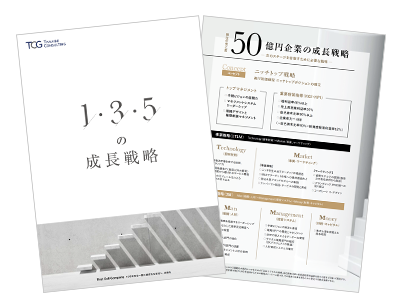COLUMN
コラム
閉じる

企業が継続的な成長を遂げる上で、新規事業開発は欠かせない取り組みです。顧客価値と自社の独自の強みを基盤にして新たな事業を考案し、プロジェクト形式から事業部への段階的な移行を目指すことが理想的です。また、リーダーの育成や外部との連携も、事業の成否を左右する重要なカギとなります。
新規事業開発の必要性と背景
事業ライフサイクルの短縮とその影響
現代におけるビジネス環境は、技術の急速な進展や市場構造の変化が絶えず起こっています。その結果、企業が長期的に成長を維持するには、時代の流れに合わせて絶えず新しい事業を生み出す姿勢が求められています。たとえ現時点で主要な事業が好調であっても、油断は禁物です。なぜなら、どの事業にも必ず「成長」「成熟」「衰退」というライフサイクルがあり、いずれは経済的価値が薄れていくものだからです。以前は十年以上、市場トップの座に君臨していた商品やサービスでさえ、現在では数年で競争力を失うことも珍しくありません。こうした状況下で企業が安定した成長を続けていくには、既存事業による収益基盤を活かしつつ、新たな柱となるビジネスを構築していく必要があるのです。
新規事業の役割と価値
新規事業は、単に売上規模の拡大手段ではありません。むしろ、企業の将来を切り拓くための戦略的な武器となります。成功する事業を生み出すには、明確な戦略と実行プロセスが不可欠です。企業が新しい事業に取り組む際には、旧来の枠組みにとらわれず、社会が抱える課題や市場動向を捉えた斬新な発想が大切です。これによって、他社との差別化が図れるだけでなく、持続的な成長にもつながります。

新規事業開発の根幹となる要素
事業アイデアの切り口
新しい事業を成功に導くには、自社が本来どのような事業に着手すべきかを明らかにすることが重要です。むやみに未知の分野へ進出しても、成果にはつながりにくいものです。自社の事業ポートフォリオを見直し、足りない部分や今後の伸びしろが期待できる領域を特定したうえで、そこを強化する方向で事業設計を行う必要があります。
取り組む際の軸は大きく2つ考えられます。
「顧客価値」を重視:既存顧客との信頼関係を生かし、顧客のニーズと時流に寄り添うサービスや商品を展開します。結果として、顧客から厚い信頼を得られる「ワンストップ型ビジネスモデル」の価値を生み出せます。
「付加価値」を重視:自社の技術やブランドといった強みをてこに、今まで手掛けてこなかった市場を開拓します。これにより、他社が真似できない競争優位を実現できます。
失敗事例に学ぶ注意点
非関連多角化のリスク
本業とかかわりのない事業や、関連性がほとんどない分野への参入は、多くの場合うまくいきません。その理由は、顧客との人脈や、付加価値・利益率を高めるスキルやノウハウを一から積み上げる必要があるためです。万が一、収益化したとしても既存事業との相乗効果が生まれにくく、企業全体のポートフォリオとしての魅力も高まりません。
市場環境を見誤るリスク
たとえ本業と関係する分野でも、市場動向を読み違えると成長は期待できません。たとえば、BtoCの製造企業が小売りやWebサイト通販といった業態に乗り出した場合でも、競合他社がすでに多く存在していれば独自性を打ち出せず、価格競争に巻き込まれることにもなりかねません。また、ニッチな市場で勝負しても、ノウハウ構築に時間がかかり、認知が高まる頃には商品やサービスが一般化してしまう可能性もあります。特に、事業スピードが求められる現在においては、立ち上げのタイミングも重要です。

新規事業を形にするプロセス
横断的プロジェクトの構築
新しい事業を具現化するには、経営資源の最適な配分と、柔軟な組織づくりが求められます。とはいえ、いきなり独立した事業部門を設立するのはハードルが高いものです。そこで、まずは既存組織内で横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、小さな単位で製品やサービス開発に着手していくのが定石です。プロジェクトリーダーを中心に、事業計画や行動計画を描きながら、事業の方向性を具体化していきます。
プロジェクトの利益化
次のステップでは、プロジェクトの売上やKPIを組織横断で管理し、利益計上まで持ち込むことが目標となります。この段階ではまだ独立した組織ではなく、全社的な取り組みとして目標にコミットします。マーケティングや営業活動の強化、人材の再配置などによって、成長スピードを高めていきます。
事業部単位への独立と拡大
事業が一定規模に達したら、これを一つの事業部として独立させます。この組織化の動きは、単なる事業拡大だけでなく、組織内に新しいキャリアパスを創出し、リーダー育成の観点でも大きな意味を持ちます。事業の成長に伴って自律的な部門運営を実現しましょう。

持続可能な事業成長を支えるリソースと連携
戦略リーダーの育成と配置
新しい取り組みを加速するには、「戦略推進リーダー」の数と質がカギを握ります。リーダーには、事業の方向性を明確に打ち出す力だけでなく、時には挫折を経験しながらもメンバーを鼓舞し続ける推進力が求められます。とはいえ、主力人材を既存事業から引き抜くのはリスクも高く、結果的に人材不足で事業化が滞るパターンも多く見られます。
外部採用(ダイレクトリクルーティングや人材紹介)を活用する方法もありますが、既存スタッフとの関係づくりに配慮が必要です。理想は、ふだんから中堅・若手スタッフの中にリーダー候補を発掘し、必要な場面で抜擢できる体制を作っておくことです。そのためにも、人材育成プログラムを見直し、「新規事業を任せられる人材」を計画的に育てる仕組みづくりが不可欠となります。
パートナーシップの活用と連携
自社だけですべてをまかなうのではなく、外部パートナーと連携することも事業開発の効率化につながります。専門的な技術やノウハウが必要な場合、スタートアップや研究機関、他業種企業等と協力することで、スピードと品質を両立できます。新規事業の経験が浅いのであれば、コンサルティング会社にプロセス伴走を依頼するのも有効です。親和性の高いパートナー企業の動向にアンテナを張り、必要に応じて連携やM&Aも活用し、自社のリソースを補強する姿勢が重要です。これらの連携によって、自社単独では得られない成長機会を追求していきましょう。

おわりに
新規事業開発は、変化の激しい現代社会において企業が生き残るための必須戦略です。事業ライフサイクルの短縮が進むなかで、既存事業に安住することなく、新たな成長の芽を常に育み続ける姿勢が求められます。成功のポイントは、顧客視点や自社の強みを明確にしたうえで、段階的かつ柔軟なプロセスで事業を推進することです。初期フェーズでは横断的なプロジェクト形式とし、成長に応じて事業部として独立させていく流れが効果的です。
加えて、人材育成や適切なリーダー選定、社外パートナーとの連携体制づくりも欠かせません。特に、事業推進リーダーの力量や適切な人数を確保し、人材育成・採用体制の見直しを徹底することが持続的な成長の原動力となります。また、自社外の専門ノウハウや技術を積極的に取り入れることで、競争力と事業の成長スピードを加速させることができるでしょう。
このように、新規事業開発は単なる新しい収益源確保にとどまらず、企業自体の構造転換や進化に向けた「次への一手」として捉え実行することが、将来にわたる成長の基盤となります。これからの企業経営においては、固定観念にとらわれず柔軟かつ戦略的に新規事業開発へ踏み出すことが求められます。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト