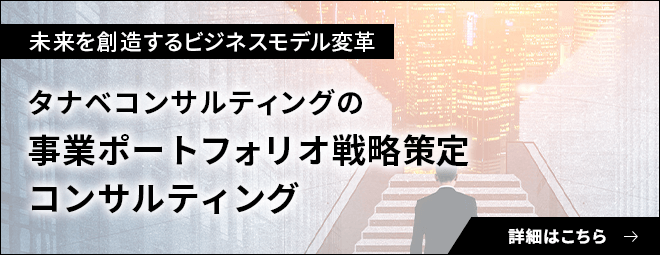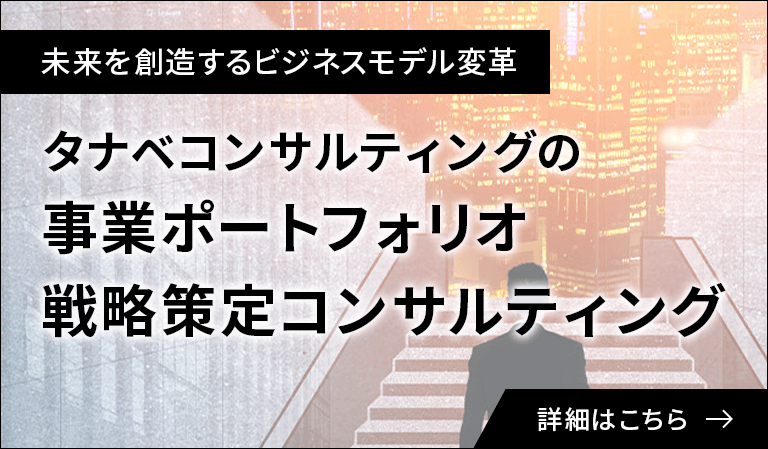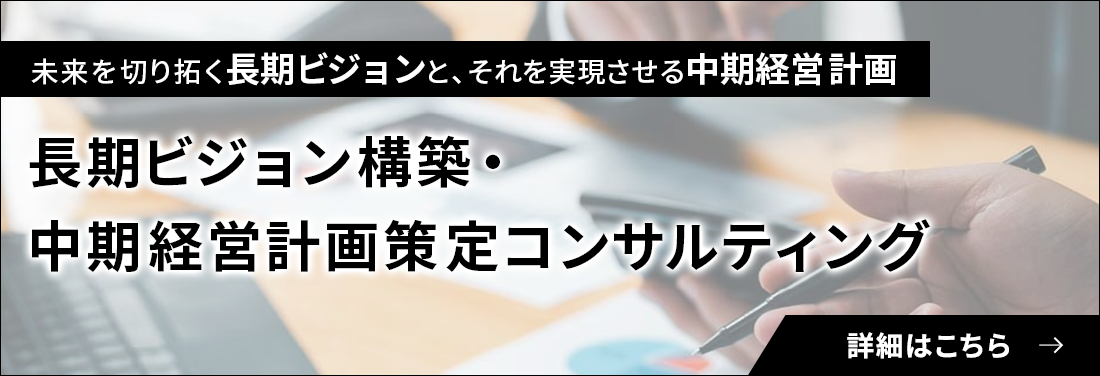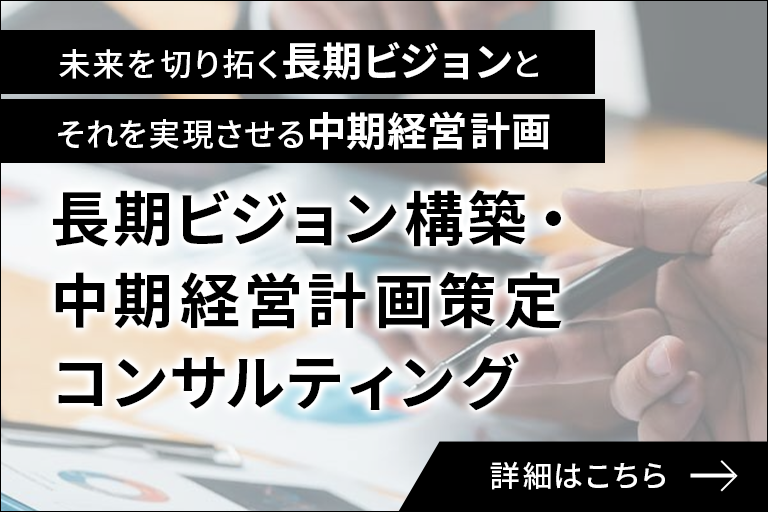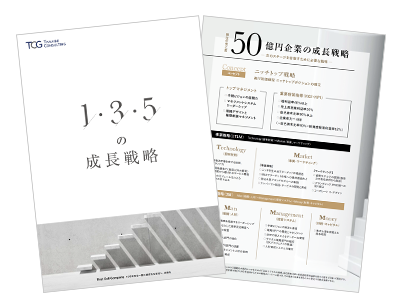COLUMN
コラム
閉じる

【結論】
事業ポートフォリオを再編し、限られたリソースを強化事業に注ぎ込むことは新規事業開発の成否を決定づけます。自社の強みを再定義し、事業を取捨選択するという「非情な決断」を断行するだけでなく、それを組織に実装させる「変革ストーリー」まで描き切ることが戦略実現のポイントです。
新事業という「理想」と、その前に立ちはだかる「現実」
企業の未来のため、新たな事業の柱を打ち立てる。その重要性を理解されていない経営者・経営幹部の方はおられないでしょう。VUCAと呼ばれる見通しのきかない時代、インフレ経済というこれまでの当たり前が通用しない環境では、今まで以上に多くの経営者が、来るべき未来を見据え、新規事業の必要性を痛感し、そのための計画策定に時間を費やしています。
しかし、その想いとは裏腹に、なぜ多くの挑戦が具体的な実行に至らず、いつしか"絵に描いた餅"と化してしまうのでしょうか。
その原因の一つは、新規事業領域という「未来」にばかり目を向け、今自社が立っている足元、すなわち「既存事業群」の構造的な問題から目を背けていることにあります。新規事業という、新たな成長への「推進力」を生み出すためには、まず、自社の事業ポートフォリオの再編に、覚悟をもって向き合わなければなりません。時には、一部の事業から撤退するという厳しい判断が、結果として会社全体を前進させるために不可欠なことさえあります。
事業ポートフォリオ再編のポイントは「強みの再定義」と「非情な決断」
事業ポートフォリオ再編の第一歩は、感傷を排した、冷静な戦略構築です。ここでの重要な手順は二つあります。
自社の「真の強み」を再定義する
実際に戦略立案のご支援をしていると「わが社には特筆すべき強みがない」という言葉をよく聞きます。しかし、企業が存続している以上、必ず顧客に選ばれる理由、すなわち「強み」は確実に存在します。問題は「強みの有無」ではなく、その価値を正しく認識し、応用可能な形で言語化できていないことです。
ここで混同してはならないのが、「単なる特徴」と真の競争力の源泉たる「真の強み=コアコンピタンス」です。コアコンピタンスとは、競合他社が容易に模倣できない、組織的な強みの源泉となる「中核的な能力」を指します。それは単一の技術やスキルではなく、長年の経験で培われたノウハウ、独自のプロセス、そして組織文化などが複合的に結びついたものです。
いくつかの例を挙げて、その違いを見ていきましょう。
①「納期が早い」という強み
この「コアコンピタンス」は、一言で言うなら「多能工連携による超柔軟生産体制」でした。これは、顧客の急な仕様変更や小ロット要求にも応えきる、柔軟な生産管理体制と多能工化した従業員の連携プレーを指し、試作品開発支援などの新事業にも応用可能な強みです。
②「地域密着」という強み
この「コアコンピタンス」は、一言で言うなら「地域社会への深い情報網」でした。これは、長年で築いた地域の主要企業やキーパーソンとの深い信頼関係と情報ネットワークを指し、ビジネスマッチングの機会創出、事業承継支援といった地域課題解決型の新サービスを生み出しました。
③「高品質」という強み
この「コアコンピタンス」は、一言で言うなら「難加工材の精密加工技術」でした。これは、特定の難削材を0.01ミリ単位で安定的に加工できる独自の治具開発ノウハウと熟練工の技能を指し、半導体や医療機器などの高付加価値市場への参入を可能にしました。
このように、自社の強みを「応用可能な中核的能力(課題解決力)」として再定義すること。
これが、限られた経営資源をどこに集中投下すべきかを見極める、全ての起点となります。
非情なまでの「事業の見極め」
再定義した強みをどこで活かすのか。それは、事業ポートフォリオ分析により、自社の事業群を客観的に評価することで見えていきます。「有望事業」や「残り福事業」から得たキャッシュを、未来の成長エンジンである「強化事業」へと戦略的に投資します。再定義されたコアコンピタンスは、強化事業での競争優位性を高めるため、集中的に磨かれていきます。そのためにも、「死に体事業」と判断した不採算事業からは、勇気をもって縮小・撤退することが不可欠です。この、企業の限りある資源を最適配分するための、非情ともいえる決断こそ、経営者に課せられた重い責務です。
再定義で成功した企業事例の記事はこちら
事業ポートフォリオの再定義で高収益化を実現|中期経営計画の参考事例

多くの企業が陥る「戦略未実装」のリスク
「真の強み」を起点に、非情な「事業の見極め」で進むべき方向性を決断する。このように論理的に導き出され、正しいはずの事業ポートフォリオが結局は実装されず、「アレもコレも状態」となっている企業が多いのが現実です。
それはなぜでしょうか。その背景には、避けては通れない「実装の壁」が存在します。
最大の壁は、言うまでもなく「人」をめぐる問題です。事業の縮小や撤退は、そこで働く従業員のモチベーションを著しく低下させ、時には深刻な抵抗を招きます。長年その事業を支えてきたベテラン社員のプライドを、どう守るのか。組織全体に蔓延する不安や不信感に、どう向き合うのか。この人間的な課題が、経営者の決断を鈍らせるのです。
こうした事態に陥る最大の問題は何か。
それは、論理的に導き出された「事業戦略」と、それを動かすための「組織戦略」が分断されてしまっているからに他なりません。どんなに練られた戦略でも、その実行段階で「人」を巻き込む際には、論理的な正しさ以上に感情の問題に行き当たります。
戦略停滞リスクを回避する「変革ストーリー」の発信
「実装の壁」を乗り越えるための鍵は、論理的な「戦略・計画」をつなぎ合わせ、人の心を動かす「変革ストーリー」へと昇華させることにあります。そのための具体的なアプローチは、決して特別なものではありません。
「なぜ変えるのか」という大義を語る
会社の置かれた客観的な事実、このままではジリ貧に陥るという危機感を、データと共に誠実に共有します。その上で、「だからこそ我々は、未来のために変わらなければならない」と、変革の必然性を組織全体の共通認識とすることが不可欠です。
「過去への敬意」を明確に表明する
事業の縮小・撤退が「敗戦処理」と受け取られてしまうことが、最も大きな戦略停滞要因です。「これまでのA事業の貢献があったからこそ、会社は存続し、次の挑戦ができる。その歴史と功績に、心から感謝している。その誇りを胸に、我々は次のステージへ向かう」と、過去へのリスペクトを明言することで、その事業に従事する社員の感情を後押しすることが必要です。
「未来への希望」を具体的に示す
新規事業がいかに魅力的で、社会に貢献できるのかを示します。できればコアコンピタンスの説明と関連付け、「A事業で培った〇〇という強みこそ、新事業の成功に不可欠な武器となる。」という発信と、「この新事業成功に向け人事制度を見直し、社員の平均年収を○%アップさせる。」と伝えることで、社員1人1人の存在が未来にどう繋がるのかを示し、新たな役割への期待を託すことができます。このように、事業戦略を「変革ストーリー」まで落とし込むためには、人事制度の見直しが必須条件と言えます。特に、新たな変革を社員に求める際には、「挑戦に貢献した人材」と「挑戦を支える人材」という異なる適性を持つ人材がいずれも報われる仕組みが必要となります。これが近年、導入企業が増えてきているジョブ型人事制度が必要とされる理由なのです。
以上の3つをセットにした「変革ストーリー」は、「ビジョンブック」や「クレドカード」といった形にまとめ、全社員に浸透させる工夫ももちろん効果的ですが、最も有効なのは、「何度も、粘り強く伝え続けること」です。経営者・経営幹部陣の言葉で、あらゆる機会を通じて、粘り強く、誠実に伝え続ける。その真摯な姿勢が、組織の空気を変え、戦略を実装へと導きます。

非情な事業ポートフォリオ再編のストーリーを組織に浸透させる「変革リーダーシップ」
経営者の究極の役割とは、ただ優れた戦略を描くことではありません。ロジックに裏打ちされた、痛みを伴う「非情な決断」から逃げず、それを組織が納得できるだけの「未来への物語」へと昇華させ、戦略を実装していく。論理と感情という、相反する2つに向き合う「変革リーダーシップ」こそが、これからの時代に求められる経営者の姿です。
著者
最新コラム

- 海外販路開拓の具体的な方法4選!成功させるための戦略と手順を解説

- タイ進出を成功させるメリットと3つの注意点|進出前に知るべきリスクを解説

- バリューチェーンの重要性とは?最適な構築方法のポイントを解説

- 中期経営計画の期間は何年が最適?成功する策定のポイントを紹介
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト