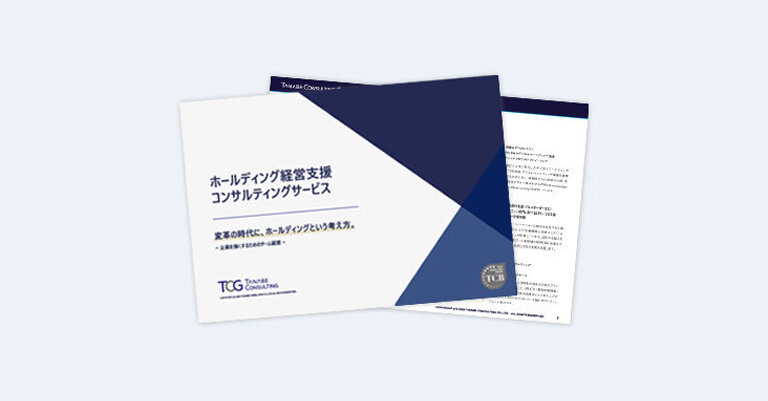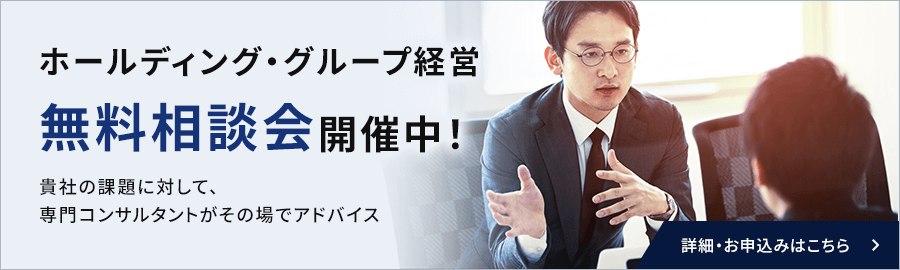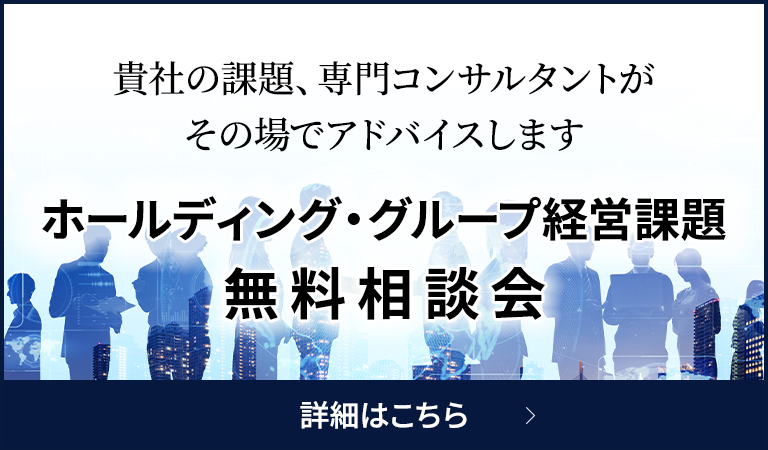ホールディングス化とは?
目的からメリット・デメリットを解説!
近年、事業承継を迎える企業増加の影響もあり、M&Aや分社化などを戦略的に進める企業が増加しています。現状、ホールディングス化を検討している、もしくはすでにホールディングス化を採用していますが、グループ化された企業経営をどのように進めるか悩まれている経営者が多いと思います。
そこで、グループ経営をうまく推進するためには、何を重点的に整備しなければならないかをご紹介します。
- ホールディング経営

閉じる
そもそもホールディングスとは
ホールディングスとは、持株会社(holding company)を指し、複数の事業会社を統括する企業形態のことです。簡単に言うと、親会社が子会社の株式を保有し、経営方針の策定や財務管理を行いながら、各事業会社が独立して業務を遂行する体制を指します。
現在、日本国内の多くの大手企業がホールディングス化を採用しており、金融、不動産、スポーツ業界など、さまざまな分野で導入されています。
この形態のメリットとして、経営の柔軟性向上やリスク分散が挙げられます。しかし、ホールディングス化の失敗例も存在し、適切な管理ができない場合にはグループ全体の運営が複雑化し、統制が取れなくなるリスクもあります。
企業の経営戦略としてホールディングスを導入する際は、ホールディングスとは何かを成功事例や課題を確認することが重要です。詳細な情報を知りたい場合は、各企業の公式ページや業界別のホールディングス一覧を検索し、最新の動向をチェックすると良いでしょう。
- ホールディングス化とは?ホールディング経営の基礎知識からメリット、具体的な手法などを解説
- ホールディング経営が選ばれる理由① ピークを迎える事業承継
- ホールディング経営が選ばれる理由② 後継者選択の自由
- ホールディング経営が選ばれる理由とは?
- ホールディングス化における株式移転を解説!株式交換との違いやメリット、デメリットも
ホールディングス化の目的
ホールディングス化の目的は、企業グループ全体の最適化を図ることにあります。
多角化した事業を持つ企業では、事業ごとに異なる市場や経営課題が生じるため、持株会社を設けることで戦略的な経営を実現する手段の一つとなりますが、必ずしも全てのケースに適しているわけではありません。それぞれの企業の状況や目標に応じた検討が重要です。
ホールディングス化により、親会社は戦略立案や財務管理に専念し、各子会社は事業の遂行に集中できるため、効率的かつ効果的な経営が可能になります。また、リスクの分散や資源の最適配分も目的の一つです。たとえば、不採算事業の切り離しや新たな事業分野への進出を迅速に進められる柔軟性が確保され、持続的な成長の基盤を構築できます。
ホールディングスの役割
ホールディングスは、株式会社が複数の事業会社を統括し、グループ全体の経営戦略や資産管理を一元的に担う重要な仕組みです。親会社が子会社の株式を保有し、各事業会社が一定の独立性を持ちながらも、グループとしての方向性を共有することで、経営効率の向上や迅速な意思決定が可能になります。
また、複数事業の収益源を持つことでリスク分散が図られ、外部環境の変化にも柔軟に対応できます。
特に中小企業では、事業承継の課題や次世代リーダー育成、新規事業やM&Aを通じた成長機会の拡大を目的に、ホールディングス化を選択するケースが増えています。
さらに、グループ全体でのシナジーを創出し、マーケティングや人材育成、DX推進といった分野で横断的に取り組むことにより、持続的な成長基盤を構築することが可能です。加えて、ステークホルダーとの関係性を強化し、社会的信用力やガバナンス体制の向上にも寄与するなど、多角的なメリットが期待されています。
ホールディングス化とグループ会社の違い
ホールディングス化と一般的なグループ会社は、組織運営の仕組みや統制の在り方に大きな違いがあります。ホールディングス化は、親会社が「持株会社」として複数の子会社を管理・統括し、グループ全体の経営戦略を一元的に策定・推進する体制です。これにより、経営資源の最適配分や事業ポートフォリオの管理が容易になり、リスク分散とシナジー効果の創出が期待できます。中小企業では、事業承継の円滑化、新規事業への挑戦、さらにはM&Aの加速を目的にホールディングス化を検討する動きが増加しています。
一方、一般的なグループ会社は、独立した法人同士が資本関係や取引を通じて連携するものの、経営方針は個社ごとに異なるケースが多く、全体最適を図るのが難しい場合があります。ホールディングス化するには、親会社がグループ全体の方向性やガバナンスを主導しやすい反面、設立や運営には法務・税務・組織再編に関する専門的な知識が欠かせません。自社に適した体制の判断には、最新事例や専門家の助言を参考にし、慎重に検討することが重要です。
ホールディングス化のパターン
ホールディングス化にはいくつかのパターンがあり、経営戦略や市場環境に応じて使い分けられます。
1. 純粋持株会社方式
持ち株会社が戦略立案やグループ全体の管理を担い、事業は子会社が遂行する形です。この方式は親会社が事業を持たないため、全体最適を重視する経営に適しています。
2. 事業持株会社方式
持株会社が事業機能を持ちながら他の子会社を管理します。中核事業を保持しつつ多角化を進める企業に多い形態です。
3. 分割型持株会社
既存の事業を分割し、持株会社がそれらを管理します。この方式は事業ごとに責任を明確化し、柔軟な運営を実現する際に有効です。
ホールディングス化のメリット
ホールディングス化は、多角化した事業を効率的に管理し、経営資源を最適に配分するための方式です。
この経営形態の採用には複数のメリットがありますが、特に注目すべき6つのメリットを解説します。
1. リスクの分散
一つ目のメリットは、リスクの分散機能です。この方法では、持株会社が複数の子会社を支配することで、特定の事業や市場の変動が持株会社全体の経営に与える影響を最小限に抑えることができます。
たとえば、一部の子会社が経済的な逆風に直面した場合でも、他の子会社の好調な業績が全体のバランスを保つことが可能です。
2. 経営資源の効率的な配分
ホールディングス化により、経営資源を効率的に配分することができます。持株会社は資金、人材、技術などの重要なリソースを集中管理し、それらを最も必要とされる子会社や事業領域に迅速に分割して配分することができます。
この方式により、グループ全体の戦略的な目標に基づいてリソースを最適に活用することが可能になり、全体としての競争力を向上させることができます。
3. 事業再編と成長戦略の柔軟性
ホールディングス化は、事業再編や成長戦略をサポートします。株式移転、株式交換、会社分割などの手続きを通じて、新たな市場への進出、買収、または不採算事業の売却といった動きを気軽に行うことができます。
これにより、持株会社は市場の変化にスムーズに対応し、成長機会を積極的に追求することができます。
4. M&A・事業承継の準備
ホールディングス化は、M&Aや事業承継の準備においても有効です。持株会社を設立することで、株式移転や組織再編が容易になり、後継者へのスムーズな引き継ぎが可能になります。たとえば、事業を個別の子会社に分割することで、承継対象を明確化し、後継者が経営に専念しやすい環境を整えることができます。また、M&Aにおいては、持株会社を活用することで買収後の管理体制を迅速に整え、グループ全体のシナジーを最大化する戦略を立てやすくなります。
5. 経営管理の高度化と意思決定の迅速化
ホールディングス化に伴い、各子会社は独立した事業体となります。持株会社は、事業別・子会社別の業績を独立した会計で正確に可視化することが可能です。結果として、各事業の収益性や効率性を客観的に評価できます。
グループ本社は、データに基づいた迅速かつ合理的な意思決定を下せるようになります。これは、事業が多角化している企業において、全体最適を実現するための強固な基盤となります。
6. 人材戦略の強化とプロ経営者の育成
各事業会社を独立させることで、子会社の社長や役員に大きな権限と責任を委譲しやすくなります。次世代のプロ経営者の育成が加速され、グループ全体の人材プールが強化されます。
さらに、グループ横断的な人材交流や研修プログラム(グループ人材マネジメント)を展開しやすくなります。この体制によって、優秀な専門人材を事業会社間で最適に配置・活用でき、グループ全体の組織力を向上させる効果も期待できます。
ホールディングス化のデメリット
ホールディング経営には多くのメリットがありますが、一定のデメリットも伴います。
以下では、ホールディング経営の3つのデメリットについて解説します。
1. コストの増加
ホールディング経営を実施する際には、新たな設立費用や、運営に必要な管理体制の構築に伴う費用が発生します。特に、純粋持株会社や事業持株会社の設立は、複数の子会社を効果的に管理し、統括するための専門家やシステムが必要になります。
これらの初期投資と維持費用は、特に中小規模の企業にとって重大な負担になり得ます。管理費用の増大は、持株会社の運営効率を下げ、全体の利益率にも影響を及ぼす可能性があります。
2. 意思決定の遅延
ホールディング経営では、重要な意思決定を持株会社レベルで行いますが、これが原因で意思決定のプロセスが遅くなることがあります。複数の子会社間での調整や、持株会社と子会社との意見の相違が意思決定を複雑にし、迅速な対応が求められる状況での行動が鈍る可能性があります。
また、子会社の自立性が高い場合、持株会社の方針との違いが生じやすく、統一された戦略の実行に支障をきたすこともあります。
3. 税務処理の複雑化
ホールディング経営を採用すると、税務処理が複雑になります。持株会社と子会社間での資金の移動、内部取引の価格設定、配当受け取りに関する税金の計算など、税務処理に関する専門知識が必要になります。
これらの複雑さは、企業が税務上の適切な対応を行うために、税理士や専門家への依存度を高め、結果として税務関連のコストが増加する原因となります。また、税法の変更に迅速に対応するためには、持株会社レベルでの監視体制と知識のアップデートが常に必要となります。
ホールディングス化における大切な5つのポイント
グループ経営で確立すべき仕組みとは?
これらの課題に対して、あるべきグループ経営とはどのようなものかを述べていきます。
目指すべきグループ経営とは、
- グループ経営としての共通した価値判断基準が存在している。
- 各事業会社よりグループ全体の最適化を優先する
(シナジー・事業ポートフォリオによる全体最適化) - グループ本社によるグループ全体におけるガバナンス構造
- グループ本社によるグループ全体のマネジメントシステム
- グループのオペレーションコストを最小化する仕組み
の5つがしっかりと確立している経営体制のことです。
では、5つのテーマとその内容について説明します。
グループ経営システムにおける5つのテーマとは、
- グループ理念の策定
- グループ経営企画機能の確立
- グループガバナンス機能の確立
- グループマネジメント機能の確立
- シェアードサービス機能の確立
です。
①グループ理念の策定
当然、多事業であることから各事業会社の事業理念などはすでに存在している場合が多いですが、グループとしてのミッション、ビジョン、バリュー(価値観)を明確にする必要があります。また、そのグループアイデンティティを策定するだけではなく、社内外にどのように発信、浸透させるかも決めることが大切です。
②グループ経営企画機能の確立
グループ企業価値(シナジーとポートフォリオ)の最大化を実現する戦略、方針、計画をする「グループ経営企画機能」の設計です。具体的には、グループビジョンマネジメント、事業ポートフォリオ(資源配分)の決定、グループ事業計画(予算)の策定、グループブランディングをどのように実施、運用していくかのルール・仕組みを構築することです。
③グループガバナンス機能の確立
グループとしてのルール、意思決定プロセス、権限と責任を明確化する「グループガバナンス機能」の設計です。具体的には、ホールディングカンパニーと事業会社のどちらにどこまでの責任と権限を持たせるか、その意思決定プロセスをどうするか会議体も含めて設計します。それ以外にもコンプライアンス・リスク管理や事業会社の監査制度なども含めたグループ諸規定の整備が必要です。
④グループマネジメント機能の確立
グループ全体を管理・評価するマネジメントシステムで、特に事業会社の業績向上を実現する「グループマネジメント機能」の設計です。具体的には、グループ管理会計システム、グループ業績マネジメント、グループ人材マネジメント、グループCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の設計になります。仕組み自体の構築になるが、この部分はどこまでシステム化するかも見据えた設計が不可欠です。
⑤シェアードサービス機能の確立
共通オペレーションの集中処理を実現する「シェアードサービス機能」の設計です。グループ全体におけるオペレーション業務の集中化と効率化が目的ですが、当然事業会社で実施したほうが良い業務もあり一概にすべてを集中化するものではありません。どこまでの業務をホールディングカンパニーで実施するかを判断する必要があります。一般的には財務会計、財務、債権回収管理、労務管理、給与関係、ITインフラなどを集中化することが多いです。
ホールディングス設立のステップ
ホールディングスを設立するためには、いくつかの重要なステップを順序立てて進めることが求められます。まず初めに、グループ全体の現状分析を実施し、財務構造の把握や株式の評価額、各部門・子会社の役割や収益構造を明確化することが必要です。この段階で現状の経営課題を整理することで、今後のホールディングス化の目的や方向性が定まります。
次に、株式移転・会社分割・株式交換など複数あるスキームの中から、自社にとって最適な方法を設計し、税務や法務の観点からリスクとメリットを検討します。特に、中小企業においては、後継者問題の解決や自社株対策、事業承継税制の活用を視野に入れたホールディングス化が増えており、専門性の高い知識が不可欠です。そのため、司法書士や税理士、社会保険労務士など外部専門家と密に連携しながら進めることが成功の鍵となります。
さらに、親会社と子会社それぞれの収益構造やガバナンス体制を再構築し、グループ内の責任分担や意思決定のフロー、社内外とのコミュニケーション体制を整えることも重要なポイントです。ホールディングス化は単なる組織再編ではなく、グループ全体の持続的成長を支える経営基盤づくりでもあるため、準備段階から慎重な検討と計画が求められます。
まとめ
ホールディングス化は、持株会社が親会社となり、グループ企業を統括する経営体制です。近年、事業承継やM&Aの増加に伴い、多くの企業がこの形態を採用しています。メリットとしては、リスク分散、経営資源の最適配分、事業再編の柔軟性向上が挙げられます。特に、M&Aや事業承継の準備がしやすくなる点も大きな利点です。
一方、コスト増加、意思決定の遅延、税務処理の複雑化といったデメリットも存在します。成功の鍵は、ガバナンスやマネジメント機能の確立、グループ理念の共有にあります。ホールディングス化を検討する際は、自社の経営戦略に適合するか慎重に見極めることが重要です。
タナベコンサルティングでは、資本・財務戦略と組織・人材戦略の双方の視点において、目指すべき将来像を描き、課題認識からホールディング経営の体制作りやグループ方針の作成に関する設計・構築を支援します。
ホールディング経営支援、グループ経営システム構築コンサルティングサービスの詳細は下記よりご覧ください。
【ホールディングス関連コラム】
- ホールディングス化・持株会社化の最適なタイミングはいつ?メリットも紹介
- 物流業のホールディングス化におけるポイント
- 建設業のホールディングス化におけるポイント
- ホールディングス設立のためのステップと考慮すべきポイント
- ホールディングス化を成功させる3つの手法
- ホールディングス化を検討すべき企業が知るべきタイミング
- 建設業のホールディングス化・持株会社化における戦略着眼とリスク
- ホールディングス・グループ経営におけるマネジメントとガバナンスのポイント
- なぜホールディング経営が選ばれるのか?再編コストフリーの時代
ホールディングスグループ経営の推進をご検討の場合には自社の現状を分析することが重要です。現状分析用チェックリストは下記より無料でダウンロードいただけます。
また下記オンデマンドウェビナーでは、企業事例を用いながらホールディング経営を成功に導くための実践的なメソッドをご紹介しています。
その他、下記コラムではグループ経営プラットフォームとしてHDCを機能させるステップや持株会社設計の際の留意点などについて紹介していますのでぜひご覧ください。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト