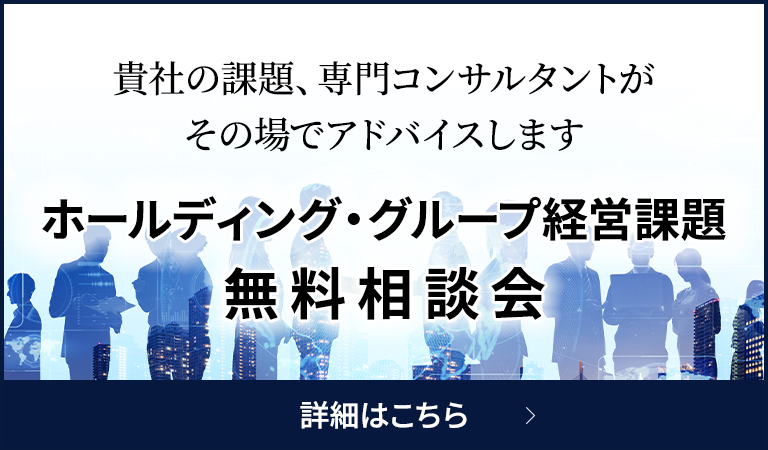グループ経営におけるシェアードサービス
- グループ経営

閉じる
M&Aによる企業合併や事業ポートフォリオ拡大により、グループ経営に向けた動きが加速している中、経営を効率化するための手段の1つである「シェアードサービス」の導入は、近年注目を集めています。
シェアードサービスとはグループ内で共通する業務や機能、システムを集約することで一元管理し、作業効率の向上やコストの削減を図る仕組みです。この「シェアードサービス」を社内機能として持つか、独立した「シェアードサービスカンパニー」として社外に持つかは、企業の規模や成長ステージ、経営戦略、状況に応じて適切に判断する必要があります。
本コラムでは両者のメリット・デメリットを比較・考察します。
社内シェアードサービスにおけるメリット・デメリット
社内にシェアードサービスを保有するメリットは以下の通りです。
【メリット】
1. グループ内のガバナンス強化
社内にシェアードサービス機能を持つことで、グループ全体のガバナンスが強化されます。業務プロセスやルールを統一しやすく、グループ全体としての一体感を醸成することが可能です。また、経営陣が直接管理することで、迅速な意思決定や柔軟な対応が可能になります。
2. コスト削減
社内設置の場合、外部委託に伴う手数料や契約コストが不要となり、長期的なコスト削減につながる可能性があります。さらに、社内リソースを活用することで、外部に依存せずに効率的な運営が可能です。
3. 機密情報の保護
社内にシェアードサービスを持つことで、グループ企業間で共有される機密情報が外部に漏れるリスクを最小限に抑えることができます。特に、財務データや人事情報などのセンシティブな情報を扱う場合、既存のセキュリティを利用することが可能であり、リスク低減効果があります。
4. グループ企業の特性に対応しやすい
社内設置の場合、グループ企業の特性やニーズに応じたカスタマイズが容易です。例えば、特定の業界や市場に特化した業務プロセスが必要な場合においても、ヒト・モノ・カネといった経営資源を柔軟に配分することが可能です。
また、社内にシェアードサービスを保有する際のデメリットは以下の通りです。
【デメリット】
1. 初期導入コストと運営負担
社内にシェアードサービスを設置するには、専用のシステムやインフラの構築、スタッフの教育、業務プロセスの見直しなど、多大な初期投資が必要です。また、運営にかかる負担もグループ企業全体で背負うことになります。
2. 専門性の限界
社内設置の場合、外部の専門的なノウハウや最新技術を活用する機会が限られる可能性があります。特に、ITや法務などの分野では、外部の専門企業の方が高度なサービスを提供できる場合があります。あくまでも1つの機能であるために、強化に割けるコストにも限界があります。
3. 柔軟性の欠如
社内設置では、グループ企業間での業務標準化が進む一方で、個別企業のニーズに対応する柔軟性が失われる可能性があります。これにより、現場の不満が生じたり、業務効率が低下するリスクがあります。導入にあたっては単なる機能の設置だけでなく、企業風土を踏まえたグループ会社や現場の理解が必要になります。
シェアードサービスカンパニーにおけるメリット・デメリット
シェアードサービスカンパニーとして事業会社と切り離して運用する際のメリットは以下の通りです。
【メリット】
1. 専門性の活用
シェアードサービスを社外に設置し、専門のシェアードサービス会社として運営することで、外部の専門知識や最新技術を活用することが可能です。例えば、ITインフラの管理や法務対応など、専門性の高い分野では、外部設置の方が質の高いサービスを提供できる場合があります。
2. コストの変動費化
社外設置の場合、サービス利用料を変動費として扱うことができるため、事業会社の固定費の削減につながります。特に、規模の変化に応じてサービスを柔軟に調整できる点は、グループ企業の成長や縮小に対応しやすいメリットです。
3. 外部顧客へのサービス提供
社外にシェアードサービス会社を設置することで、グループ外の企業にもサービスを提供することが可能になります。これにより、収益源を多様化し、グループ全体の収益向上を図ることができます。機能ではなく事業とすることで独自の収益創出が可能となることは、大きな特徴と言えるでしょう。
4. グループ企業間の公平性
社外設置の場合、シェアードサービス会社が独立した立場で運営されるため、グループ企業間での公平性が保たれやすくなります。特定の企業に偏ったサービス提供が避けられるため、グループ全体の信頼関係を維持しやすくなります。
また、シェアードサービスカンパニーにすることによるデメリットは以下の通りです。
【デメリット】
1. 機密情報の漏洩リスク
社外設置の場合、外部のシェアードサービス会社に機密情報を提供する必要があるため、情報漏洩のリスクが高まります。特に、財務データや人事情報などのセンシティブな情報を扱う場合、慎重な管理が求められます。
2. コストの増加
外部のシェアードサービス会社を利用する場合、サービス利用料や契約コストが発生します。これが長期的に見て社内設置よりも高額になる可能性があります。また、契約内容によっては、追加のカスタマイズ費用が発生することもあります。
3. グループ企業の特性への対応が難しい
外部設置の場合、標準化されたサービスが提供されることが多く、グループ企業の特性やニーズに十分に対応できない可能性があります。
これにより、現場の不満が生じたり、業務効率が逆に低下するリスクがあります。
4. 経営陣の統制力の低下
社外設置の場合、シェアードサービス会社が独立した運営を行うため、事業会社の経営陣が直接管理することが難しくなります。これにより、迅速な意思決定や柔軟な対応が困難になる可能性があります。
まとめ
シェアードサービスを社内に持つか、社外に持つか、どちらが最適かについては企業の戦略や状況によって異なってまいります。
社内設置は統制力や機密情報の保護に優れる一方で、初期導入コストや運営負担が課題となります。一方、社外設置は専門性の活用や収益源の多様化が期待できるものの、機密情報の漏洩リスクやコスト増加が懸念されます。
どちらの選択肢を取るにせよ、導入前に十分な計画と準備が必要です。
また、最も重要であるのは、自社がどのような成長をしていきたいのか、そこに向けてどのような戦略を取るのかといった、ビジョンや戦略との整合性です。単なる業務効率化を目的とした安易なシェアードサービスの導入は逆に企業の成長を阻害する要因にもなりかねません。さらに導入後も継続的な改善を行い、グループ全体の効率化と競争力向上を目指すことが求められます。
企業がシェアードサービスを最大限に活用するためには、メリットとデメリットを正しく理解し、自社の状況に最適な選択を行うことが肝要です。
関連記事
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~企業を取り巻く経営課題~
- 資本政策・財務戦略
-

中堅企業が実装すべき財務戦略~「財務価値分析」から見る経営実態~
- 資本政策・財務戦略
-

事例から学ぶROIC経営の落とし穴とは?
- 企業価値向上
-

-

-

-

企業価値とは?意味と評価方法をわかりやすく解説
- 企業価値向上
-

 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト