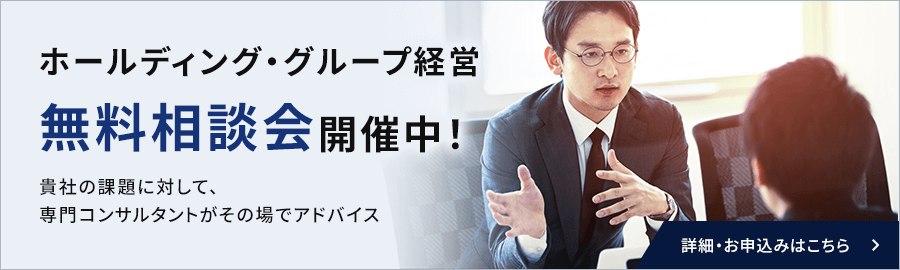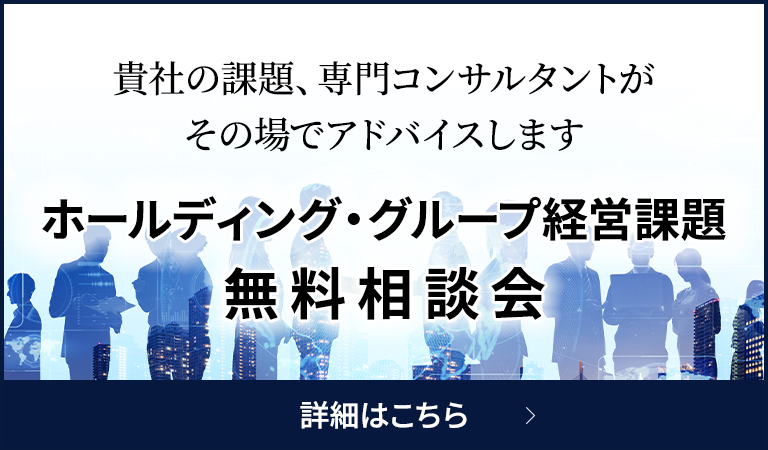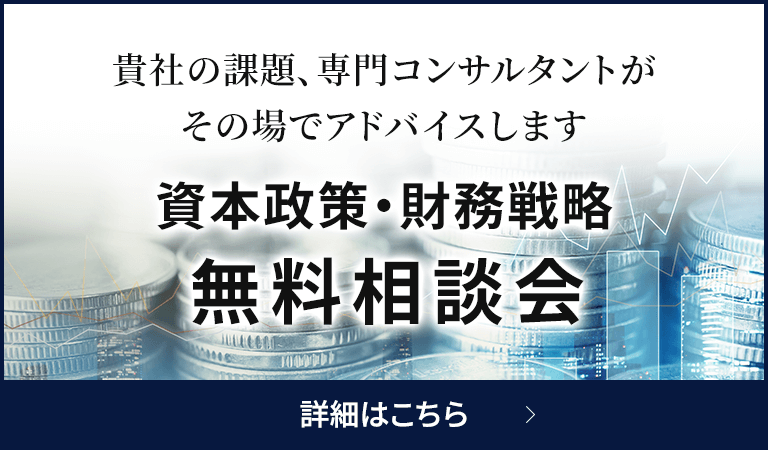シェアードサービスとは?
導入のメリットと成功事例
- グループ経営
- 資本政策・財務戦略

閉じる
近年、中堅企業や大企業において、シェアードサービスを導入する企業が増加しています。この背景には、単一事業での成長に限界を感じる経営環境の中で、事業の多角化や事業ポートフォリオ戦略が求められていることがあります。また、これらの戦略を推進する体制として、ホールディングス化やグループ経営体制を採用する企業が増えていることも一因です。本コラムでは、シェアードサービスの導入意義や実施方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
シェアードサービスとは
シェアードサービスとは、企業内の複数事業やグループ企業における共通業務を統合・集約し、専門的なサービスとして提供する仕組みを指します。これにより、業務の効率化・標準化、専門ノウハウの向上が図られるとされています。
統合の対象となる主な業務はコーポレート部門の業務であり、具体的には以下の業務が挙げられます。
(1)経理
(2)人事労務
(3)総務
(4)情報・ITシステム など
コーポレート部門の業務は、オペレーション業務として共通の内容となっているものが多く、統合・集約が図りやすいとされています。
シェアードサービスの導入意義と対象業務
シェアードサービスの導入は、企業にとって以下の意義を持ちます。
1. コスト削減
重複する業務を集約することにより、オペレーション業務における総作業時間の削減、またそれに伴うバックオフィス人員の削減を実現し、コスト効率を向上させることができます。
2. 標準化による業務品質向上
各部門や各事業会社でバラバラに実施されていた業務を統一することにより、業務の標準化が図られ、業務品質の向上が期待されます。これは特に、グループ企業間で業務品質のバラつきがある場合に有効に機能すると考えられます。
3. ガバナンス強化
業務の集約により属人的な業務を解消することができ、ガバナンス強化につながります。例としては、経理業務における不正防止が挙げられます。
またシェアードサービスの対象業務は、以下のようなものになります。
1.専門性が低いオペレーション業務
人事部門:労務管理、給与計算、社会保険手続き
経理部門:入出金管理、仕訳業務、経費精算
総務部門:備品・消耗品管理、施設管理、文書管理 など
2.専門性が高くノウハウの習得が必要な業務
人事部門:人事制度、採用戦略、エンゲージメント向上
経理部門:管理会計、資金調達、投資判断
総務部門:働き方改革、オフィス戦略、DX化・システム導入 など
シェアードサービスの導入企業事例
年商400億円の中堅運送業A社の事例
(1) 背景
A社は年商400億円の運送業という厳しい外部環境にさらされている業種ながらも、M&A戦略の実行により急成長を実現している企業です。ホールディングス化を行い、シェアードサービス部門はホールディングス内の組織として組成されています。
グループ企業数が20社を超える中、グループの共通オペレーションインフラとしてシェアードサービス機能を実装すること、グループ全体に関わる戦略機能を強化することが課題として挙がっていました。
(2) シェアードサービス機能の実装
A社はまず、グループ各社における共通業務の洗い出しと統合対象業務一覧を作成しました。統合する業務については、一律で定めるのではなく、統合対象業務一覧の中で各社ごとに統合すべき業務を判断しています。機械的に統合すべき業務を設定するのではなく、各社の業務運営体制を踏まえたうえでシェアード化すべき業務を判断していることがポイントになります。
(3) シェアードサービス部門におけるKPI設定
シェアードサービス部門では、集約した業務を担うだけでなく、いかに効率的にオペレーションをこなせているかを測るためのKPIを設定しています。具体的には、経理であれば処理した帳票枚数などの目標値を設定し、業務時間内でどれだけの各社のオペレーション業務を代行できたかを測定しています。このことが、業務の効率性を高めるという目標意識とオペレーション部隊のモチベーション向上に繋がっています。
(4) 成果
上記の取り組みにより、グループとしての経営効率が改善したのは言うまでもありませんが、特筆すべき成果として以下のものがあります。
財務部門に所属していた部長が、シェアードサービス機能を実装するまではオペレーションの管理にほとんどの時間を割いていました。しかし、業務の効率化や標準化が進んだことにより、戦略的な業務に従事する時間を捻出できるようになりました。M&A戦略の推進や財務戦略の構築がグループとして求められる中で、財務のオペレーションマネージャーから戦略人材へと進化する人材が輩出されたことは、大きなプラス要因となっています。
シェアードサービスの成果目標としてのコストダウンに関する考察
バックオフィスをミドルオフィス機能へシフトさせるという考え方
シェアードサービスの導入を検討する企業が増える一方で、「果たして本当にコストは下がるのか」と疑問を持たれることが多くあります。どのような条件でコストダウンの効果が出やすいのか、また留意点について以下に解説します。
1. 各社のバックオフィス部門に相応の人員(人数)が所属していることが必要
業務を集約化したとしても、各社に全くバックオフィス人員を置かない体制は非現実的です。各社・各事業の現場に寄り添ったスピーディな対応を維持するためには、最小限の人員を残すことが必要です。そのため、各社のバックオフィス人員がそもそも少数であった場合、集約によるバックオフィス人員のスリム化が実現しにくくなります。
2. 単に集約するだけでは効果は出ず、IT技術を用いた効率化が前提となる
単にバックオフィス業務を集約しただけでは、業務量自体が削減されない限り、コストダウンにつながることはありません。そのため、集約したうえでITシステムを活用し、新たな業務フローを設計・実装することが必要です。ただし、ITシステムの導入には投資費用がかかるため、初期段階ではむしろ費用が増加することが想定されます。単年度ではなく、中期的な視点で効果を検証することが重要です。
3. バックオフィスをミドルオフィス機能へシフトすることが必要
IT投資を実施し、業務の集約と効率化が実現したとしても、余剰となったバックオフィス人員の再配置という課題が残ります。バックオフィスの人員をフロント業務(営業など)に従事させることは現実的ではないため、現状の所属部門における企画業務・戦略業務へ業務内容をシフトさせることが基本的な対応方針となります。
上記の内容から、大企業や大規模なグループ組織を有する企業であれば、コストダウン効果は見込まれやすいですが、中小規模の企業がシェアードサービスを実装する場合は、コストダウンだけでなく戦略機能の強化という目的を捉えたうえで推進することが必要と考えられます。
関連記事
-

物流業におけるROIC改善事例を解説!企業価値を高める方法とは?
- 資本政策・財務戦略
-

資本政策 事例|押さえるべき3つのポイントを事例を基に解説!
- 資本政策・財務戦略
-

組織における意思決定の種類とは?トップダウン・ボトムアップの活用法を解説!
- コーポレートガバナンス
-

製造業における収益改善の2つの視点と5つのステップを徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

収益改善の成功事例 | 効果的なポイントについて徹底解説!
- 資本政策・財務戦略
-

-

中堅企業が実装すべき財務戦略~ホールディング経営におけるトップのリーダーシップ~
- ホールディング経営
 コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト
コーポレートファイナンス・M&Aの情報サイト