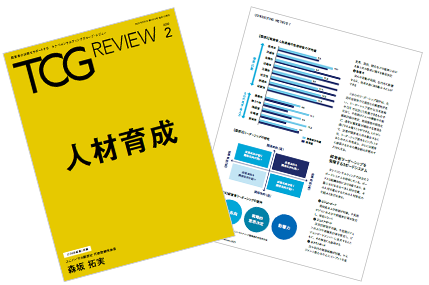人事コラム
成長する企業の経営者人材・幹部人材の育成方法とは?
短期的に利益を上げても伸び悩む会社と、長きにわたって業績が上がる会社とでは「明確な違い」があるそうです。その違いとはいったいなんなのか、詳しくみていきましょう。
成長する企業は、「経営者人材・幹部人材」を育てている
本コラムは『THE GOLD ONLINE』の寄稿原稿です。
2025年3月期、上場企業の利益は「過去最高」の見込みとなっています。しかし、短期的に利益を上げても伸び悩む会社と、長きにわたって業績が上がる会社とでは「明確な違い」があるそうです。その違いとはいったいなんなのか、詳しくみていきましょう。株式会社タナベコンサルティングの番匠茂執行役員が解説します。

成長する企業は、
「経営者人材・幹部人材」を育てている
2025年3月期、上場企業の純利益合計額は過去最高の見込みだ。決算期まで残り2ヵ月ほどだが、現実になれば4年連続での最高利益更新となる。
この要因として真っ先に考えられるのは「値上げ」だろう。単価アップは、企業収益におよぼす影響がもっとも大きい。
原材料や電気代などのあらゆるコストが上昇しており、人件費も上げなければ採用や定着が厳しい時代である。
ここ最近は、「いま値上げをせずに、いつ値上げをするのか?」といわれるほど値上げをしない企業が少ない。
物価高騰というよりは「物価が適正値に向かっている」と考えるべきだ。2024年は、デフレからインフレに明確に変わった年だった。
では、2025年以降はどうなるか?モノやサービスの価格はこれからも上昇することが予想されるが、これにともない企業間の収益格差もより広がっていくだろう。
そのようななか、世間の風潮に乗っかって値上げを繰り返す「外的要因」だけで収益を上げた企業と、「内的要因」もともなって、つまり、しっかり地力をつけて収益を上げた企業との差が明確になっていくと考える。
なかでも注目したいのが、経営者や幹部となる人材の「質と量」だろう。
これは企業経営において、好調時はその差が見えにくい部分だ。しかし、好調時にこそ、将来を見据えて、「経営者人材・幹部人材」をしっかり育成している企業は、長い目で見たときにそうでない会社と比べ確実に差がつくのである。

とある経営者からの"切実な相談"
15年ほど前、売上高70億円規模の製造業A社を経営するX氏から、「この10年で経営者人材を10人育成したいので、力を貸してほしい」との相談があった。
X氏は、その理由として、次の2点を挙げた。
1. 個人経営から組織経営への転換
X氏は「今後、自社や業界を取り巻く経営環境がさらに厳しくなることが予想され、経営者だけでなく、それを支える経営者人材を育成・強化しなければ、経営を未来に繋ぐことはできない」と考えた。
2.「経営者人材」が育っていないと、決断が遅くなる
さらにX氏は「今後、M&Aが活発になったときに会社の経営を任せられる人材(経営幹部)がいなければ、会社を買う・買わないという決断が遅くなる」と考えていた。
約15年前の話だが、この経営者は時代を的確に読んでいたといえる。
弊社では、企業が「1・3・5の成長の壁※」を乗り越えるためには、「売上高10億円につき、経営のわかる幹部が1名は必要である」と提唱している。
※企業の成長段階には壁があり、年商1億・3億・5億・10億・30億・50億・100億・300億と、節目ごとに経営体質を転換できなければ成長は頭打ちとなり、やがて成長は止まってしまうという考え方。
X氏は長年ワンマン経営で業績を伸ばしており、真に「幹部」と呼べる人材は少なかった。終始トップからの指示を待ち、"考えることをやめた集団"にも映っているという。
X氏と将来のビジョンについてディスカッションしたところ、社長としてのビジョンや経営方針・人に対する考え方は非常にいいものである一方、やはりそれを実現するための人材が揃っていない、育成できていないことが大きな問題点であるとの共通認識を持った。
そして、「10人の経営者人材を育てる」ことを目標に、より実践的な階層別研修を計画した。

「階層別研修」の結果、収益性が上がり
"筋の通った"企業に
階層別研修とは、社員を「管理者」や「監督者」、「リーダー」、「若手リーダー」、「中堅社員」など階層別に分け、それぞれ内容の異なる研修を行うことをいう。
まずは、リーダー候補10人(いずれも30代)を選抜し、定期的に管理・監督者研修を実施した。
さらに、社内公募でやる気のある若手社員を選抜した「若手リーダー」クラスには、A社の中期経営計画を策定させ、年度の経営方針に落とし込んでもらった。さらに、PDCAを回しながら実践させることを通じて、理想の経営者人材・幹部人材への成長を促した。
経営とは? 戦略とは? 管理とは? マネジメントとは? 部下育成とは?
......階層別研修によってこうした「経営者マインド」を学んだことで、A社はそれまでの「部分最適」(特定の部署内だけが効率的に業務を進められる状態)から「全体最適」(組織全体が生産性の高い業務を行える状態)へと働き方が変わり、各部署の経営的な視座も高まった。
また、研修では自社の貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー、管理会計、業績先行管理といった実務的な収益構造の基本も学んでもらった。これにより、それぞれが自発的に利益を生み出す行動がとれるようになった。
弊社では「教え・育てる」ことよりも、「自発的に学ぶことの重要性を理解させる」ことを重視する。そのため、こうした自発性を引き出す、気づきと学びを与える社内教育も階層別研修と同時並行で実施した。
その結果、A社は目覚ましい成長を遂げた。経営者人材・幹部人材だけでなく若手人材もしっかりと育っており、収益性も非常に高い企業となっている。「このまま行けば自社はどうなるか?」と先を見通し、「ではどうするか?」と対策を打った結果である。
A社の成功のカギは、幹部だけでなく、部下や若手社員にも目的を理解させ、浸透させたことにある。現場で働く社員と共通認識を持つ重要性を真に理解している会社はまだまだ少ないと感じているが、こうすることで経営計画の推進力は格段に違ってくる。

「人材育成」は、企業経営の一丁目一番地
弊社では毎年、日本全国の企業を対象にアンケートを実施している。その結果を見ると、「経営者人材の育成」「幹部人材の強化」は毎回、企業の課題として上位にあがる項目だ。
しかし、人材育成・強化の優先度は高いにもかかわらず、実際に時間とお金をかけて実施している会社はまだまだ少ないというのが実態である。
経営者人材・幹部人材を育てることが、会社の未来を決める。特に、今の時代はどの企業でも人材の採用・育成・活躍・定着が最重要課題である。いい経営者人材・幹部人材が育っていれば、新入社員の採用から若手社員の育成・活躍、中堅社員の定着にいたるまで、さまざまな分野に好影響をもたらす。
また、経営者人材・幹部人材は「未来の業績を作る人」でもある。この場合、業績とは「利益」と「利益を生み出す基盤」のことである。そして、基盤とは「顧客基盤・商品基盤・人材基盤」の3つを指す。
したがって、人材基盤を強化することで、企業におけるそのほかの2つの基盤(「顧客基盤」、「商品基盤」)の強化に繋がり、業績は上がるのである。企業にとっての一丁目一番地は、人材基盤の強化なのである。
企業経営者は自社を未来に繋ぐために、今一度真剣に「経営者人材・幹部人材」の育成・強化を考えてほしい。
関連動画