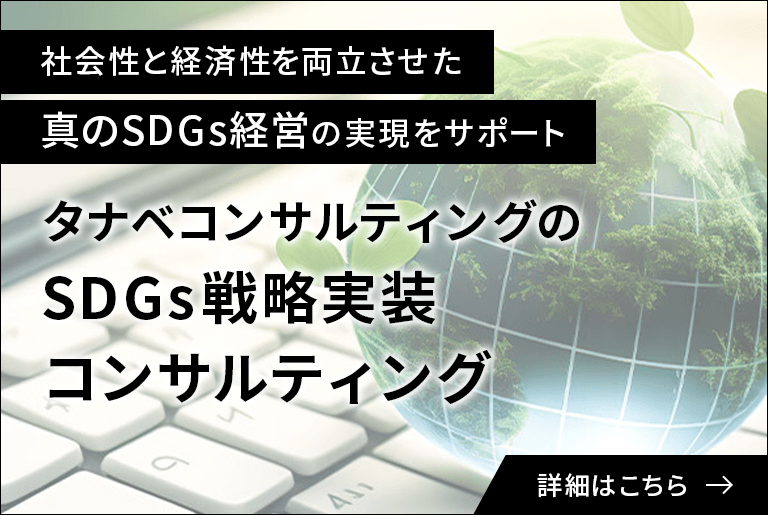COLUMN
コラム
閉じる
前回(https://sdgs.tanabekeiei.co.jp/vision/column/detail28.html)は、食品産業がSDGsに取り組む際のメリットや考え方についてお伝えしました。今回は、SDGsと食品業界・メーカーの関わりを紐解いた上で、サプライチェーンの川上に位置する食品メーカーが取り組むべき課題として、「食品ロス」と「従業員の働き方」の二つについて考えていきます。
食品業界・メーカーのSDGsとの関わりとは?
そもそもSDGsとは?
SDGs(Sustainavle Dvelopment Goals)とは、21世紀の国際目標として2000年にスタートしたMDGs(ミレニアム開発目標)の後継として、国連サミットで採択された2030年までに達成する国際目標で、「持続可能な開発目標」と訳します。「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現の為に、17の目標と169のターゲットが定められています。
食品メーカーとSDGsの関係については、農林水産省「SDGs×食品産業」にもまとめられている通り、人々の食を支える食品メーカーにとっては切っても切れないものとなっています。例えば、SDGs目標の3番「すべての人に健康と福祉を」では、食品や関連製品・サービスの提供を通じて、「人々の健康に大きく貢献すること」や、SDGs目標12番の「つかう責任、つくる責任」では、食品産業の事業活動による、エネルギー・資源の消費、廃棄物の排出などを「持続可能(サステナブル)な社会」の為に、どのように減らすかです。次の章では、もう少し踏み込んで、SDGsの食品メーカーにとっての価値を見ていきましょう
引用
農林水産省「SDGs×食品産業」:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/
食品業界・メーカーの課題と現状、なぜSDGsに取り組まなければならないか
農林水産省「SDGs×食品業界」によると、食品産業がSDGsに取り組む価値は3つあるといわれています。
1つは、事業を通じてSDGsの達成に近づくことができる「ビジネスの発展」の視点からみたものです。食品メーカーは様々な栄養素を含む食品を安定供給することで、SDGsが目指す豊かで健康な社会に貢献できる産業です。特に日本や世界の先進国では高齢化が急速に進み、人々の健康な生活を支えるためにどのような製品やサービスが必要か?という視点が重要になってきます。
2つ目は、SDGsが達成されないと事業の将来が危ないという「リスクの回避」の視点です。食品業界やメーカーは多くの自然資源と人的資源に支えられながら成立している為、SDGsが達成されずに環境と社会が不安定になることが、ビジネス上のリスクに直結しています。例えば、目標13の地球温暖化の例では、気温上昇や自然災害の多発によって、食品原料となる農林水産物の生産や事業所の創業が脅かされます。企業単位で見るならば、日本が超高齢化社会を迎える中で、継続的に事業の担い手を確保するためには、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」や目標8「働きがいも経済成長も」など人材に関するイノベーションも欠かせません。
最後の3つ目は、SDGsの達成に貢献できる企業であるか問われている「企業の社会的価値」という視点です。特に近年は、ESG投資と呼ばれる、Enviroment:環境、Social:社会、Governance:企業統治について配慮している企業に投資を行うという投資家行動が良く見られます。グローバル企業を中心に、環境負荷の低さや、人権・労働環境などの社会問題への配慮しているかどうかが世界的に問われてきており、グローバル企業のサプライチェーンの一部である、取引先などにも大きく影響してきています。日本の消費者においても、「エシカル(倫理的な)消費」と呼ばれる消費者行動が取り上げられるようになりました。これは、企業がバリューチェーンにおいて、環境負荷を抑制し、原材料等の生産者に不当な圧力をかけていないか、諸外国との取引であれば正当な貿易(フェアトレード)になっているかどうかチェックし、社会や環境に対して十分配慮された商品、サービスを買い求める動きです。
これらの動きによって、食品業界はSDGsの取り組みと切っても切れないものとなっており、グローバル企業だけでなく、中小・中堅企業にも広がる動きとなっています。

「おいしい」の裏にある大量生産・大量廃棄~食品ロスの現状と課題~
「安全・安心」「高品質」をつくり上げてきた食品メーカーの商習慣
日本においてもSDGsという言葉が以前よりも認知され、SDGs目標12番の「つかう責任、つくる責任」からも、食品ロスが大きな社会課題として注目されるようになりました。農林水産省によると、食品ロス量は年間570万トンと、前年度から30万トン減少しています(2019年度推計値)。しかし、食品ロス量を2030年度までに2000年度比で半減させるという目標には、まだ遠いのが現状です。
これは、メーカーや生産者だけの責任ではありません。食品ロスが発生する要因の一つには、日本の食品産業ならではの商習慣や、小売店の欠品回避意識、食品の安全性に対する厳しい意識があります。
例えば、野菜や果物などの生鮮品は、形が悪かったり傷があったりすると規格外とされ、出荷できません。また、食品流通には、高品質を担保するための「3分の1ルール」(食品の納入期限を賞味期限の3分の1以内とし、販売期間を確保する食品流通・小売業界特有の商習慣)があり、その期限を過ぎた製品の多くが廃棄となります。さらに、メーカーよりも小売店が優位であることから、欠品による販売機会の損失を防ぐために大量生産し、過剰在庫となる悪循環に陥っています。
このように、流通の前段階で多くの食品ロスが発生しています。もちろん安全も利便性も大切ですが、そのままでは食品ロス量は減りません。
メーカーが行うべき食品ロス削減の取り組みとは
近年、前述したような商習慣は問題視され、大手小売店やメーカーに少しずつ改善の動きがみられます。しかし、食品業界全体が変わるのを待っていたら、SDGsのゴールである2030年はすぐ来てしまいます。食品メーカーとして、食品ロス量を減らすために何ができるでしょうか。
注目を集めているSDGs取り組みの一つに「フードバンク」があります。規格外品や過剰在庫品、パッケージに印字ミスや傷がある製品などを、児童養護施設や子ども食堂、障がい者福祉施設、ホームレス支援団体などに届けることで、社会貢献と食品ロス削減を両立させる仕組みです。また最近は、こうした食品を格安で扱う小売店やECサイトもあります。
加えて、近年推奨されているのが、賞味期限の「年月表示」です。年月表示の場合、「表示月の末日」までが実際の賞味期限となります。日単位から月単位の管理にすることで、保管スペースや荷役業務、品出し業務などが効率化され、従来は出荷できなかった在庫も出荷可能となることで、廃棄量が削減できるといったメリットがあります。
【関連ページ】:
~大阪大学:「革新的低フードロス共創拠点」~ フードDXを用いたイノベーションで実現するサステナブル社会とは?
【事例】山崎製パンの「食を大切にする活動」
食品ロスの現状についてお話ししてきましたが、ここからは食料資源を循環させるモデルを実現している山崎製パンのSDGs取り組みをご紹介します。
参照
https://www.yamazakipan.co.jp/shakai/kankyou/pdf/2021/kankyou2021.pdf
山崎製パンは「食を大切にする活動」として、食料資源の有効活用と国産食材の利用拡大、食育活動などを行っています。また、生産工場では、5Sの徹底と全従業員参加の改善活動により、廃棄量を削減しながら品質の向上に取り組んでいます。
例えば、製造過程で発生するカット部分や食パンの耳などの端材を業務用商品や飼料に加工し、有効活用しています。また近年は端材を利用した商品開発も行い、新しい製品を生み出しています。
このように、食料資源を最大限に活用することで、市場に出る前の食品ロスを削減するだけでなく、端材の活用を原料費削減につなげる良いサイクルができています。
【関連ページ】:
SDGs成功事例を学ぶなら「SDGsビジネスモデル研究会」

消費者の健康に貢献するため、従業員の働く環境を整える
職場環境と健康
今も昔も変わらず食品メーカーに求められることは、「安全・安心」と「健康への貢献」です。しかし、現代の企業には、消費者だけでなく従業員の健康も、考えるべき大事な要素として求められます。
世界保健機関(WHO)憲章は、「健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない」と定義しています。人々の健康に貢献するために、まずは従業員が健康であること。これはとても重要なことです。多様性ある従業員が心身ともに健康であり、誰もが力を発揮できる職場環境をつくり出すことも、企業が取り組むべき重要なSDGsと言えるのです。
【事例】カルビーの「働き方改革」
カルビーグループは、全従業員がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、公正な評価・報酬の制度も含めた仕組みづくりを行っています。さらに、従業員の約半数を占める女性の活躍推進に注力するとともに、障がい者雇用の促進、外国人の活躍推進、LGBTの支援なども進め、グローバル水準でのダイバーシティー経営を目指しています。
引用
農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/goal_08.html#com_01
また、SDGsが掲げられる以前から、効率的かつ生産性高く働くことを目指して各種制度を導入。2020年には、従業員の多様なライフスタイルを尊重し、業務の質やスピードを上げることで成果の最大化を追求する施策として、柔軟な働き方を支援する「Calbee New Workstyle」を推進しています。
さらに、従業員の心身の健康に対しては「カルビー健康宣言」を掲げ、一人ひとりがイキイキと活躍するため体制を整えています。このような施策が、カルビーグループの企業価値をますます高めているのです。
参照
https://www.calbee.co.jp/sustainability/human-resources/workstyle.php
【関連ページ】:
SDGs成功事例を学ぶなら「SDGsビジネスモデル研究会」
最後に
食品産業が抱える課題は、1社で解決できるものではありません。しかし、2030年に向け、世界共通の課題を各社が自分事と捉え、企業のサステナビリティと社会のサステナビリティを両立させなければ、より良い未来は訪れないでしょう。
あらためて自社を見つめ、どのような企業でありたいかを考えてみてください。そこには必ず、SDGsと結び付く自社の強みや価値があるはずです。
著者
最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト