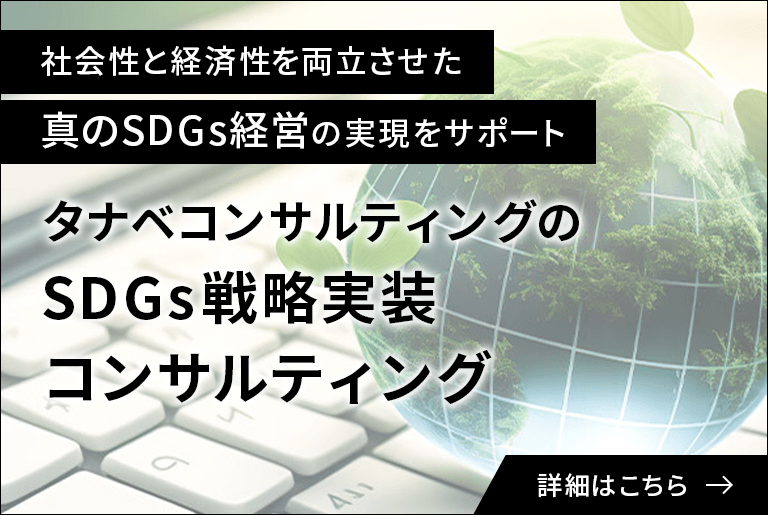COLUMN
コラム
閉じる
バリューチェーンの上流から下流まで関わる食品産業は、製品やサービスの提供を通じて、人々の健康に大きく貢献することが可能です。今回は、影響力の大きい食品産業ができるSDGsの取り組みを考えていきます。
今、なぜSDGsなのか。食品産業が取り組むべき理由とメリットとは
食品産業とSDGsの大きな関わり
食品産業は、人々の健康な生活のためにある業界と言えます。その中で得られる様々な知識や技術、思考がバリューチェーン全体の発展に繋がることで、健康のためのより良いサイクルが生まれています。
製品の原材料の多くは自然資源であり地球温暖化などの環境問題や、産地の労働問題にも関わります。今後、世界人口は増加し、日本の人口は減少さらに超高齢社会へと変化していく中で、労働力不足はもちろん食べる人が減るという食品産業の存続に大きく関わる問題がやってきます。これらの問題は世界の抱える問題、つまりSDGsと直結していると言えるのです。
取り組むメリットとポイント
とは言っても、SDGsの取り組みは義務ではありません。労力やコストをかけてまで取り組むメリットは何でしょうか。
一つは、食品ロス削減やエネルギーの効率化などによるコスト削減です。単にコスト削減ができるというだけでなく、廃棄しないための仕組み作りが、環境保全や社会貢献に繋がります。
近年では、教育の場にSDGsが取り入れられ若い世代の関心度が高く、企業選びの基準にもなっていることから、人材確保のためにも取り組むべきと言えます。
また、SDGsと本業を結び付けることは企業にとって新たな価値を生み出す可能性があるという点もメリットです。

食品産業にできること
人や社会に対してできること
では実際にできることは何でしょうか。「人・社会」「地域・環境」に分けて考えていきます。
人と社会という部分で一番イメージしやすいのは、食品ロス削減活動やフードバンクへの寄付・支援、食育活動、フェアトレードの取り組みではないでしょうか。また、他の業界に比べて女性の就業率が低い食品産業では女性の働きやすい環境づくりや、労働力不足に備え働き方改革の推進やIT化も視野に入れる必要があると言えます。
環境や地域に対しできること
太陽光パネルやLEDの導入、プラスチック容器の見直しや3Rの推進は多くの企業で進められており、サプライチェーン全体で省エネ、CO2削減の動きがみられます。また、食品産業は各段階で多くの水を消費します。食物のほとんどを輸入に頼る日本は、世界の水不足や安全な水についてももっと考え、使用水量の削減や水質確保など何らかのアクションを起こすことも必要でしょう。
【関連ページ】:
食品業界・メーカーの課題~食品ロスと従業員の働き方
今後取り組むべきこと
取り組む際のポイント
食品産業は1~17の全てのゴールに対して何らかのアクションができる業界だと私は思います。その中で企業は、何ができ、何ができないのか、今後どうしていくべきなのかを考えなければなりません。
SDGsを本業と結び付ける際のポイントは下記3点です。
(1)本業に目標を当てはめるのではなく、目標全体に対し何ができるかを考える。
(2)自社だけでなく、サプライチェーン全体として考える。
(3)過去に倣わず、新しい感覚や発想を取り入れる。
まずは自社の関わりが深い課題から考えてみてください。
最後に...
SDGsを考えるうえで、おそらく何も取り組めていないという企業はないはずです。
視野を広く持ち、もっとできることは他にないか、一緒に考えていきましょう。
【関連ページ】:
SDGs改善|食品メーカー・業界の取り組み
著者
最新コラム

- 物流事業者が2030年に向けて打つべき手

- ビジネスモデルを構成する収益モデルとバリューチェーン

- バリューチェーンとサプライチェーンの違いとは?それぞれの役割と事業戦略の進め方

- パーパスと経営理念の違いとは?パーパス戦略の基本とその重要性を徹底解説
ビジョン・中期経営計画策定キーポイント

- 新規事業を成功させる市場調査のポイントと
進め方・方法について解説

- パーパス経営完全ガイド
~成功事例から社内浸透のポイントまで徹底解説~

- 新規事業開発・立ち上げ完全ガイド
~発想や進め方など重要なポイントを解説~

- ESG経営完全ガイド
~SDGsとの違いや経営に活かすポイントまで徹底解説~
資料ダウンロード

- 製造業企業事例集_vol1

- 長期ビジョン・中期経営計画に関する企業アンケート調査レポート2025年

- ストラテジー&ドメインコンサルティングメニュー紹介資料

- 統合報告書 ストーリー設計のコツ~企業価値は「説明」では動かない。「物語」が動かす。~

- 設備工事業界の未来を切り拓く:課題解決と成長戦略の最前線~人手不足からデジタル化まで、業界の変革を支える実践的アプローチ~

- TCG REVIEW 顧客創造モデル

- 収益構造を変える!ビジネスモデル・イノベーション~高収益を実現する事業ポートフォリオとPLのデザインはできていますか?~

- 食品業界の企業が中期経営計画策定で押さえるべきポイント~重要になるテーマと事例5選をご紹介~
 長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト
長期ビジョン・中期経営計画策定の情報サイト