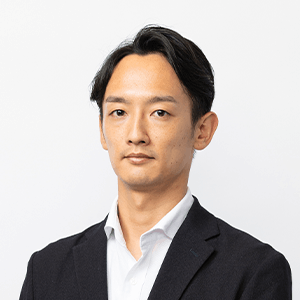1.営業プロセス改革の本質
営業プロセス改革の本質は、営業プロセスの最適化です。営業プロセスの最適化とは、営業活動の分業化および専業化による高生産性モデルの確立を指します。ただし、分業化、専業化によって分かれた活動が一連の流れとなる必要があります。それぞれが個別に動いてよいというわけではなく、営業の成果である売上に紐づけて、各組織が専門性を高めると同時に各チームの活動がつながっていることが肝要です。
2.各専門領域のポイント
営業プロセスを分けて組成された各部門が、それぞれ専門部隊としてどのように高生産性を生み出しているのかご紹介させていただきます。
(1)リード創出【デジタルマーケティングチーム】
ターゲットとなる新たな顧客を見つけ、その顧客に情報を届け行動を促すことが、リード創出を担うデジタルマーケティングチームの役割です。
① 外部環境分析や営業担当者へのヒアリングを通じて内部環境を分析し、ターゲットを設定した後、営業を目的に設計されたウェブサイトを立ち上げます。顧客が探している情報を掲載することで、ウェブサイトへの集客を狙い、訪問者に自社の製品・サービス・課題解決方法を知ってもらいます。ウェブサイトを通じてデジタル上で接点を構築することは、すぐにお問い合わせや購入に至らなくても、その後の関係性を構築するために必要な情報を取得する場となります。そのため、顧客が探している情報を掲載し、"見に来てもらえる"状態を維持する必要があります。顧客が求める情報には、業界レポートやホワイトペーパー、成功事例、ケーススタディなどがあります。
② 営業を目的に設計されたウェブサイトを立ち上げた後、SEO対策や広告出稿を行い、ウェブサイトへの集客を目指します。また、展示会への出店など、イベント実施も集客において重要な役割を果たします。コロナ禍ではオンライン実施に切り替わりましたが、現在はリアルとデジタルが組み合わさったハイブリッド型の集客施策を進める企業も増えています。Zoomなどのシステムが一般化し、ウェビナーを行う企業も珍しくなくなりました。ウェビナーでは、お客様に興味を持ってもらうための取り組みが行われています。例えば、特定の業界向けのソリューションを提供するために、パートナー企業と共同で開催するなど、自社だけでなく他企業を交えたイベントを実施している企業も多くあります。
③ 集客戦略として、特定の顧客に絞ったアカウントベースドマーケティング戦略を採用する企業も増えています。例えば、高価格取引が望める顧客に集中した施策を実行している企業や、特定の顧客に合わせたコミュニケーションを行うことで、見込み顧客の獲得から成果につなげるまでのリードタイムを短縮している企業があります。
上記のように集めたデータは、その後の営業プロセスに活かすために顧客基盤として資産にしていくことが重要です。CRMやSFAといったシステムの導入が一般化していますが、資産として残すためには、どのような顧客情報を収集・分析し、どのようなアクションにつなげるのか、データをどのように活用するのか、戦略を立てる必要があります。
(2)一次対応【インサイドセールスチーム】
インサイドセールスチームは、顧客のニーズを見極め、興味を喚起し、商談へと昇華させることが重要な役割となります。
① 顧客のニーズを見極めるためには、リードスコアリングシステムを導入し、得られるリードの行動や属性データに基づいたスコアをもとに行います。例えば、高スコアのリードは営業チームに優先的に引き渡し、低スコアのリードはナーチャリング対象として関係性を築き続けます。
② リードに対するフォローを自動化することで効率化を図ることができます。事前に設定されたメールテンプレートとシーケンスを使用してリードに対するフォローアップを自動化し、営業担当者が行うべきタスクを自動的に生成し、リマインダーを送信することでフォローアップの漏れを防ぎます。
(3)二次対応【営業チーム】
専門性を活かし、ターゲットの課題解決に向けた提案が役割となります。営業は案件の受注に向けて、リード創出から育ててきた顧客のクロージングを行います。
① 関係性の強化に向けた最低限抑える情報
これまでリード創出から一次対応を通じて、自社と顧客の間で築いた関係をより強固にしていきます。そのために、顧客の行動とニーズを把握し、一次対応までに提供してきた情報がどういった内容だったかを把握しておく必要があります。これまでの内容と営業自身が話す内容に矛盾が生じないようにし、不要な不信感を生まないようにします。
② 顧客の決め手となる情報の提供
情報の提供 顧客に対して行ってきた認知・興味喚起の活動で商談化できたとしても、顧客の状態は業界・業種・製品・サービスによって様々です。情報収集段階、検討段階、最終意思決定段階など、どの段階でも自社の強み・特徴を顧客の決め手となる形で伝える必要があります。「○○な機能」「○○が強み」ではなく、顧客が自社の製品・サービスを活用しているイメージを持たせることが重要です。顧客と同業他社の活用事例や、同様の課題を持った他社の解決事例を話すことで、顧客がよりイメージしやすくなります。
③ 営業自身の活動も資産
これまでの活動で蓄積してきた顧客の情報と同様、営業パーソンが行う活動も資産として蓄積していく必要があります。受注が目的ですが、顧客との関係は受注後も続きます。受注後のアップセル、クロスセル、新たなニーズの発掘など、その後の活動に活かすためにも営業パーソンの活動を蓄積することが重要です。
最近では、通話のログを自動的に記録し、必要に応じて通話内容を録音するツールも登場しています。これらのツールを活用することで、情報の蓄積を図りながら効率化を進めることが重要です。また、AIによる売上予測や失注可能性の予測を行うシステムも出現しています。CRM統合型やクラウドベースの機械学習プラットフォームなど、様々な選択肢があり、企業に合わせたツールを選択し、AIを活用した予測をもとに次のアクションを立てることが可能になっています。さらに、企業がパートナー企業との関係を管理し、パートナーシップの効果を最大化するツールも登場しています。PRMツール(パートナーリレーションシップマネジメント)は、パートナーのオンボーディング、トレーニング、コミュニケーション、パフォーマンス追跡などを支援します。様々なツールを活用しながら、営業パーソンの活動を生産的な活動に集中させ、データを資産として蓄積していく活動を継続して実行することが重要です。
(4)アフターフォロー【カスタマーサクセスチーム】
カスタマーサクセスチームは、顧客の成長を支援し、顧客体験価値を最大化することが役割にな
ります。
顧客の成長を支援し、顧客の体験価値を最大化するには、顧客のエンゲージメントを追求し、自ら積極的にフォローアップする取り組みが必要です。アップセルやクロスセルの提案だけでなく、顧客との信頼関係を継続して築くためにも、顧客の状況を把握しながら先んじて対策を打つことが求められます。そのためには、顧客の行動のスコアリングやフォローアップの仕組みづくりが必要です。また、各社にパーソナライズされたコミュニケーションを行うことで、エンゲージメントの向上やリテンション率の向上を図ります。
3.顧客起点のアプローチ
(1)営業プロセスの各専門チームが顧客起点のアプローチをすることで、一貫したコミュニケーションを生み出し、顧客との関係性構築を図ることができます。一貫したコミュニケーションを生み出すには、営業プロセス専門チーム同士の情報共有だけでなく、組織間の連携が必須です。各チームの活動内容やKPIを共有し、ターゲット顧客に合わせた活動を各チームが行うことで、一貫したコミュニケーションにつなげます。
(2)顧客が購入するまでのプロセスを支援するという考え方も顧客起点のアプローチに含まれます。認知・興味喚起・検討比較・購入・リピートの中で、当社や製品の魅力を感じてもらうことは前提ですが、スムーズな情報のやり取りや契約のわかりやすさ・進めやすさなど、購買プロセスそのものの体験価値を向上させることで、よりファン化を目指します。
(3)専門チームそれぞれのKPI設定を売上に紐づけ、各チームの成果が売上につながるように設計する必要があります。営業プロセスにおける最終のゴールは、成果・売上の創出です。成果からロジックツリーを広げ、それぞれのチームのKPIを設定し、各チームの活動が最終成果に紐づくように活動することが重要です。
4.まとめ
営業プロセス改革の本質は、営業プロセスの分業化・専門化による最適化です。分業し、専門チームを作ることで各プロセスの深さを出しながらも横の連携を進めることが大切です。その中で、AIなどの新たな技術、システム、ツールが多く登場しています。それらを使いこなしながら専門性を高め、連携力も強化し、一連の流れを構築していくことが求められています。改めて、営業の成果である売上に紐づけて、営業プロセスの各専門チームが専門性を高め、各チームがつながった活動を行うことが、営業プロセスの改革に求められています。

 デジタル・DXの戦略・実装情報サイト
デジタル・DXの戦略・実装情報サイト